【冒険の記録】「自然と人の共存」をテーマに撮り続けた釣り写真家が伝えたいこと
その道をリードする人に、これまでの歩みについてお伺いする「冒険の記録」。今回は日本の釣りカメラマンの第一人者として、約40年にわたって、この道を切り拓いてきたさん写真家・津留崎 健(つるさき けん)にこれまでの人生における転機や現在にいたる足跡をお聞きました。
水を感じる写真を目指していた
水を感じる写真を目指していた
――津留崎さんの写真を拝見していると、魚にも意思や表情があると感じる時があります
「やっぱり魚は生き生きとしてなきゃダメだよね。それは釣りをやってないとわからない部分もあって、魚の目付きとか色合いとか、どういう状況が元気なのかっていうのをわかってないとシャッターは押せないよね」
――こういう写真は水中に潜って撮影しているのでしょうか
「もちろん水中カメラで撮影しています。僕は若い頃から『水を感じる写真』を目指していました。水があって、魚があって、それで釣り人がいるっていうことを大切にしたいなと」
――水中写真は最初の頃からですか?
「1987年に雑誌の表紙になった写真があるんだけど、これは川の中に飛び込んで撮りました。当時釣り写真の世界に水中写真を持ち込んだ人はいなかったんですよ。あの頃はまだ若手だったから、自分が名前を売るにはこれを確立するしかないと考えていました」
――いま見てもすごい表紙ですね。その他に大切にしていることはありますか?
「臨場感ですね。僕の写真を見てくれた人がうわっと思った瞬間、その写真の中に入ってるみたいな、自己投影できる写真、心が動く写真を撮りたいといつも思っています」
釣りとの出合いと音楽の道
釣りとの出合いと音楽の道
――生まれは福岡の久留米ですが、どんな子供時代でしたか?
「僕の父は油絵画家だったんですが、風景画を描いていたので、小学生の頃からパレット持ちとして、山や渓流に行っていました。でも子供としてはやっぱりつまらない。それで、親父が釣り好きだったこともあり、釣り竿を買ってくれました」
――そこで釣りを始めるんですね
「その時に初めて釣れたのが天然物のヤマメだったんです。魚を見たら『パーマーク』っていう碁盤の目のような模様が魚体にあってそれが本当に綺麗で、こんなに美しい魚がいるんだと感動して。その時、漠然と何かを残すようなことがしたいと思いました」
――釣りはそれ以降も続けていたんですか?
「釣りは好きでずっと続けていましたね。でも、小さい頃はシャイだったので、性格を変えたい、と思っていました。それもあって中学生の頃に音楽を始めたんです。気づいたら夢中になっていて、10代の頃は頭の中は音楽でいっぱいでした」
――音楽は長く続けたんですか?
「高校生の時には久留米でバンドを組んで活動を始めたんです。当時の福岡はバンド熱がすごくて、自分がトリのイベントで、若手で良いバンドがいる、と聞いて前座をやってもらったら、それが今のチェッカーズだったなんてこともありました。その頃、オーディション番組の『君こそスターだ!』に応募したんです。1年かけて予選を勝ち抜き全国大会に出場して、第28代目のグランドチャンピオンになりました」
――すごいですね。
「この番組のチャンピオンには歌手デビューの道が約束されていました。ところが、番組が終わるタイミングだったこともあり、優勝したのに力を入れてくれない。それで結局言われたのが『演歌を歌ってみないか』でした。当時の僕はピアノの弾き語りをやっていたので、それならデビューしたくないと断って、もう1回自分を探してみようと、故郷の九州に戻りました。当時、大学では写真学科でしたが、休学中だったので、復学して改めて勉強し直そうと思いました」
大学在学中に写真が雑誌の表紙に採用される
大学在学中に写真が雑誌の表紙に採用される
――復学後はどんなことをやっていたんですか?
「戻ってからカメラと釣り竿を持って九州を回る旅に出たんですよ。その時にまたヤマメに出合ったんです。子供の時と同じように、その美しさに感動しました」
――その時はどんな心境だったのでしょう?
「自然と接していけば、僕の生きる道が見つかるんじゃないかなっていう気がしたんです。音楽に一生懸命に取り組んで、でも大人の都合でそれが挫折した時に、改めて発見したのが自然でした。そこで頭を切り替えて、カメラマンになろうと思いました」
――デビューまでの流れを教えてもらえますか?
「大学3年の時に撮った写真を東京の釣りの出版社に送ったんです。そしたらそれが表紙になり、10数ページの巻頭特集になった。その後、その出版社に挨拶に行ったら、編集者に『明日、源流に行くんだけど来てみる?』と聞かれて、いきなり翌日から撮影でした」
――すごい展開ですね
「険しい渓流を遡行して無事に撮れたけど、帰りは雨が降って増水したんですよ。もう逃げるところがないくらい水かさが増えて、戻るには滝の上から飛び込むしかない。意を決して、カメラをカッパにくるんでザックに入れて、先に落として、それから自分も飛び込みました」
――大変でしたね
「でも、あそこで飛び込んだことで、出版社側も『こいつ結構いけるんじゃない?』と思ったらしいです。大学卒業後は東京に出て、写真を撮らせてもらうようになりました。最初はちょっとした撮影だったんだけど、次第にいろんな仕事をやらせてもらえるようになりました」
――そこから40年間ずっと釣りカメラマンですか
「僕自身、このままずっと釣りのカメラマンでいいのかな、と考えることは何度もありました。雑誌の表紙の写真を撮っていても、『釣りなんて』と言われたり。自分が思っているよりも、人って自分のことを見てないんですよ。だから、やり続ける
神様が撮らせてくれた一枚
神様が撮らせてくれた一枚
――釣りの写真は釣った魚がどこから出てくるか分からないので一発勝負ですよね
「だから、釣り写真は機材が必要なんです。マクロレンズ、望遠レンズ、4×5と呼ばれる大きなカメラから、水中撮影の装備とか、もう機材だらけ。でも後悔したくないから全部必要なわけです。それでも自然が相手だと、失敗したり、その反対に思いもよらない良いものが撮れる時もある。だからいつも新鮮な気持ちで被写体と向き合えるんです」
- ――1995年には『Tamagawa東京ネイチャー』(つり人社)という多摩川の写真集も出されてますよね
「多摩川の源流は奥多摩にあります。そこで生まれた水は上流の八王子で取水して、水道局を通って東京都民の飲み水の一部になるわけです。その水を飲んで我々の体を通ったものが、今度は下水道局に集まります。そこで濾過されてきれいになった水が、八王子より下流の国立とか府中あたりの多摩川から流されて東京湾に辿り着くわけです」
――そうなんですね
「だからあの辺から下流の水っていうのは、人間の体の中を通った水であり、いうなれば人間を生かしてくれた『命の水』ともいえます。その水の中でアユやマルタウグイが東京湾から遡上してきて産卵する。自分たちの体を通った水で命が育まれている。それはもう我々と親戚みたいなものだし、そこにすごくストーリーがあるなと思いました」
――多摩川は浅いですし、水中写真が大変そうですね
「大変でしたよ。浅い川にウェットスーツを着て、じっと1時間ぐらいカメラを構えてると、『あの人動かないわね、溺れてるんじゃないか』って近所の人に『大丈夫ですか!』って声をかけられたことが何度もありました」
-
――大変でしたね。このアユが孵化した瞬間の写真は特に生命力を感じる力作ですね
「産卵するタイミングが、10月後半の大潮の一部分だけなんですよね。日にちが限られているうえに、その日に雨が降ると卵が流されちゃう。さらに雨になると透明度が低いから撮影できない。そうなると来年になる。結局、この写真集は撮影に13年かかりました」
――それはすごいですね
「アユの卵は、石にくっついて出てくる直前になるとピクピクっと動くんだよね。それにピントを合わせて構えてるんだけど、動くとピントがずれるから一切動けない。川の流れがある中で、ずっと踏ん張りながら構えてる。この写真はたぶん神様が僕の努力を見て撮らせてくれた1枚だと思います」
素晴らしい自然の中にいることに気づいてほしい
素晴らしい自然の中にいることに気づいていない
-
-
――津留崎さんの写真を見ていると、釣り人も自然の中の一部なんだなと思わされます
「僕の仕事っていうのは、釣り人だけではなく、自然を含めて撮影することで、人間だけが偉いわけではなくて、自然と協調することによって、よい魚と出合えているんですよ、こんな綺麗なところで釣りができて、あなたは幸せですよ、ということを伝えることだと思います。写真はそれが伝わりやすいから、僕の写真がそういう気付きの入口になったらいいなと思っています」
-
プロフィール
1960年、福岡県久留米市出身。九州産業大学芸術学部写真学科卒業。雑誌や広告写真などを中心に活躍。自然環境と釣りをテーマにした撮影を続けている。1990年、日本写真家協会激励賞受賞。『キャッチ&リリース』『幸福の森』『写真集・フライフィッシング』『絶景・日本の釣り』『Tamagawa東京ネイチャー』などの写真集を上梓。
https://kentsurusaki.com/



















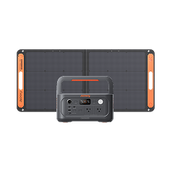





































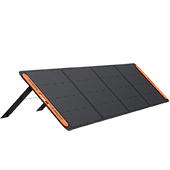



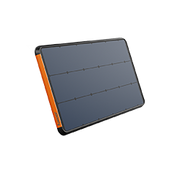










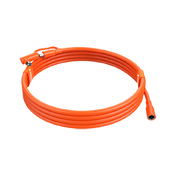
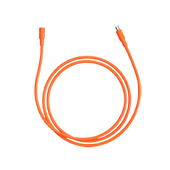
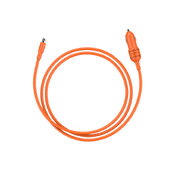

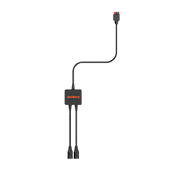



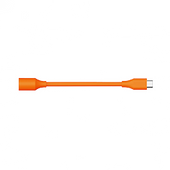

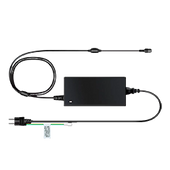
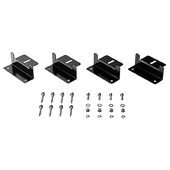




































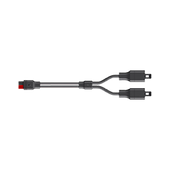











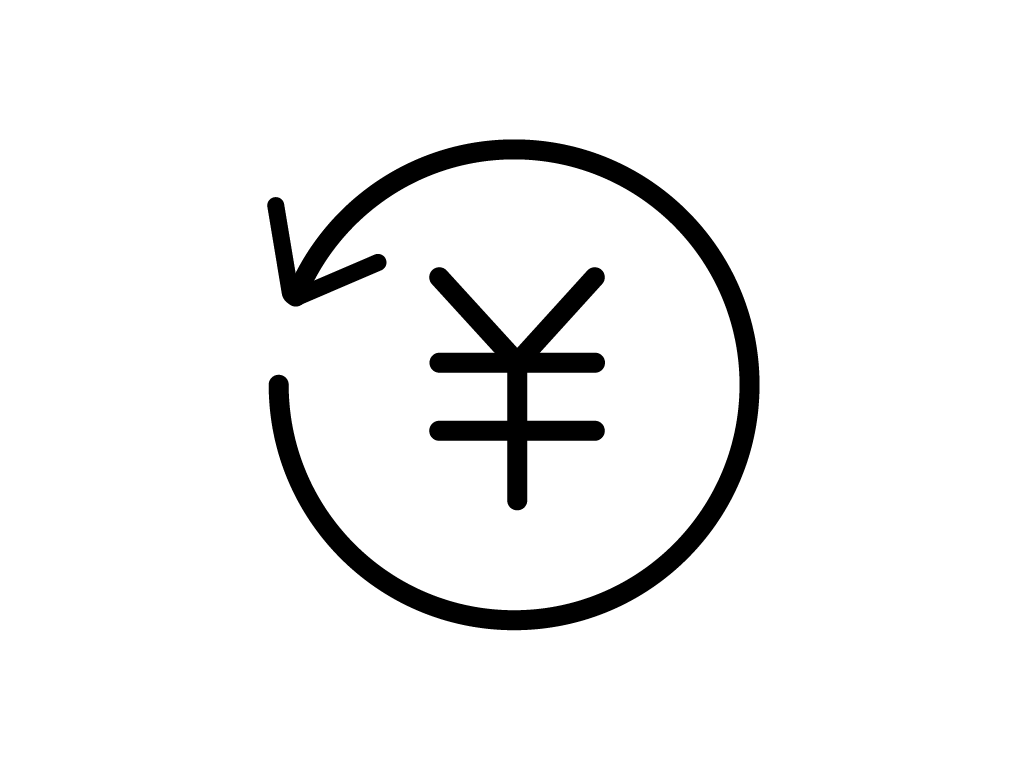

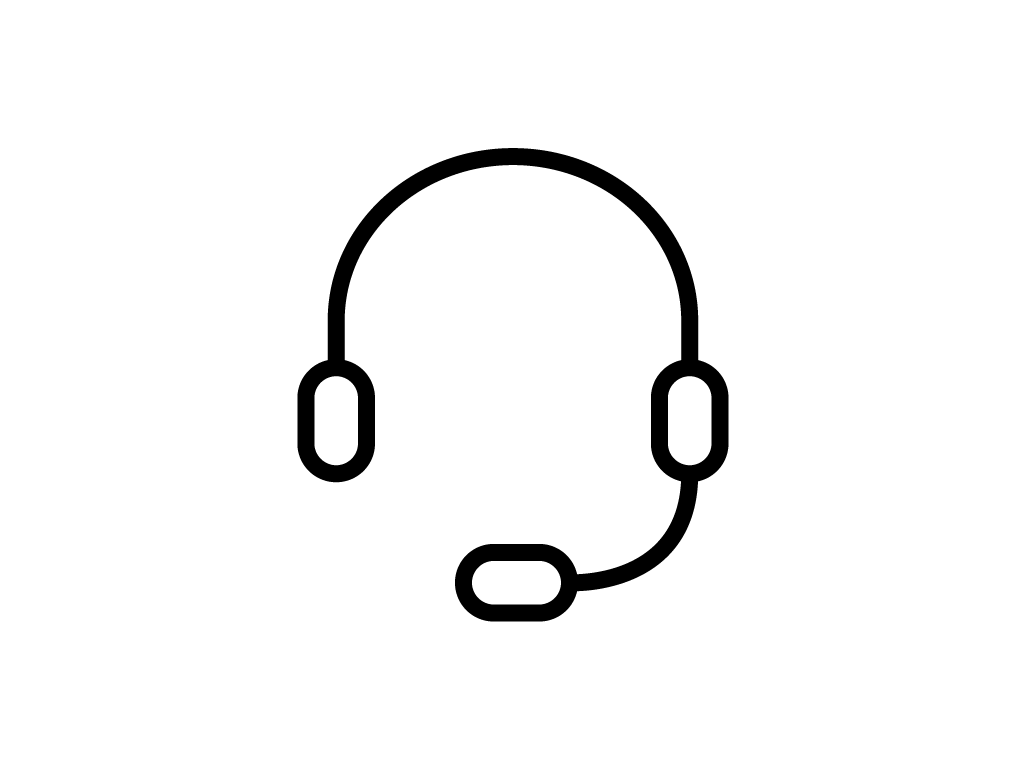
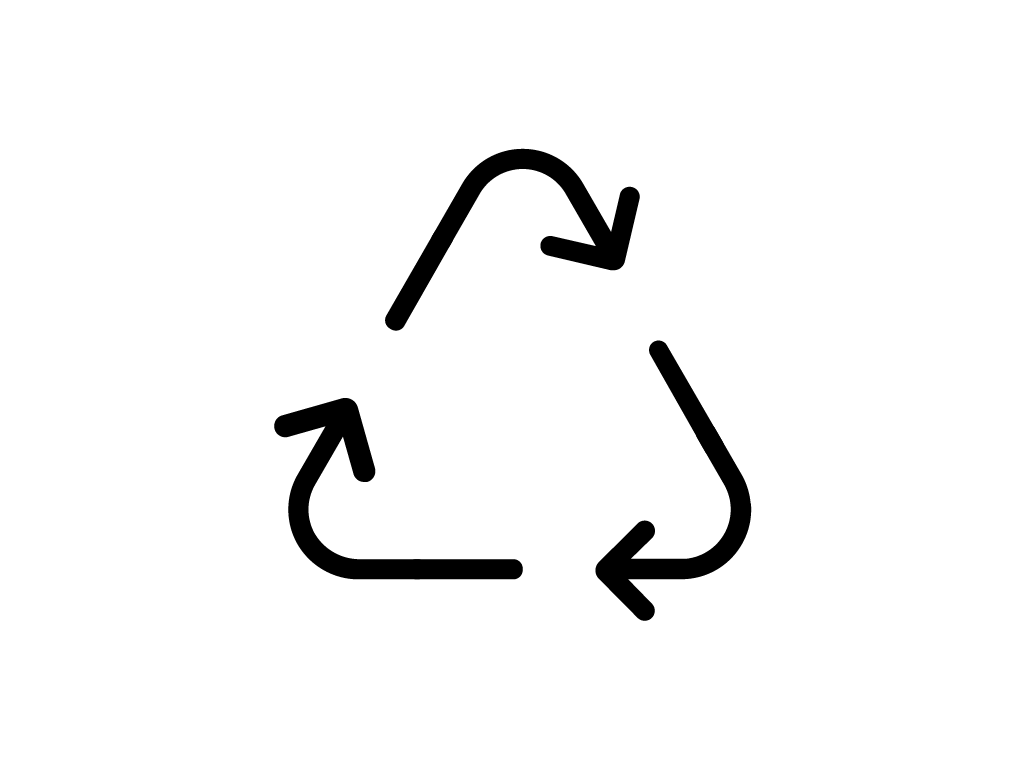
コメント