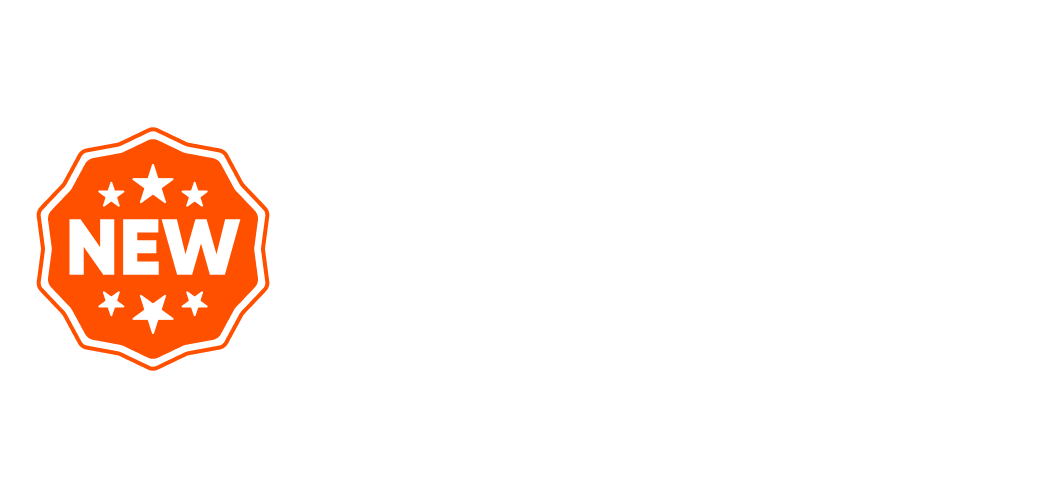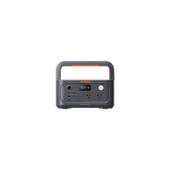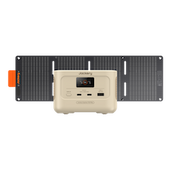1.災害やリスク対策を担う「BCP資格」とは?
BCP資格は、事業継続計画に関する専門知識とスキルを証明する資格制度です。企業の危機管理体制を強化し、災害時の適切な対応力を身につけるために設けられています。
●BCP(事業継続計画)の概要
事業継続計画(BCP)とは、自然災害や感染症拡大などの緊急時に企業が事業の中断を最小限に抑え、迅速な事業再開を目的とした計画です。
以下のような項目を整備することがBCPの基本です。
・重要業務の特定
・リスクシナリオの設定
・被害想定と影響分析(BIA)
・代替手段・復旧方法の策定
・優先順位の設定(復旧目標時間RTOなど)
・緊急時の体制と役割分担
・連絡体制の整備
BCPを策定すれば、非常時においても生産・物流停止や納期遅れなどの顧客への影響を抑え、企業存続と競争優位性を維持できます。BCPの準備がなければ、復旧の遅れによって深刻な経営危機を招く可能性があります。
●BCP資格の必要性
BCP資格は、事業継続について学んでいることの証明となり、社内外の信頼獲得に効果的です。とくに取引先企業からの評価が高まり、新規契約獲得や既存契約の継続において有利に働くケースが増えています。
実務面では、リスク分析手法や復旧計画策定のスキルが身につき、効果的なBCP構築を主導できます。また、危機管理の専門家としてキャリアアップの機会が広がり、コンサルタントや管理職への昇進も期待できるでしょう。
2.事業継続・災害対策に役立つBCP資格の種類|難易度も紹介

BCPに関連する資格は国際的な認定機関から国内の専門団体まで、さまざまな組織が提供しています。それぞれ対象者や難易度が異なるため、自身の経験レベルと目標にあわせて選択しましょう。
●企業のBCP体制を診断・提案する「BCP診断士」
BCP診断士は企業のリスク評価から計画策定まで、事業継続体制を総合的に診断・改善提案できる専門家資格です。
|
認定機関 |
日本BCP協会 |
|
資格の特徴 |
・中小企業の事業継続を阻害する要因を理解し、解決策を提案 ・中小企業経営者への啓蒙活動 ・専門分野では弁護士や税理士などの専門家と連携 ・中小企業の事業継続を支援し、日本経済の活性化に貢献 |
|
受験資格 |
・中小企業経営に貢献したい保険営業マンや士業の方 |
一般的には、BCPに関する基礎的な知識が問われ、難易度は比較的取得しやすいレベルとされています。
企業内でBCP推進責任者として活動したい方や、将来的にコンサルタント業務を目指す方に適した資格です。ただし、公的な認定制度ではないため、目的を明確にしたうえで取得しましょう。
●企業・自治体のBCP推進を支援する「BCPアドバイザー」
BCPアドバイザーは組織のBCP策定・運用を専門的に支援する、実務担当者向けの認定資格です。BCPアドバイザーの概要は以下のとおりです。
|
認定機関 |
RMCA(日本リスクマネジャー&コンサルタント協会) |
|
資格の特徴 |
・企業や自治体のBCP推進を支援する専門資格 ・比較的取得しやすい資格 ・WEB試験で認定される |
|
受験資格 |
・RMCAのBCPアドバイザー講座を受講済み ・RMCA会員または非会員(非会員も受験可能) |
|
試験形式 |
・WEB試験(RMCAサイト内で実施) ・4択問題、全20問 ・試験範囲は講座動画および社会常識 ・合格基準:100点満点の90点以上 |
講座受講後の試験合格により認定され、出題範囲が事前に明示されるため計画的な学習が可能です。認定団体によってカバーする範囲や専門性の深さは異なるため、導入前に内容をしっかりと確認しましょう。
●企業のBCP担当者向け資格「事業継続管理士(CBCP)」
事業継続管理士(CBCP)は、国際的に権威ある資格で、BCP実務者としての高度な専門性を証明できます。事業継続管理士(CBCP)の概要は以下のとおりです。
|
認定機関 |
DRII(国際災害復旧協会) |
|
資格の特徴 |
・世界的に認知された事業継続 ・災害復旧分野の専門資格 ・高度な専門性を証明する資格 ・継続教育が必要 |
|
受験資格 |
・2年以上の実務経験 ・専門業務10項目のうち5項目における実践経験の証明 ・4項目(BIA・事業継続戦略・計画の開発と導入・計画の演習)のうち2項目の経験が必要 |
|
試験形式 |
・100問の多項選択式試験 ・合格基準:75%以上の正答率 ・試験後にオンライン申請と実務経験に基づくエッセイ提出が必要 |
合格後は年次更新が必要ですが、BCP分野における最高レベルの専門資格として、キャリア形成に大きな価値をもたらすでしょう。
●BCMS規格準拠の専門資格「BCMS審査員資格」
BCMS審査員資格は、ISO22301(事業継続マネジメントシステム)に基づく第三者審査や内部監査を実施する、専門家向けの国際資格です。マネジメントシステムの適合性評価能力を証明します。
BCMS審査員資格の概要を確認しましょう。
|
認定機関 |
IRCA(国際公認監査員登録簿) |
|
資格の特徴 |
・ISO22301(事業継続マネジメントシステム)に基づき、第三者審査や内部監査を実施する専門家向けの国際資格 ・准審査員(Associate Auditor)から主任審査員(Lead Auditor)までの段階がある |
|
受験資格 |
・CQI and IRCA認定コースの受講・合格が必要 ・CBCI資格保有者は事前知識証明として認められる |
|
試験形式 |
・CQI and IRCA認定コース修了後の試験 ・試験の形式は認定機関や講座内容によって異なる ・一般的には選択問題や記述問題を含む |
認証審査や内部監査で専門性を発揮でき、ISO22301導入企業での需要も高まっています。
●防災とBCPに特化した資格「防災士」
防災士は地域や企業での防災活動リーダーとして活躍できる知識・技能を証明します。防災士の概要は以下のとおりです。
|
認定機関 |
日本防災士機構 |
|
資格の特徴 |
・防災に関する知識や技能を持つことを証明する民間資格 ・災害時の対応や防災、減災活動をリードする役割が期待される ・救急救命講習を受講し、災害現場での応急活動も可能 |
|
受験資格 |
・年齢・性別・国籍に制限はなく、誰でも挑戦可能 ・防災士養成研修講座の履修修了 ・救急救命講習の修了が必要 |
|
試験形式 |
・試験時間:50分間 ・問題数:30問(三者択一形式) ・出題範囲:防災士教本の内容 ・合格基準:80%以上の正答(24問以上正解) |
多くの自治体が取得費用を助成しており、経済的負担を軽減できる点も魅力です。
平常時の防災啓発活動から災害時の避難誘導まで幅広い役割を担い、企業のBCP推進における現場レベルでの実践力向上に直結します。
●情報管理とBCPを融合した資格「情報セキュリティ管理士(ISMS)」
情報セキュリティ管理士は、サイバー攻撃や情報漏洩リスクへの対策知識を体系的に習得できる資格です。ITリスク管理と事業継続の両面をカバーし、デジタル化が進む企業での実践力を証明できます。
情報セキュリティ管理士の概要を確認しましょう。
|
認定機関 |
一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|
資格の特徴 |
・情報セキュリティの基礎から応用までを認定する民間資格 ・セキュリティ対策の管理職・リーダーとして必要な知識を証明 ・BCP(事業継続計画)やリスクマネジメントの知識も含む |
|
受験資格 |
年齢・国籍に関係なく受験可能 |
|
試験形式 |
・試験時間:120分 ・問題数:100問(マークシート方式) ・試験内容:基礎知識・実務知識・応用知識・倫理観・社会的責任 ・合格基準:各科目70%以上の得点 |
DX推進やテレワーク導入企業において、情報セキュリティとBCPを統合した危機管理体制構築に貢献できる重要な資格です。
●国際的に認められた事業継続の登竜門「ABCP(アソシエイト事業継続)」
ABCP(アソシエイト事業継続)DRII(国際災害復旧協会)が認定する入門レベルの国際資格で、事業継続分野でのキャリアをスタートする方に最適です。資格の概要は以下のとおりです。
|
認定機関 |
DRII(国際災害復旧協会) |
|
資格の特徴 |
・事業継続(BCP/BCM)分野のエントリーレベル国際資格 ・実務経験2年未満の初心者や他分野からの転身者向け ・BCM(事業継続マネジメント)の基礎知識と国際標準の理解を証明 |
|
受験資格 |
・事業継続分野での実務経験2年未満 ・関連分野の知識や興味があれば可 |
|
試験形式 |
・100問の多項選択式試験 ・合格基準:75%以上 ・試験範囲:事業継続の基本概念、リスク評価、復旧戦略など |
上位資格であるCFCPやCBCPへの申請が可能で、試験を受け直す必要がないのもメリットです。国際的に通用するBCPの基礎を学べる点で、初心者にとって最適な導入資格といえます。
関連人気記事:BCP対策とは|策定方法や策定時のポイント・補助金制度について解説
3.国内企業向けBCP体制を強化する「BCAO認定」
BCAO認定は、日本の主要なBCP関連資格制度のひとつで、国内企業の事業継続体制強化を目的としています。BCAO認定の概要は以下のとおりです。
|
認定機関 |
BCAO(特定非営利活動法人 事業継続推進機構) |
|
資格の特徴 |
・事業継続計画(BCP)の策定・運用に必要な知識を認定 ・PDCAによる継続的改善を実施する能力を証明 ・自社で事業継続の構築・維持管理ができる ・必要に応じてコンサルタントと応対可能 |
|
受験資格 |
・主任管理士受験は「事業継続准主任管理士」または「事業継続管理者」資格保持者 ・個人正会員/法人正会員/法人賛助会員/学生会員であること ・主任管理士受験に5日間の講習受講が必須 ・初級の「事業継続管理者」資格は誰でも受験可能 |
|
試験形式 |
・試験時間:選択式・記述式・論述式の3パート ・合格基準:80~90%の正答率 ・講習後に試験実施(講習内容に基づく問題) |
事業継続管理者(初級)から主任管理士(上級)まで段階的にスキルを高められ、それぞれのレベルで必要な知識や役割が明確に定められています。初級は実務経験なしで受験可能ですが、上級は講習や実務経験が必要で、専門知識が求められます。
4.国際基準に準拠したBCP専門資格「CBCI認定」
CBCI認定は世界120カ国以上の9,000名を超える会員を擁する、権威ある国際的なBCP資格制度です。CBCI認定の概要は以下のとおりです。
|
認定機関 |
BCI (事業継続協会) |
|
資格の特徴 |
・国際的に認知されたエントリーレベルの資格 ・BCM(事業継続マネジメント)の基礎知識を網羅的に学習 ・Good Practice Guidelines (GPG) 7.0 に準拠 ・世界120カ国以上で認知される資格 |
|
受験資格 |
・特別な実務経験は不要 ・誰でも受験可能 ・試験前にトレーニングコースの受講が推奨 |
|
試験形式 |
・試験時間:90分 ・問題数:90問の選択式 ・合格基準:63問以上正解で合格、77問以上正解で「Merit」取得 ・試験はオンラインで実施され、英語で行われる(非英語話者には25%の時間延長あり) |
実務経験は不要のため初心者でも挑戦可能で、経験豊富な講師による指導により体系的な学習ができます。グローバル企業では、BCMの共通理解や専門性の証明に役立ち、国際プロジェクトでも活用されています。
5.BCP資格を短期間で効率よく合格するおすすめの学習法
RMCA BCPアドバイザーのような国内資格は数時間〜数日で合格可能です。ただし、CBCIやDRIIなどの国際資格は3〜6か月程度の計画を立てるのが一般的です。平日は1日1〜2時間、休日は3〜4時間の学習時間を確保し、継続的な学習を習慣づけます。
教材選択では、CBCIやDRIIなど目標とする資格の公式教材を選びましょう。あわせて、認定研修コースを受講すれば実践的に学べます。
とくにCBCIでは4日間の集中研修で試験範囲を網羅的に学習でき、合格率が大きく向上します。過去問題集の入手が難しい場合は、模擬試験や演習問題で実戦的な解答力を養いましょう。
6.BCP資格取得後の実践!災害時に必要な防災資機材とその選び方

BCP資格で習得した知識を実際の災害対策に活かすため、防災資機材の選定と管理は大切です。効果的な備蓄計画から非常用電源の導入まで、実践的なノウハウをお伝えします。
●災害時の備えに欠かせない!防災資機材の基本セット
災害時の生命維持と事業継続には、計画的な防災資機材の備蓄が不可欠です。以下の物資を基本セットとして備えておきましょう。
・3日分の飲料水(1人1日3リットル)
・非常食(アルファ米・缶詰・栄養補助食品)
・懐中電灯
・ラジオ
・救急用品
・携帯トイレ
企業では従業員数×3日分を基準とし、家庭では家族構成を考慮した備蓄計画を策定してください。地震や津波による被害で備蓄が使用できなくなるリスクも想定し、複数拠点への分散配置が効果的です。
BCP資格で習得したリスク分析手法を活かして、自社の業種や立地にあわせた優先順位をつけましょう。
●非常用電源で停電対策!「Jackery ポータブル電源」がおすすめ
停電は事業継続において致命的なリスクで、通信機器の停止により業務中断と顧客対応力の低下を招きます。停電などの電力断絶を想定したBCP対策には、Jackery(ジャクリ)のポータブル電源が効果的です。
ポータブル電源とは、持ち運び可能な大容量バッテリーにコンセントやUSB端子を搭載した蓄電装置です。オフィスでのポータブル電源の活用例を確認しましょう。
・パソコンやスマートフォンの緊急電源
・Wi-Fiルーターへの電力供給で通信環境の維持
・LED照明による最低限の照度確保
Jackery(ジャクリ)ポータブル電源ならソーラーパネルとの組み合わせにより、長期間のライフライン断絶にも対応可能です。静音設計のため避難所や仮設オフィスでの使用にも適しており、BCP発動時の代替拠点運営を支援できます。
Jackery(ジャクリ)ポータブル電源は、非常時の電力確保を支える心強い備えとして、実効性の高いBCP対策に大きく貢献します。
もっと多くの商品を見る
●備えの見直しで安心!防災資機材の管理とメンテナンス法
防災資機材の実効性確保には、継続的な管理とメンテナンスが欠かせません。以下のような定期確認を実施し、維持管理を徹底しましょう。
・食料品の賞味期限
・電池の消耗
・医薬品の有効期限
各資機材の特性に応じた点検スケジュールを策定し、月次または四半期ごとの定期確認を実施してください。
企業では防災担当者を明確にし、年2回程度の防災訓練の実施が重要です。実際の使用を想定した訓練により、資機材の不足や操作上の課題を事前に発見できます。
BCPで学んだPDCAの考え方を資機材管理に応用することで、継続的な改善と対応力の向上が図れます。
関連人気記事:BCP訓練完全ガイド!進め方の基本と5つの成功事例を紹介
7.BCP資格についてのよくある質問
BCP資格取得を検討する際によく寄せられる質問について、実務に役立つ観点から詳しく解説します。
●BCPが完全義務化になるのはいつですか?
BCP策定の完全義務化は業界によって時期が異なりますが、介護業界では2024年4月からすべての介護事業所でBCP策定が完全義務化されました。未策定の場合は介護報酬の減算が適用されています。具体的には施設・居住系サービスで3%、その他サービスで1%の減算です。
一般企業については法的な義務化は現時点で実施されていません。ただし、中小企業庁が推進する「事業継続力強化計画」の認定制度により、実質的な策定促進が図られています。
今後も業界ごとに段階的な義務化が進むと予想されるため、早期の対応準備が必要です。
関連人気記事:介護施設のBCP策定が2024年4月から義務化!やるべき対策まとめ
●BCP認定を受けるメリットは?
BCP認定の取得により、事業継続に関する専門知識と実践能力を客観的に証明でき、社内外からの信頼度が大幅に向上します。とくにビジネスパートナーからの信頼を得やすくなり、新規取引や継続契約で差別化が可能です。
実務面では、リスク分析から復旧計画策定まで体系的なスキルが身につき、自社のBCP構築を効率的に主導できます。キャリア面では危機管理の専門家として市場価値が向上し、管理職昇進やコンサルタント転身の機会も広がるでしょう。
介護業界ではBCP資格を持つことで、重要な役割を担える人材として評価され、就職・転職時の強みになります。
まとめ
BCP資格は、事業継続計画に関する専門知識とスキルを証明する重要な資格制度です。CBCIやDRII、BCAO認定などさまざまな選択肢があり、自身の経験レベルと目標に応じた選択が可能です。
効率的な合格には公式テキストの活用と認定研修コースの受講が重要で、資格によって数日から数か月の学習期間が必要となります。
Jackery(ジャクリ)ポータブル電源の導入や備蓄の再確認を通じて、実践的なBCP体制を築いていきましょう。