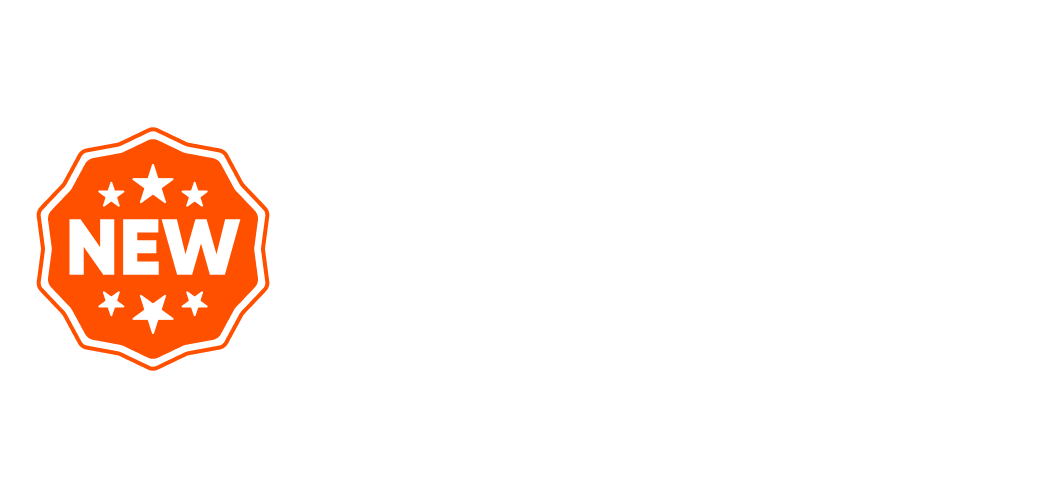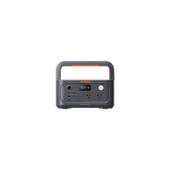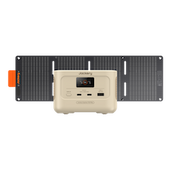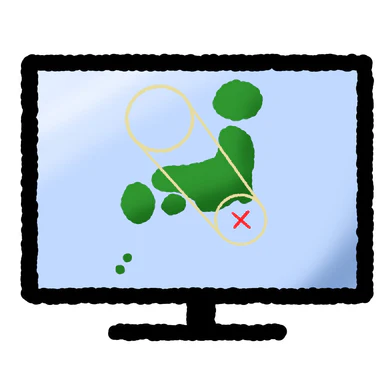1.台風で今出ている警報情報をチェックする方法
台風の影響を最小限に抑えるには、まず最新の警報情報を早く確認しましょう。気象庁の公式情報から民間の防災アプリまで、複数の情報源から最新の状況を確認できます。
●気象庁・防災アプリ
信頼性の高い情報源は気象庁が提供する「キキクル(危険度分布)」と警報・注意報のページです。キキクルでは、土砂災害や洪水の危険度を5段階の色分けで表示します。
危険度の色分けの内容は以下のとおりです。
|
危険度 |
表示色 |
対応の目安 |
|
レベル5 |
黒 |
災害切迫(命を守る行動を/警戒レベル5) |
|
レベル4 |
紫 |
危険(避難指示/警戒レベル4) |
|
レベル3 |
赤 |
警戒(高齢者等避難/警戒レベル3) |
|
レベル2 |
黄 |
注意(注意報級/警戒レベル2) |
|
レベル1 |
白 |
今後の情報等に留意(警戒レベル1) |
また、Yahoo!防災速報やNHKニュース防災アプリは、あらかじめダウンロードしておきましょう。プッシュ通知を設定しておけば、警報が出たときにすぐ情報を受け取れます。
防災アプリは気象庁の発表とほぼ同時に避難指示や注意報を通知してくれるため、外出中でもタイムリーに情報を受け取れます。
●Yahoo天気の活用
Yahoo!天気アプリは台風の動向をチェックするのに便利です。機能は以下のとおりです。
|
機能名 |
特徴 |
活用ポイント |
|
雨雲レーダー |
15時間先までの降雨予測を表示 |
台風接近時の雨のタイミングや強さを事前に把握できる |
|
台風進路図 |
5日先までの進路予想と暴風域を視覚的に確認可能 |
自宅や実家など、地域への影響時間を予測しやすい |
|
通知設定 |
居住地に加えて職場や学校周辺も登録可能 |
各場所の警報・注意報を個別に受け取れる |
|
大雨危険度通知 |
土砂災害や浸水の危険度が高まったときに通知を受け取れる |
危険が迫ったタイミングで避難判断ができ、避難の遅れを防げる |
Yahoo!天気アプリは、避難のタイミングを判断するのに役立ちます。日常的に活用しておけば、災害時に迷わず行動に移せるでしょう。
●地域別に警報を調べる方法
警報を地域別で確認するには「東京 警報」など、地域名(都道府県名・市町村名)と警報をセットで検索すると簡単に調べられます。
気象庁の都道府県別情報ページでは、市町村単位の警報・注意報とあわせて、周辺地域の状況も確認可能です。
自治体のホームページや防災サイトでは、地域特有の災害リスクが紹介されています。避難所の開設情報もあるので、事前に確認しておきましょう。
関連人気記事:注意報と警報の違いとは?基準や警戒レベル・発表されるタイミングを解説
2.台風で発生する警報とは?正しく知って行動しよう

台風が近づくと、さまざまな種類の警報が発表されます。各警報の基準と警戒レベルとの関係を理解して、適切なタイミングで避難行動をとりましょう。
●台風警報の種類と発令基準
台風によって発令される主な警報は、以下のとおりです。
|
警報名 |
発表される条件 |
内容 |
|
暴風警報 |
平均風速20メートル以上の暴風が予想される場合 ※基準風速は地域によって異なる |
外出が危険な状況 建物内での待機を推奨 |
|
高潮警報 |
台風により潮位が異常に上昇し、重大な災害の恐れがある場合 |
海岸付近や低地での浸水・冠水に注意が必要 |
|
大雨警報 |
災害が発生するほどの大雨が予想される場合 |
土砂災害・浸水の危険性が高まり避難判断が必要 |
|
洪水警報 |
河川の増水により氾濫の恐れがある場合 |
河川周辺の住民は早めの避難行動が必要 |
さらに深刻な状況では特別警報が発表されます。数十年に一度の現象が予想される際の最高レベルの警報で、台風では以下の特別警報が考えられます。
・暴風特別警報
・高潮特別警報
・大雨特別警報
特別警報が発表された地域は、災害が発生している可能性が高く危険な状態です。直ちに命を守る行動をとってください。
●警戒レベルとの関係性を把握
気象庁の警戒レベルは1から5の5段階で構成され、数字が大きいほど危険度が高くなります。警戒レベルの内容を確認しましょう。
|
警戒レベル |
対応する警報・情報 |
住民がとるべき行動 |
|
レベル5 |
特別警報・災害発生情報など |
命を守る最終行動をとる |
|
レベル4 |
土砂災害警戒情報・高潮警報など |
危険な場所から全員避難 |
|
レベル3 |
大雨警報・洪水警報など |
高齢者や避難に時間のかかる人は避難を開始 |
|
レベル2 |
大雨注意報、洪水注意報など |
避難行動の確認、ハザードマップで状況を再確認 |
|
レベル1 |
気象情報・台風情報など |
防災への心構えを持ち、最新情報に注意 |
大雨・洪水警報は警戒レベル3、土砂災害警戒情報や高潮警報はレベル4、特別警報は災害発生の恐れが極めて高いレベル5に相当します。
避難指示が出る前でも、警戒レベルに該当する情報が出たら、速やかに自ら避難の行動をとりましょう。
3.台風で警報が出たとき避難すべきタイミングと判断の目安

台風で警報が発表されたときは、適切なタイミングでの避難が命を守る重要な行動です。警戒レベルや地域の災害リスクを正しく理解して、安全に避難しましょう。
●避難の基本は「早め・明るいうちに」
夜間の避難は危険を伴うため、明るい時間帯の避難が基本です。夜間は視界が悪く、以下の危険箇所を見落とし転倒や転落の危険があります。
・側溝
・マンホール
・倒木
また、救助活動も困難になるため、万が一の際の対応が遅れてしまいます。気象庁の警戒レベル3が発表された時点で、高齢者や小さな子どもがいる家庭は避難を開始してください。
気象情報をチェックし、自治体の指示が出る前に動く意識が大切です。
●避難すべき具体的な状況とは
河川の氾濫危険水位に達した際や、土砂災害警戒情報が発表された地域では即座に避難が必要です。避難すべき具体的な状況は以下のとおりです。
|
状況の種類 |
具体例 |
避難判断のポイント |
|
河川の増水 |
水位が堤防の高さに近づいている |
氾濫の危険があるため、速やかな避難が必要 |
|
山間部の大雨 |
1時間に50mm以上の雨が継続している |
土砂災害のリスクが高く、警戒レベル4相当の行動が求められる |
|
海沿いの地域 |
高潮警報が発表されている |
・満潮と台風接近が重なる場合はとくに危険 ・早めの避難が重要 |
住宅の立地や構造によっても判断基準は変わります。木造住宅や平屋建ての場合は浸水リスクが高いため早期避難が必要です。
3階建て以上の頑丈な建物では垂直避難も1つの手段ですが、周囲の危険性もあわせて判断してください。
●避難先はどこ?避難所の種類と開設状況の確認方法
避難先には市町村指定の公的避難所、自主避難所などの選択肢があります。公的避難所は体育館や公民館などで、災害の規模に応じて段階的に開設されます。自主避難所は、避難指示前に自ら避難を希望する人のために市が開設する避難所です。
開設状況の確認は、以下のとおりです。
・自治体の公式ウェブサイト
・防災アプリ
・防災行政無線
Yahoo!防災速報アプリでは開設情報をリアルタイムで受け取れます。ペットを連れて避難する場合は、同行避難ができるかを事前に調べておきましょう。車椅子の方がいる家庭は、バリアフリーの避難所を確認しておくと安心です。
避難所によっては収容人数に限りがあるため、複数の避難先を考え、移動手段や経路の安全性も考慮して判断してください。
●住んでいる地域の災害リスクを把握
住んでいる地域の災害リスクを把握するために、ハザードマップで以下の内容を確認してください。
|
確認すべきリスク |
チェック内容 |
避難判断の目安 |
|
洪水リスク |
・自宅が洪水浸水想定区域にあるか ・予想される浸水深 ・浸水継続時間 |
0.5m以上の浸水が予想される場合は避難が必要 |
|
土砂災害リスク |
・土砂災害警戒区域に該当するか ・急傾斜地崩壊危険箇所との距離 ・土石流危険渓流との距離 ・イエローゾーン(警戒区域)とレッドゾーン(特別警戒区域)の確認 |
レッドゾーンでは住宅の構造にかかわらず原則避難が必要 |
|
高潮リスク |
・高潮浸水想定区域に該当するか ・満潮時刻と台風の接近時刻の関係 |
海抜の低い地域は早期避難が重要 |
詳細な情報は国土交通省の「重ねるハザードマップ」や自治体サイトで確認でき、印刷しておけば停電時にも活用できます。
4.台風で避難が遅れるとどうなる?実際の被害事例に学ぶ教訓

過去の台風災害を振り返ると、避難の遅れが深刻な被害拡大につながった事例が多くあります。災害事例から避難タイミングの大切さを学びましょう。
●元年台風19号(東日本台風)
2019年10月の台風19号は「東日本台風」と呼ばれ、関東甲信地方から東北地方にかけて記録的な大雨となりました。被害の概要は以下のとおりです。
|
項目 |
内容 |
|
総降水量 |
神奈川県箱根で1,000ミリを記録 |
|
大雨の範囲 |
17地点で500ミリを超える豪雨を観測 |
|
特別警報 |
13都県に大雨特別警報が発表され、最大級の警戒が呼びかけられた |
|
被害の種類 |
河川の氾濫・土砂災害・浸水害が広範囲で同時多発的に発生 |
|
避難の状況 |
一部地域では避難が間に合わず、多数の住民が取り残される事態 |
東日本台風では、とくに千曲川や阿武隈川など大河川の氾濫では、住民の避難が間に合わず、多数の方が取り残される事態となっています。
災害時には避難所だけに頼らず、垂直避難や親戚宅への移動など、柔軟で早めの避難行動が重要だと再認識されました。
参考:気象庁|令和元年東日本台風(台風第19号)による大雨、暴風等
●平成25年台風26号(伊豆大島豪雨)
2013年10月の台風26号による伊豆大島災害の概要は以下のとおりです。
|
項目 |
内容 |
|
総降水量 |
最大1時間降水量118.5ミリ 4時間連続で1時間80ミリ以上の猛烈な雨が継続 |
|
大雨の範囲 |
伊豆大島で局地的に記録的豪雨 |
|
特別警報 |
土砂災害警戒情報は発表されたが、大雨特別警報は出されなかった |
|
被害の種類 |
土石流により住宅が倒壊し36人が死亡、3人が行方不明者という深刻な被害 |
|
避難の状況 |
避難指示・勧告は出されず |
被害のあった神達地区と元町地区では避難行動がとられておらず、土石流で住宅が倒壊した15世帯すべてで犠牲者が発生しました。
36人が死亡し、3人が行方不明者という深刻な被害となっています。被害を防ぐには、危険を感じた時点での避難が重要といえるでしょう。
参考:内閣府防災情報|2013年(平成25年) 台風26号による災害
5.台風で警報が発生し避難が難しいときの対処法
台風の接近により外出が危険になった場合は、無理に避難所へ向かわず屋内での安全確保を最優先に考えましょう。屋内避難ですることは以下のとおりです。
・建物の2階以上へ移動する(垂直避難)
・山や崖から最も離れた部屋を選ぶ
・浸水の恐れがある1階から必要なものを上階へ運ぶ
・懐中電灯・携帯ラジオなどを手の届く場所に準備する
・断水に備え、浴槽やペットボトルに飲料水を確保する
・ガスの元栓を閉めて火災のリスクを軽減する
夜間や暴風雨の中では外の状況が確認できないため、無理な避難は危険です。自宅内の安全な場所で待機する方が安全な判断といえます。
関連人気記事:台風時に車で避難する際の3つの注意点!車を守るための対策も解説
6.台風で警報が出たとき避難時に必要な持ち物
台風避難では、両手がふさがらないようリュックに必要品を最小限詰めるのがポイントです。防災セットに加え、家族に必要なものを追加しておきましょう。
●基本の防災グッズ
避難時の基本セットは以下のとおりです。
・飲料水は1人1日3リットル(最低3日分)
・非常食(加熱不要のレトルト食品・缶詰・栄養補助食品)
・懐中電灯(予備の乾電池も必須)
・常備薬・お薬手帳
・医療用品
・現金(小銭含む)
・身分証明書・健康保険証
・携帯電話の充電器
・着替え
荷物が重くなりすぎないように注意し、家族で分担してリュックに入れることで、安全に避難しやすくなります。
●プラスして持っておきたい備え
基本の防災グッズに加えて、以下のものがあると避難生活で役に立ちます。
・モバイルバッテリー
・ソーラー充電器
・除菌ウェットティッシュ
・ドライシャンプー
・アルコール消毒液
・体温計
・生理用品
・紙おむつ
・粉ミルク
高齢者がいる場合は入れ歯洗浄剤や老眼鏡、補聴器用電池も準備しましょう。ゴミ袋は避難所での感染対策にも使用でき、アルミ製保温シートは防寒対策として有効です。
家族の写真は避難所で離ればなれになった際の確認用として携帯してください。笛やブザーは緊急時の救助要請に活用できます。
7.台風に備えた「ポータブル電源」はJackery(ジャクリ)がおすすめ!
台風による停電対策として、Jackery(ジャクリ)製ポータブル電源がおすすめです。ポータブル電源は、コンセントを備えた持ち運び可能な大容量バッテリーで、モバイルバッテリーよりも多機能で高出力です。
軽量・コンパクト設計により、女性や子どもでも扱いやすく設計されています。停電時にはスマホの充電から照明器具の使用など幅広く対応し、台風後の復旧期間も安心です。
全世界で500万台以上の販売実績を持ち、最大5年の無料保証が付いているため、安全性と信頼性の両面で優れています。台風シーズンを迎える前に、Jackery(ジャクリ)のポータブル電源を備えて停電に備えましょう。
もっと多くの商品を見る
8.台風で警報が出たときに家族で共有したい避難マニュアル
台風時の混乱を防ぐためにも、避難マニュアルは家族みんなで作成し、事前に共有します。マニュアルでは以下の項目を決めておくと、スムーズな避難につながるでしょう。
・避難先の候補を複数決めておく(親戚宅・避難所・ホテルなど)
・自宅・職場・学校それぞれからの避難経路を家族で共有する
・集合場所は小学校や公民館など、誰もがわかる場所を設定する
・連絡が取れないときの行動パターンをあらかじめ決めておく
・高齢者がいる場合は、車椅子で通れる避難ルートや常用薬の準備を確認する
・ペット同行避難可能な避難所を確認し、ペットキャリーやフードを準備する
さらに、定期的に避難経路を歩く訓練をしておくと、危険箇所や所要時間がわかり災害時も落ち着いて避難できます。
非常時に迷わず行動するために、家族全員で避難マニュアルを見直すことが重要です。
まとめ
台風で警報が出たときは、命を守るために早めの判断が何より大切です。警戒レベル3で高齢者等の避難開始、レベル4では全員が明るいうちに避難するのが基本となります。
避難時には最低3日分の飲料水・食料に加え、懐中電灯や常備薬などの防災グッズをリュックに準備しましょう。
スマホの充電や照明の確保にも使えるJackery(ジャクリ)のポータブル電源は、停電時の強い味方です。災害時に困らないよう、事前にできる対策を進めておきましょう。