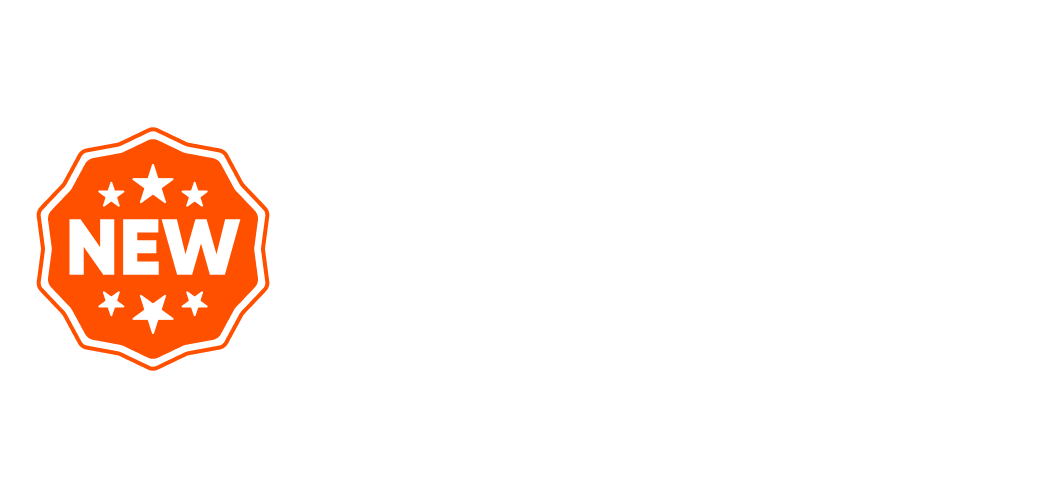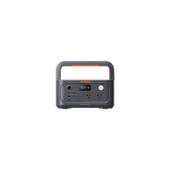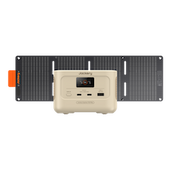1.そもそも台風の名前はどうやってつけられるの?命名のルールを解説
台風に名前がつけられる背景には、防災や国際協力のための明確なルールがあります。以下では、台風の名前が決まる仕組みや命名のルールを見ていきましょう。
●台風の名前は「台風委員会」が決めている
台風の名前の命名は「台風委員会」という国際組織が決めています。台風委員会には日本を含む14の国と地域が加盟し、北西太平洋および南シナ海で発生する台風に対して共通の名前リストを用いています。
ちなみに2000年以前は、アメリカ式の英語名(女性名など)が使われていました。しかし、文化的多様性を尊重する観点からアジア名に変更されています。
●台風名は提出国の固定順でローテーション使用されている
台風名は、各国・地域が10個ずつ提出した名前が固定順でローテーション使用されています。全部で140個の名前がリストとして管理されていて、台風が発生するたびにリストの順番に従って命名されます。140個を使い切ると、再び最初からスタートです。
●被害が大きかった台風名は引退して新しい名前に置き換えられる
甚大な被害をもたらした台風名はリストから除外し、再使用を避ける「引退」制度を台風委員会では設けています。引退制度は、被災者への配慮と情報の混乱を防ぐための措置です。
たとえば2013年にフィリピンを襲った台風「ハイエン」は約7,300人の死者・行方不明者を出し、その後リストから削除されています。代わりに登録されたのは、中国が提案した「バイルー」です。
●名前を付ける目的は「防災意識と情報共有の精度を高める」こと
台風に名前をつける最大の理由は、情報を正確にかつ迅速に伝えるためです。番号だけでは覚えにくい台風でも、名前があれば関係各所での情報共有がスムーズになります。災害時の備えや判断を的確にするためにも、台風に名前があることは重要です。
さらに複数の台風が同時に発生する場合には、名前があることで混同を防げます。
2.現在使われている日本の台風の名前一覧と意味・由来

現在使われている日本の台風の名前は、10個あります。それぞれ名前に意味と由来があるため、以下で詳しく解説します。
●日本が提案した台風の名前一覧
日本は「星座」をテーマに、以下の10個の名前を提案しています。
・コグマ(こぐま座)
・ウサギ(うさぎ座)
・ヤギ(やぎ座)
・トカゲ(とかげ座)
・カジキ(かじき座)
・クジラ(くじら座)
・コイヌ(こいぬ座)
・コト(こと座)
・トケイ(とけい座)
・ヤマネコ(やまねこ座)
各国の言語差を超えて情報伝達の正確性を保つため、すべて漢字ではなくカタカナで表記されるのが国際ルールです。
他国が地名や神話にちなんだ現実的な名前を多く提案している中、日本の命名はやや抽象的で独特な印象を与えます。そのため日本が提案した台風の名前は、「ダサい」「かわいすぎる」などと話題になることもあります。
●各国の台風の名前はどんな感じ?日本と比較
他のアジア諸国が提案する台風名には、その国の自然・文化・暮らしが色濃く反映されています。たとえば、各国の主な台風名称と、その名称の傾向は以下のとおりです。
|
国名 |
特徴・代表的な台風名 |
|
韓国 |
身近な動植物 例:ノグリー(たぬき)、ナーリー(百合) |
|
フィリピン |
動作に関わる用語 例:ハグピート(むち打つこと)、ラガサ(動きを速めること) |
|
ベトナム |
伝説や地名 例:ソンティン(ベトナム神話の山の神)、ハーロン(湾の名前) |
|
香港 |
固有名詞や象徴 例:サンサン(少女の名前)、ドルフィン(白イルカ) |
日本の星座に由来した名称に比べると、他国は日常に根差した表現を採用しています。このような違いから、台風名にも各国の文化的背景が鮮明に表れていることがわかるでしょう。
3.日本が提案した台風の名前はなぜダサいと話題になるのか?
日本が提案した台風の名前は、なぜダサいと話題になるのでしょうか。3つの理由を解説します。
●かわいすぎる名前が台風のイメージと合っていないから
日本が提案している名前には「コイヌ」や「ウサギ」など、かわいらしい印象の動物名が並びます。台風は暴風や豪雨などの深刻な被害をもたらす自然災害のため、かわいすぎる名前と台風のイメージがマッチしていません。
台風の危険さや緊張感が伝わりにくいと感じる方も多いことから、名前がダサいと話題になってしまいます。
●名前の響きがやさしすぎて、台風の怖さが伝わりにくいから
名前の響きは、印象に大きく影響します。たとえば「ヤマネコ」や「トケイ」などは音としても響きがやさしいため、台風の怖さが伝わりにくい印象があります。
SNSやニュースで「ヤマネコ」という台風の名前を見ても、台風の大きさや強さはイメージしにくいでしょう。「もっと台風の怖さが分かりやすい名前にしたほうがいいのではないか」といった疑問が話題になりやすい傾向にあります。
●星座テーマの影響で動物系に偏り台風にふさわしくない印象になっているから
日本が提案している台風名は、すべて星座に由来があります。実在の星座をもとにした名前が採用されているのですが、このテーマ設定があることで、どうしても「よく聞く動物の名前」に偏ってしまいます。
台風名にふさわしい迫力や説得力を感じにくいのは、星座テーマの影響で名前が動物系に偏り台風にふさわしくない印象になっていることも一因です。
4.話題になった台風名とユニークな名前の由来

一部の台風名は、意外性や親しみやすさからネット上で話題になることがあります。以下では、とくに注目を集めた「かわいい・面白いと話題になった名前」と「被害とのギャップで記憶に残った名前」の2つに分けて紹介します。
●かわいい・面白いと話題になった名前
日本が提案した台風の名前(コグマ・ヤギなど)は、「動物っぽくてかわいい」や「台風らしくない」などとたびたび話題に上がります。いずれも星座名を由来としており統一感はあるものの、災害を連想させない印象が逆にユニークです。
海外の台風では、以下のような台風の名前が話題となりました。
・バビンカ(プリン)
・サンサン・レンレン(いずれも女性名)
名前自体にインパクトがあり、「台風情報なのになぜプリンの名前?」という反応も見られます。
●被害とのギャップで記憶に残った名前
かわいらしい名前でも実際の台風が大きな被害をもたらすと、名前とのギャップが話題となって記憶に強く残ることがあります。具体的には、次のような名前の台風です。
|
台風名 |
被害 |
|
2013年「ウサギ」 |
フィリピンや中国南部で暴風雨をもたらし、死者や数万人の避難者を出す |
|
2018年「ジョンダリ(ひばり)」 |
日本列島を横断し各地で河川の氾濫や浸水を引き起こす |
|
2019年「カジキ」 |
九州南部に停滞して記録的な大雨をもたらし、災害級の被害となる |
|
2020年「バービー(山の名前)」 |
韓国や中国で強風・浸水被害をもたらす |
|
2023年「コイヌ」 |
台湾で記録的暴風雨を観測し、交通・電力インフラに大きな影響をもたらす |
名前の由来や響き、実際の被害状況とのギャップから「記憶に残る台風名」が生まれています。
5.災害時の安心と日常の利便性を両立できる「Jackery(ジャクリ)ポータブル電源」
台風や地震などの災害時、停電による不安を軽減する手段として注目されているのが「ポータブル電源」です。
ポータブル電源とは、軽量で持ち運び可能な大容量バッテリー。ポータブル電源があれば、電気の通らない非常時でも次のようなことができます。
・スマホの充電
・冷蔵庫の稼働
・暖房器具の使用
中でも「Jackery(ジャクリ)」は、全世界500万台以上の販売実績と13年の信頼を誇るブランドです。工事不要で、家庭用コンセントのようにどこでも電源を確保できます。ソーラーパネル併用で節電にもなり、普段使いと防災対策が両立可能です。
そして日本語サポートや最大5年の保証付きで、初めての人でも安心して利用可能。コンパクト設計で女性や高齢者にも扱いやすく、もしもの備えとして各家庭に一台あると重宝します。災害への備えとして、今すぐJackery(ジャクリ)ポータブル電源を導入してみてください。
もっと多くの商品を見る
6.台風の名前に関するよくある質問
台風の名前に関するよくある質問と、その回答をまとめました。
●2025年に使われる台風の名前は?
現在(2025年7月2日時点)までに発生した台風の名前は、以下のとおりです。
・台風1号(ウーティップ):6月11日
・台風2号(セーパット):6月23日
今後台風が発生すると、以下の順に名前が付けられる予定です。
・台風3号(ムーン)
・台風4号(ダナス)
・台風5号(ナーリー)
・台風6号(ウィパー)
・台風7号(フランシスコ)
・台風8号(コメイ)
このように台風の名前は、14の国と地域が提案した140の名前を順番にローテーションで使用していきます。年ごとに割り当てられているわけではなく、前回使われた名前の次から継続されていく形式です。
●アメリカの台風(ハリケーン)にはなぜ女性の名前が多いの?
ハリケーンに女性の名前が多いのは、もともと米軍の気象学者が恋人や妻の名前をハリケーンにつけていたことが起源とされています。1953年から1978年にかけて、アメリカではハリケーンに女性の名前だけを使っていました。
しかし女性名だけを使うのは不適切との声が上がったため、1979年からは男女交互の名前リストに変更されています。現在は世界気象機関(WMO)があらかじめ決めたリストをもとに、男女の名前が順番に割り当てられています。
●歴代でもっとも台風の発生が多かった年はいつ?
歴代で最も台風が多く発生した年は1967年(昭和42年)です。年間で39個の台風が発生し、統計開始以降で最多となっています。例年は年間平均25個前後の発生数で推移しており、39個という数は異例です。
参考:気象庁「台風の平年値」
なお、台風は毎年同じ時期・同じ数が発生するわけではありません。エルニーニョ現象(※)や海面水温など複数の気象要因により、年ごとに大きく変動します。
※エルニーニョ現象:太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけての海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象のこと。エルニーニョ現象が起きると、日本を含め世界中の異常な天候の要因となり得ると考えられている。
関連人気記事:過去最強の台風をランキングで紹介!日本や世界で一番被害が大きかった台風は?
●1年に一度も台風が発生しなかった年ってある?
記録が残る1951年以降で、台風が一度も発生しなかった年はありません。毎年少なくとも十数個の台風が発生しており、もっとも少なかった年は2010年(平成22年)の年間14個です。
地球温暖化の影響や海面水温の上昇もあり、将来的に発生数が極端に減る可能性は低いと考えられています。そのため「台風が1つも来なかった年がある」という印象は、たまたま日本に接近した台風が少なかったことからきているのでしょう。
関連人気記事:なぜ台風は日本に多く来るの?理由と備えるべき時期をわかりやすく解説
●台風の番号と名前はどちらを信用すればよい?
正確性を重視する場合は台風の番号を、会話や報道での分かりやすさを求める場合は名前を信用するにするのが適切です。
「番号」は日本の気象庁が公式に採用しており、時系列の把握や記録管理などの正確な情報が求められる場面で使われます。防災機関や報道などでは、おもにこの番号が使われます。
一方の「名前」は、世界気象機関(WMO)傘下の台風委員会によって定められたリストから選ばれるものです。複数の台風が同時発生した際の識別や、国際的な情報共有をスムーズにする役割があります。両者を使い分ける意識を持つと、混乱せずに済むでしょう。
まとめ
台風の名前には、日本を含む14の国と地域が提案した140個の名前が順番に使われています。名前はときにかわいらしく見えるものもありますが、重大な被害をもたらした台風も多いため油断は禁物です。
なお停電など災害時の備えとしては、普段使いもできるJackery(ジャクリ)のポータブル電源のようなアイテムがあると安心できます。台風の命名の由来を知ると同時に、防災対策としても役立ててください。