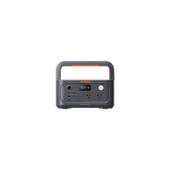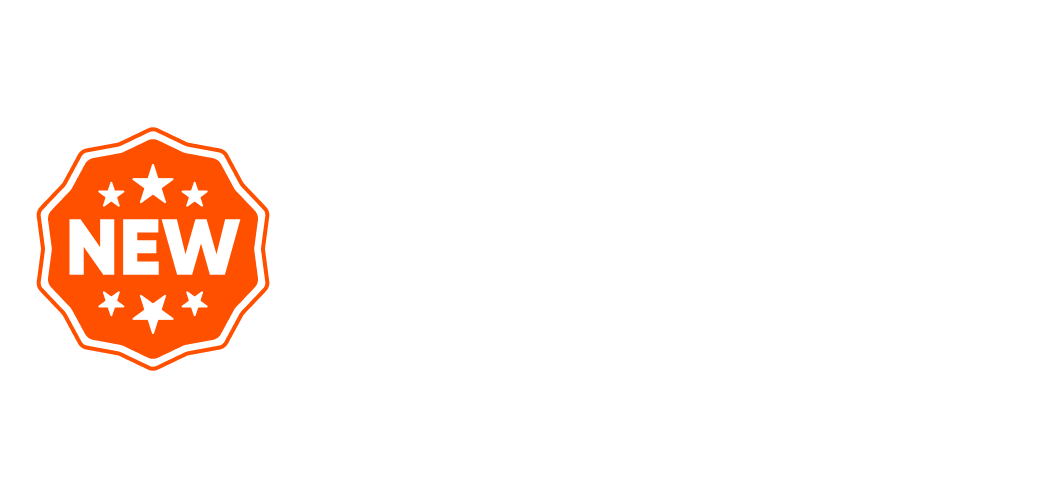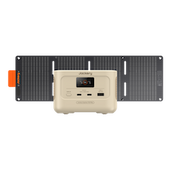1.罹災証明書と被災証明書の違い
地震や台風などの自然災害により住宅が被災した場合、保険の請求や行政からの支援を受ける際「罹災証明書」「被災証明書」が必要です。
ここでは、「罹災証明書」「被災証明書」をそれぞれ詳しく解説しているので、2つの証明書の違いを理解しておきましょう。
●罹災証明書とは災害で被災した住家などの被害の程度を証明したもの
罹災証明書は、地震・豪雨・強風などの自然災害が原因で住家(住宅・居住している建物)がどの程度被害を受けたかを証明する書類です。
主に以下のような場面で使われます。
・自宅の応急的な修繕を行う際の手続きの申請
・被災者の生活再建を支援する制度の利用
・税金や公共料金の減免申請
ただし、市区町村の職員による現地確認が必要なため、既に建物が修復されていると罹災証明書は発行できません。また、調査に時間がかかり、罹災証明書がすぐに発行されないこともあり得ます。
参考元:「内閣府防災情報のページ|第1章 制度概要 1.災害対策基本法における位置付け」より
●被災証明書とは災害で被災した非住家などの被害の事実を証明するもの
被災証明書は住居そのものではなく、住宅付帯設備・動産・住家以外の工作物などの被害の事実を証明するものです。非住家には、以下の項目が該当します。
|
非住家 |
非住家の詳細 |
|
住家の付帯物 |
門扉・フェンス・カーポート(簡易的な車庫)・雨どいなど |
|
動産など |
車・施設の機械・店舗の商品など |
|
住家以外の工作物 |
倉庫・物置・納屋など |
被災証明書は、被災者支援制度や地震・火災保険などを申請する時に必要です。なお「罹災証明書」の申請時のように、役所の職員による被害判定の調査はありません。
参考元:「マイナポータル|【災害】被災証明書の発行申請」より
2.罹災証明書・被災証明書で受けられるメリット・支援・補助金

自然災害によって住宅などが被災した場合、自治体から「罹災証明書」「被災証明書」を取得していれば、公的支援や補助金が受けられるメリットがあります。
具体的な支援内容について分かりやすく解説しているので、それぞれ見ていきましょう。
参考元:「内閣府 防災情報のページ|被災者支援に関する 各種制度の概要」より
●罹災証明書で受けられる支援・補助金
「罹災証明書」を取得していると、以下の支援制度・補助金の対象となります。
・災害弔慰金の給付
・生活再建支援金制度の利用
・災害援護資金の貸付
・地方税の減免・猶予措置
・国税に関する特例処置
それぞれ見ていきましょう。
災害でご家族を失った遺族の方に対し、一定の金額が支給される制度です。家族内で、亡くなられた方に応じて支給額は異なります。
・生計維持者の場合:最大500万円
・それ以外の家族の場合:最大250万円
なお、災害が直接の死因でなくても、災害関連死と判断されると災害弔慰金の対象になります。
住居が全壊・半壊、または災害の影響でやむを得ず解体された世帯に対し、支援金が給付される制度です。被災状況に応じて、以下の支援金が支給されます。(加算支援金を含む)
|
被害状況 |
金額 |
|
全壊(50%以上の損害)・解体・長期避難 |
150万~300万円 |
|
大規模半壊(40%台の損害) |
100万~250万円 |
|
中規模半壊(30%台の損害) |
25万~100万円 |
※(※世帯人数が1人の場合、金額の3/4の額)
参考元:「内閣府|被災者生活再建支援制度の概要 4.支援金の支給額」より
ただし、災害当時に実際に住んでいた必要があり、別荘や空き家、賃貸物件は原則対象外です。
災害によって生活の立て直しが難しくなった方に対して、生活資金の貸付を受けられる制度です。災害援護資金の貸付条件は下記の通りです。
|
項目 |
内容 |
|
年利 |
3% |
|
据置期間(利息のみ返済する期間) |
最長3年間 |
|
返済期間 |
最大10年間 |
また、以下の条件を満たす世帯が対象です。
・家具や家電などの家財の3分の1以上が損壊
・自宅が半壊以上または流出
なお、災害により世帯主が負傷し、1か月以上の療養が必要な場合も災害援護資金を受けられます。
罹災証明書を取得していると、以下の地方税関連の特別措置の対象となります。
・住民税・自動車税・固定資産税の減免
・地方税の一時的な納税猶予
・納税期限の延長(自治体の判断により実施)
地方税の特別措置は、災害で受けた住宅や家財(家具・家電製品など)の合計価格が、10分の3以上が対象です。前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合、軽減・免除の割合は「8分の1~全額」の特別措置が適用されます。
参考元:「総務省|大規模災害時の災害減免基準について 3ページ」より
納付期限の延長が都道府県の条例で一律に定められている場合、特別な手続きは不要です。
税務署へ罹災証明書を提出することで、国税関連の支援を受けられます。
|
支援項目 |
内容 |
|
申告・納税期限の延長 |
最大2か月まで猶予される場合あり |
|
納税の猶予申請 |
所得の減少等を理由に猶予を申請可能 |
|
予定納税額の見直し |
実際の所得に基づき税額を調整 |
|
所得税の軽減 |
所得税の全部または一部を軽減 |
災害により国税の納付や申告ができない場合は、罹災証明書を発行すれば国税の特別措置を利用できます。
●被災証明書で受けられる支援・補助金
被災証明書を使って以下の支援・補助金が受けられます。
・生活福祉金制度による貸付
・公営住宅への入居
詳しく紹介しているので、いざという時のために把握しておくと良いでしょう。
災害によって傷んだ住宅の修繕や増改築、保全のための費用を、条件付きで借りることができます。
|
項目 |
内容 |
|
貸付上限 |
最大250万円 |
|
利率(保証人あり) |
無利子 |
|
利率(保証人なし) |
年1.5% |
|
据置期間 |
最大6か月 |
|
返済期間 |
最長7年間(据置期間終了後) |
ただし、災害援護資金の対象となっている方は、本制度と併用できません。
災害によって自宅が損傷し居住ができなくなった方は、自治体が用意する公営住宅への一時的な入居の対象となります。入居条件は各市町村の判断によりますが、一定期間の家賃免除が適用されます。
3.罹災証明書・被災証明書の発行までの流れ
罹災証明書・被災証明書の発行は、お住まいの市区町村の役所で行われます。以下の流れで手続きをします。
1.住家や非住家など被害状況の写真撮影
2.発行申請
3.被害状況の調査(罹災証明書のみ)
4.罹災証明書・被災証明書の発行
※政府が運営する、行政手続きのオンライン窓口「マイナポータル」でも申請ができます。
発行までの流れを詳しく解説しているので、把握しておけばスムーズな手続きが行えるでしょう。
参考元:「マイナポータル|【災害】被災証明書の発行申請」より
1.住家や非住家など被害状況の写真撮影
罹災証明書や被災証明書の申請には、住家や非住家の被害を証明する写真が必要です。外観や内部の被害状況をわかりやすくするために、できるだけ多角的に撮影をしなければいけません。
写真の撮り方について、住家の被害状況を例に挙げて以下のような方法で撮影すると効果的で被害状況がわかりやすいです。
|
撮影対象 |
ポイント |
|
外観 |
建物全体を4方向から撮影。浸水の場合はメジャーを当てて浸水の深さが分かるようにする |
|
室内 |
被害のある部屋ごとに撮影し、損傷箇所をアップで撮影する |
浸水した場合は、メジャーを当てて「引き」と「寄り」の両方の写真を撮っておくと、被害の程度がより明確になります。片付けや修理を始める前に、必ず撮影を済ませてください。
また被害の細かい部分がわかるように、以下のイメージ図を参考にして撮影してください。

引用元:『鹿島市役所|「罹災(り災)証明書」「被害(被災)証明書」の発行について』より
写真を撮る時は、被災箇所の修理や片づける前に被害状況を撮影しておきましょう。
2.発行申請
発行申請は、お住まいの市町村の窓口で受け付けています。提出に必要な主な書類は以下の3点です。
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
・罹災証明書・被災証明書の交付申請書(自治体ごとに様式あり)
・被害の状態を示す資料(撮影した写真など)
原則として申請者本人が手続きを行いますが、事情により来庁できない場合は委任状を添えて代理人が申請することも可能です。
参考元:『みなべ町|住家被害における罹災証明書の発行について』より
参考元:『小城市役所|「罹災証明書」・「被災証明書」について』より
3.被害状況の調査
提出された申請内容をもとに、市区町村の担当職員が現地調査を行います。調査員は専門研修を受けた職員で、建物の損傷具合や傾斜の有無などを目視で確認します。
例えば被災した住家の場合は「被害認定基準」に基づいて、損害の程度に応じて以下のように6段階で判定されます。
|
被害の程度 |
損害基準判定 |
|
全壊 |
50%以上 |
|
大規模半壊 |
40%以上50%未満 |
|
中規模半壊 |
30%以上40%未満 |
|
半壊 |
20%以上30%未満 |
|
準半壊 |
10%以上20%未満 |
|
準半壊に至らない(一部損壊) |
10%未満 |
参考元:「内閣府 防災情報ページ|災害に係る住家の被害認定」より
調査結果に納得できない場合は、再調査(2次調査)の依頼も可能です。内部の被害や見落としがある場合など、より詳細な確認が行われます。
なお、被災証明書の場合は多くの自治体で現地調査を行わず、被害状況がわかる写真の確認のみで発行できます。
参考元:「古河市|罹災証明書および被災証明書の発行について」より
4.罹災証明書・被災証明書の発行
被害が認定されると、罹災証明書または被災証明書が発行されます。証明書の交付までの所要期間は自治体により異なりますが、概ね1~2週間程度が目安です。詳しい発行期間については、お住いの市区町村役所窓口に問い合わせてみてください。
参考元:「古河市|罹災証明書および被災証明書の発行について」より
また申請期限も、自治体ごとに設定されています。「災害発生日から1カ月以内」や「半年以内」などの、申請期限があることも把握しておきましょう。
4.自然災害の防災アイテムに「Jackery Solar Generator」を備えておこう!
内閣府の中央防災会議では、「南海トラフ巨大地震」による停電で甚大な被害を想定しています。
|
停電地域 |
被災直後の停電件数 |
被災1週間後の停電件数 |
|
東海(静岡、愛知、三重) |
約5,200,000 |
約130,000 |
|
近畿(和歌山、大阪、兵庫) |
約8,700,000 |
約32,000 |
|
山陽(岡山、広島、山口) |
約 3,100,000 |
約12,000 |
|
四国(4県) |
約 2,500,000 |
約110,000 |
|
九州(大分、宮崎) |
約 1,100,000 |
約39,000 |
|
停電地域の合計件数 |
約 20,600,000 |
約320,000 |
※中央防災会議「南海トラフ地震防災対策推進基本計画(令和7年3月31日公表)」
参考:『内閣府 防災情報ページ|南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について (40P)』
地震などの自然災害による停電が発生すると、以下のように家電製品が使えず日常生活に支障をきたします。
・スマホがバッテリー切れになり、家族や友人の安否確認ができない
・テレビが視聴できず、災害情報が入手できない
・冷蔵庫が使えず、食料の保存ができない
電力がストップしてしまうと、普段と同じような生活を送るのが困難に。そこで停電時でも電力供給をして家電製品が使えるように、Jackery(ジャクリ)の「ポータブル電源」を自宅に備えてみてください。
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源は全世界で500万台の販売実績を誇り、世界中のユーザーから信頼されている製品です。震度7の揺れにも耐える堅固な設計で、耐衝撃性に優れているから災害時でも安定して電力供給できます。
さらにソーラーパネルがセットになっている「Jackery Solar Generator」のラインナップもご用意。自家発電でポータブル電源を充電できるから、停電が長期間になっても安心です。
「Jackery Solar Generator」を自宅に1台備えて、家族の安心・安全を確保しましょう。
5.罹災証明書と被災証明書の違いでよくある質問
罹災証明書と被災証明書の違いで、以下の質問が多く寄せられています。
・被災証明書は何に使いますか?
・東日本大震災で被災したのですが、被災証明書は発行できますか?
・罹災証明書のデメリットを教えてください
・被災証明書はどこで発行すればいいですか?
質問に詳しく回答しているので、それぞれ見ていきましょう。
●被災証明書は何に使いますか?
被災証明書は、主に以下の申請をする際に使います。
・生活福祉金制度による貸付
・公営住宅への入居
国の支援制度を利用する際に必要なので、提出先に申請する時は発行しておきましょう。
参考元:『大阪市役所|罹災証明書・被災証明書(自然災害)』より
●東日本大震災で被災したのですが、被災証明書は発行できますか?
東日本大震災で被災した方の被災証明書は発行できます。自然災害以外にも、原子力災害で避難されている方も対象です。
なお、平成23年4月4日以前の旧様式の被災証明書でも引き続き使用できます。新しい様式への交換も可能なので、お住いの市町村役場に相談してみたください。
参考元:『大熊町役場|被災証明書』より
●罹災証明書のデメリットを教えてください
罹災証明書は国から支援や補助金などが受けられるメリットがある一方で、以下のデメリットもあります。
・発行に時間がかかり、すぐに支援を受けられない
・被災から長時間経つと災害による被害か判断が難しくなるため、被災判定が行えない
・罹災証明書の有効期限が過ぎると、支援・補助金などの申請ができない
すぐに発行できないことがあり、また有効期限があるため、罹災証明書が必要な場合はお住いの市区町村の役所で早めに申請をしましょう。
●被災証明書はどこで発行すればいいですか?
被災証明書は、各区役所で申請書を提出すれば発行できます。なお、手続きの際には、以下の書類も必要です。
・本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
・被害状況がわかる写真
被災証明書を発行する際は、必要な書類も忘れずに持っていきましょう。
参考元:『大阪市役所|罹災証明書・被災証明書(自然災害)』より
まとめ
罹災証明書や被災証明書は、住家や非住家の被害程度や事実を証明する大事な書類です。自然災害で被災しても適切に対応できるように、発行までの流れや受けられる支援内容を事前に理解しておくと万が一の時に役立ちます。
また住家が被災していなくても災害による停電でテレビや冷蔵庫などの家電製品が使えず、通常の生活ができないことも想定されます。
停電時でも、家電製品に電力供給ができて安心して過ごせる「Jackery Solar Generator」を自宅に1台備えておきましょう。