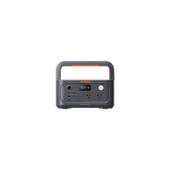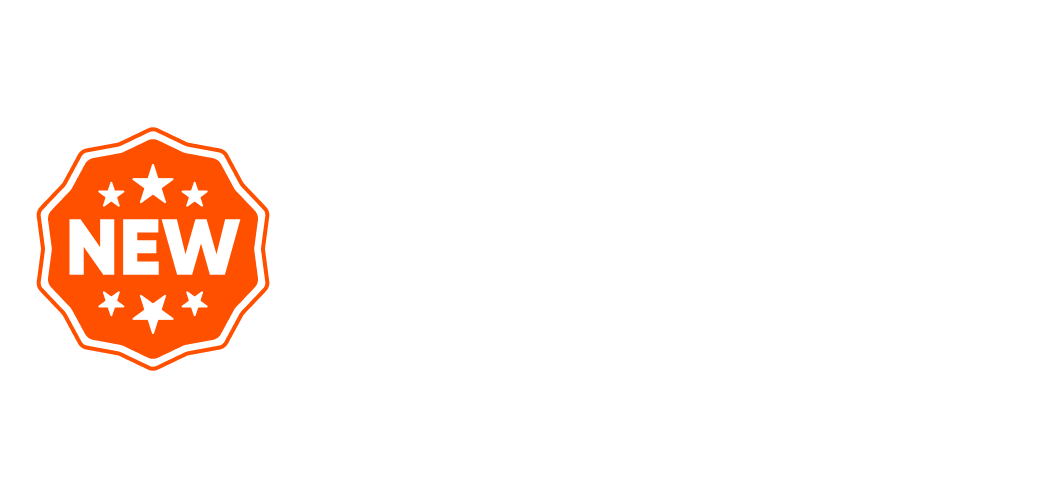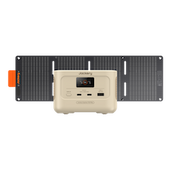1.保育園での火災避難訓練のねらい|園職員・園児・保護者ごとの目的
まずは、園職員・園児・保護者の3つの視点から、火災避難訓練のねらいや目的を解説していきます。
●園職員に対する火災避難訓練のねらい
避難訓練の中心となって行動する責任がある、園職員に対する火災避難訓練のねらいは以下のとおりです。
・火災発生時の対応手順の確認と習得
・子どもたちの安全な避難誘導スキルの向上
・職員同士の連携と情報共有の確認
・非常時に冷静に判断し、行動する意識づけ
園職員は火災発生時の初期対応や避難誘導、保護者への連絡まで迅速かつ冷静に対応できる力が求められます。時間帯や火元の想定を変えるなど、訓練を通してさまざまな場面への対応力を高めていきましょう。
●園児に対する火災避難訓練のねらい
園児にとっての火災避難訓練は、「命を守るための行動」を学ぶ大切な時間です。訓練を通して、以下を染み込ませていくことをねらいとしています。
・指示に従って落ち着いて行動する習慣を身につける
・避難経路や集合場所を覚える
・合言葉「お・か・し・も」を理解する
園児の中には、避難訓練を怖がってしまう子がいます。そうした子たちも避難訓練の意味を理解して冷静に行動ができるように、園職員は年齢に応じた説明や遊びを取り入れて指導しましょう。
●保護者に対する火災避難訓練のねらい
保護者に対する火災訓練のねらいは、以下のとおりです。
・園の避難マニュアルや対応方針を理解する
・非常時の引き渡し方法や連絡手段を把握する
・家庭での防災対策を見直すきっかけを作る
・園の訓練に協力する姿勢を持つ
保護者にも訓練の目的や園の対応を知ってもらうと、万一の際にも安心して子どもを預けられる信頼関係を築けます。訓練を通じて、緊急時に保護者と園がしっかりと連携が取れる関係性を作りましょう。
関連人気記事:【保護者向け】引き渡し訓練のねらい・流れや防災の備えを徹底解説
2.保育園で行う火災訓練の流れ

保育園での火災避難訓練は、実際の火災を想定して以下の4ステップで進められます。
1.火災発生を想定し、火災報知器を作動させる
2.園児の避難誘導と安全確保を行う
3.点呼と安全確保を行う
4.訓練の振り返りと反省点を確認する
4つのステップを、順番に詳しく見ていきましょう。
火災訓練の流れ①火災発生を想定し、火災報知器を作動させる
訓練はまず、火災が発生したという想定から始まります。どの時間帯・場所で火災が起きたかを設定するなど、以下の手順で訓練を進めていきます。
・火元の設定
・119番への模擬通報
・火災報知器・非常ベルの作動
火の元として設定する場所は、「給食室」「電気設備」「保育室」などが多いです。火災報知器やベルを実際に作動させて緊急事態の雰囲気を再現し、本当に火災が起きたときに子どもたちがパニックにならないように訓練していきます。
火災訓練の流れ②園児の避難誘導と安全確保を行う
火災の発生を想定して火災報知器を作動させたら、職員が園児たちを安全な避難経路に沿って誘導していきます。安全な避難誘導のポイントは、下記のとおりです。
・園児を落ち着かせてから避難をスタートする
・「お・か・し・も」のルールを守らせる
・経路の確保や危険箇所を確認する
・避難場所へスムーズに誘導する
年齢や状況に合わせてペースを調整し、混乱や転倒が起こらないように訓練を通じて対応力を養っていきましょう。
火災訓練の流れ③点呼と安全確認を行う
避難が完了したらすぐに点呼をとり、園児全員の安全を確認します。負傷者や体調不良者がいないかの確認し、必要な場合は医療機関へ連絡するなど迅速に対応しましょう。
このときに避難場所の安全性や医療機関への連絡体制を確認しておけば、実際の災害時に園児が怪我をしても慌てず対応ができます。
火災訓練の流れ④訓練の振り返りと反省点を確認する
訓練が一通り終了したら必ず振り返りの時間を設け、良かった点や改善点を洗い出すことが大切です。次回の訓練に活かせるよう、以下のような振り返りを行いましょう。
・職員間での連携はスムーズだったか
・園児の反応や理解度の確認
・誘導ルートや非常口の見直し
・訓練中に起きたトラブルの共有
必要があればマニュアルを更新し、実際の災害時に備えた対策を強化していくことがポイントです。
関連人気記事:保育園での避難訓練のやり方【5ステップ】子どもへ地震を伝える3つの方法
3.保育園の火災避難訓練の合言葉「お・か・し・も」
保育園では園児たちがパニックにならずに安全に避難できるように、「お・か・し・も」を合言葉に火災避難訓練を行っています。
ここでは、火災避難訓練の合言葉「お・か・し・も」の意味や指導方法について解説していきます。
●「お・か・し・も」は災害時の4つの行動をわかりやすくするもの
「お・か・し・も」とは、災害時に守るべき4つの行動の頭文字をとって作られた合言葉です。意味は、以下のようになっています。
・お(押さない)
・か(駆けない)
・し(しゃべらない)
・も(戻らない)
「お・か・し・も」は、園児たちが取るべき行動を分かりやすく理解するために作られています。この合言葉を訓練を通して繰り返し伝えていけば、子どもたちは災害時に落ち着いて行動できる力を身につけられるのです。
● 「お・か・し・も」のルールを守るための指導案
子どもたちに「お・か・し・も」を自然と身につくように教えるには、日常の保育に取り入れて繰り返し伝えるのがポイントです。
子どもたちが楽しんで覚えられるように、絵本や紙芝居を活用するなど工夫をしましょう。ジェスチャーゲームやごっこ遊びなど、体を使って楽しく覚えさせる方法も効果的です。
4.保育園の火災避難訓練を子どもにわかりやすく伝える方法

小さな子どもたちにとって「火災」や「避難」は、なかなか理解しづらいものです。だからこそ、保育園では言葉だけでなく、視覚・聴覚・体験を通じて楽しくわかりやすく伝える工夫をしましょう。
ここでは、子どもたちに火災避難訓練の大切さや行動をしっかり伝えるための方法を紹介します。
●子どもにわかりやすい伝える「話し方」のコツ
伝え方ひとつで、子どもの理解度や反応が大きく変わります。子どもたちに伝えるときは、以下のポイントを意識しましょう。
・難しい言葉は避け、短くてやさしい表現を使う
・声のトーンは優しく、安心感を与える話し方を心がける
・「怖いから逃げる」ではなく「命を守るための大切な約束」と前向きに伝える
子どもたちが「怖い」ではなく、「やってみよう」と感じられる話し方がポイントです。命を守るための大切な練習であることを伝えるなど、子どもたちが怖がらない工夫をしましょう。
●楽しい「お話」で伝える
避難のルールを一方的に教えるのではなく、ストーリー仕立てのお話で伝える方法もおすすめです。例えば、以下のようなお話で伝えていくと、子どもたちも楽しみながら学んでくれます。
・「もしも、森の保育園に火事がきたら?」という空想ストーリー
・キャラクターを使って、「お・か・し・も」を守る姿を描く
・先生が登場人物になり、寸劇のように演じる
お話にすることで子どもたちは自然に集中し、内容をイメージしやすくなります。ストーリーを通じることで、「自分だったらどうする?」と考える力も育てられるでしょう。
●「クイズ」で遊びながら伝える
遊び感覚で火災避難訓練を子どもたちに伝えたいなら、「クイズ」がおすすめです。例えば、以下のような問題を作って、子どもたちに出題してみましょう。
・火事のときにやっていいのはどれ? A.走る B.押す C.静かに歩く
・「お・か・し・も」の「も」はなに?
・火事のときに戻っていい?戻っちゃダメ?
全員で手を挙げたり〇×で答えたり、体を使ったクイズにするとより盛り上がります。
●「イラスト」を活用して視覚的にわかりやすく伝える
視覚的な情報は、とくに年齢の低い子どもたちに伝える際におすすめの方法です。以下のようなイラストを用意すると、子どもたちが楽しみながら学べます。
・「お・か・し・も」のルールを表すイラスト
・火災のときの様子と、安全な避難の流れ
・避難する子どもと誘導する先生の様子
日常的に目にすることで自然と身につくので、保育室に掲示物やポスターとしてイラストを貼っておくのもおすすめ。言葉だけでなく、視覚的に分かりやすく子どもたちに伝えていきましょう。
●「紙芝居」で火災時の行動を物語で伝える
以下のような内容の紙芝居は「お話」とイラストの両方を活かせるため、避難訓練の導入や復習にぴったりの方法です。
・火災が起きた場面を子どもたちが体験できるように演出する
・登場人物と一緒に「お・か・し・も」を守る流れを描く
・最後に「みんなも今日からできるね!」と呼びかけて実践意識を高める
先生の読み方や間の取り方を工夫するだけでも、子どもたちの集中力がぐんとアップします。子どもたちを紙芝居の世界に引き込み、より分かりやすく災害について伝えていきましょう。
5.保育園で火災避難訓練を行う前の事前準備
火災避難訓練は、ただ「訓練をする」だけでは効果は十分ではありません。事前にしっかりと準備し、全体の流れや役割を把握したうえで実施することが実効性のある訓練につながるのです。
ここからは、火災避難訓練の前に行うべき事前準備をくわしく解説していきます。
●訓練計画の作成とスケジュール調整
まずは、火災訓練の目的・対象・方法・タイミングなどを明確にした「訓練計画書」を作成しましょう。
【事前に計画しておきたい項目】
・実施日と時間帯
・想定する火災発生場所
・非常ベルや報知器の使用有無
・訓練実施後の振り返り会議の予定
訓練計画を作成する際は、他の行事や保護者対応と重ならないようにスケジュール全体を調整するのがポイント。また天候不良など急な変更に対応できるように、予備日を設定しておくと安心です。
●園職員への事前教育と役割分担の確認
訓練当日に混乱が起きないよう、職員一人ひとりが自分の動きや役割をしっかりと把握しておきましょう。
【園職員が事前に確認しておきたいこと】
・火災発見時の初動対応の担当
・園児の誘導担当
・点呼・安全確認の役割分担
・けが人発生時の対応や応急処置の担当
実際の避難ルートを歩きながら確認すると、より具体的な動きがイメージしやすくなります。事前にシミュレーションし、不安や不明点を解消して慌てず冷静な対応ができるように備えましょう。
●避難経路と避難場所の確認と調整
避難経路や避難場所に問題があると、災害時に子どもたちに危険が及ぶ可能性があります。以下のポイントを確認し、安全に避難ができる体制を整えましょう。
・経路上に障害物がないか、ベビーカーや避難車の通行が可能かを確認する
・避難場所が安全かつ園児全員が収容できるスペースがあるか確認する
・非常口や誘導灯を点検する
必要に応じて経路や場所を見直し、園全体で共有しましょう。非常時に混乱が起きないように、定期的に職員同士で情報を再確認する機会を設けると安心です。
●火災避難訓練マニュアルの作成と共有
火災避難訓練の手順や役割分担を明記した「避難訓練マニュアル」は、訓練の質を高めるための必須アイテムです。
【避難訓練マニュアルの例】
・手順ごとに「誰が・何を・いつ・どうやって」行うかを明記する
・年齢別で対応が異なる点を整理する
・非常時の連絡体制や保護者への対応方法も記載する
避難訓練マニュアルは全職員に配布し、必要に応じて見直しや更新を行いましょう。定期的に勉強会を実施し、職員全体の防災意識を高める機会を設けるのも効果的です。
●保護者への事前連絡と協力依頼
避難訓練は園内だけで完結するものではありません。以下のような情報を保護者と共有し、信頼と安心感を高めていきましょう。
・訓練の目的や実施日、内容を文書やアプリで事前に通知する
・引き渡し訓練の場合は、参加のお願いと対応方法を詳しく説明する
・訓練後に結果報告と反省点を共有する
保護者に園の安全対策を正しく理解してもらうことが、災害時の混乱防止にもつながります。しっかりと情報を供給し、保護者と園が協力し合える体制を整えましょう。
6.保育園の防災対策にはこれ!「Jackery Solar Generator」で子どもの安全を守ろう
火災や地震など、万が一の災害時に保育園でとくに懸念されるのが停電への備えです。照明・連絡手段・冷暖房など、電力が止まってしまうと園児たちの安全確保にも大きな影響が出てしまいます。
そんなときに役立つのが、ポータブル電源とソーラーパネルがセットになった「Jackery Solar Generator」です。ポータブル電源とは、持ち運び可能でコンセント(AC100V電源)も搭載した大容量バッテリーのこと。燃料不要の安全に使える非常用電源として、保育園をはじめとする保育施設や教育機関で注目されています。
【Jackery Solar Generatorの保育園での活用法】
・保護者への連絡用タブレットやスマホの充電ができ、いち早く安否情報を伝えられる
・パソコンやサーバーを稼働し、園内の基幹システムを早期に復旧できる
・災害時の園内緊急放送や職員間の連絡用トランシーバーの充電に使える
・停電時でも冷蔵庫を稼働させて給食の材料や園児の薬を適切に保管できる
・夜間に避難が必要な場合も園内を照らして安全に誘導できる
「Jackery Solar Generator」の魅力は、その安全性の高さにあります。防災製品等推奨品マーク(※)を取得しており、騒音や排気ガスも出ないので保育園で使用しても安全です。
保育園の防災力をグッと高める「Jackery Solar Generator」で、子どもたちの大切な命を守りましょう。
※防災製品等推奨品マーク:防災用品の安全性や機能性が防災安全協会の独自基準を満たしていることを示すマーク
もっと多くの商品を見る
7.保育園の火災避難訓練に関するよくある質問
ここからは、保育園の火災訓練に関するよくある質問にお答えしていきます。
●保育園の火災避難訓練は、どのくらいの頻度で実施しますか?
保育園では、消防法によって少なくとも避難訓練を月に1回実施することが義務付けられています。
火災だけでなく地震や不審者侵入など、さまざまな非常事態を想定して訓練する必要があります。そのため、他の訓練とあわせて年3〜4回程度行われるケースが多いです。
参考:こども家庭庁
●保育園の訓練では、窓からの避難も想定したほうがいいですか?
保育園の訓練では、窓からの避難も想定しておく必要があります。
とくに火災では、出火場所や煙の広がりによって通常の避難経路が使えない場合もあるので、窓からの脱出手段の確認や訓練をしておきましょう。
まとめ
今回は、保育園の火災訓練のねらいや子どもに定着させるコツについて解説しました。保育園で火災が起こったとき、何よりも優先すべきなのは子どもたちの命です。
災害時に電気が使える安心感は、保育士や保護者にとって大きな支えとなってくれます。定期的な避難訓練を実施するとともに、「Jackery Solar Generator」を導入して、災害から子どもたちを守る体制を整えましょう。