1.天体観測におすすめの季節は「冬」
1年の中で天体観測に最も適している季節は冬です。空気が乾燥している冬には、星がくっきりと綺麗に見えます。降水量も少ないため、高確率で満天の星空が見られるでしょう。
また、冬は日が短い季節でもあり、17時には日没を迎えることも少なくありません。日の出も遅くなるため、夜の時間が1年で最も長い季節なのです。天体観測を思う存分堪能したい方にとっては、絶好の季節と言えるでしょう。
2.冬が天体観測に最適な季節である3つの理由
寒い冬の夜、空を見上げると驚くほど鮮やかな星々が輝いています。その美しさは、空気の透明度や明るい星座の配置などに関係しています。冬が天体観測に最適な季節である理由は、以下のとおりです。
①大気中に含まれる水蒸気が少ない
冬が天体観測に最適な季節である理由として、空気の乾燥が挙げられます。冬は大気中に含まれる水蒸気が少ないため、大気の透過率が高くなるのです。反対に大気の水蒸気量が多くなると空は霞み、星が鮮明に見えません。
水蒸気は星の見えやすさに直結するので、冬に限らず水辺付近は天体観測に不向きと言われています。冬は大陸からの高気圧に覆われるため、太平洋岸が乾燥します。
②一等星の見える数が多い
冬は、1年で最も一等星の見える数が多い季節です。一等星とは、明るさの等級が最も高い星を指します。肉眼でもよく見える明るい恒星が多いので、冬の夜空は煌びやかに輝くのです。季節ごとに見える一等星を紹介します。
|
季節 |
一等星 |
|
春 |
アークトゥルス、スピカ、レグルス |
|
夏 |
ベガ、デネブ、アンタレス、アルタイル |
|
秋 |
フォーマルハウト |
|
冬 |
プロキオン、ベテルギウス、リゲル、シリウス、カペラ、ポルックス、アルデバラン |
③揺らぎによる瞬きがある
空気の密度の違いによる揺らぎも、冬が天体観測に最適な季節である理由の一つです。気温や湿度が低く、風が強い冬の夜空では、星の光が大気層を通過する際に密度の違いで揺らぎが起こります。揺らぎが顕著になればなるほど、星が綺麗に瞬くのです。
関連人気記事:冬の天体観測のおすすめスポット8選!冬に星空が綺麗な理由や持ち物も解説
3.初心者必見!季節ごとに観測できる星座と天体の特徴
常に空に存在している星たちも、季節によって観測できる天体は異なります。地球は1年を通して太陽の周りを公転しているので、季節ごとに宇宙を見ている角度が変わるのです。季節ごとに観測できる星座と天体の特徴を紹介します。
●【春】おとめ座銀河団

春の夜空には、1500個前後にのぼる大量の銀河が密集する「おとめ座銀河団」が見られます。地球が所属する天の川銀河もおとめ座銀河団に含まれているのが特徴です。おとめ座銀河団の中心には、M87と呼ばれる銀河が存在します。
M87は中心に超大質量のブラックホールがあり、地球から5900万光年も離れています。おとめ座銀河団は、焦点距離の短い望遠鏡や望遠レンズでも十分観察できるでしょう。
●【夏】夏の大三角

出典: ケンコー・トキナー「夏の大三角と天の川を見てみよう! 」
夏の夜空を見上げると、夏の大三角がひときわ明るく輝いて見えます。夏の大三角を構成するのは、こと座の1等星「ベガ」、わし座の1等星「アルタイル」、はくちょう座の1等星「デネブ」です。
夏の大三角は、街明かりの少ない暗い空ではっきりと観察できます。三角形の中には天の川が流れており、右側に目を移すとさそり座の1等星「アンタレス」が見えるでしょう。天の川沿いには、夏を代表する星座がたくさん観察できます。
関連人気記事:夏の天体観測で見られる星座・流星群!星空が綺麗に見える条件や持ち物も紹介
●【秋】秋の四辺形

出典:暦生活「秋の四辺形」
秋の夜空には、「秋の四辺形」や「ペガススの大四辺形」と呼ばれる四角形に並ぶ明るい星が見られます。秋の四辺形を構成するのは、ペガスス座の「マルカブ」「シェアト」「アルゲニブ」、アンドロメダ座の「アルフェラッツ」です。対面する2辺をそのまま延ばすと、天の北極付近に交わるため、北の方角を探す際にも役立ちます。
●【冬】冬の大三角
1年で最も星が綺麗に見える冬の夜空には、冬の大三角がひときわ輝いています。冬の大三角を構成するのは、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオン、オリオン座のベテルギウスです。冬の大三角をまたぐように、ぎょしゃ座やふたご座、おうし座、こいぬ座、おおいぬ座、オリオン座といった星座が勢ぞろいしています。
関連人気記事:初心者でも安心な天体観測のガイド 星も月も楽しめるおすすめグッズやマナー
4.季節共通!天体観測に欠かせない必需品5選
 季節によって見える天体は異なりますが、天体観測をするための道具は共通しています。一度揃えてしまえば、1年中天体観測を満喫できるでしょう。天体観測を本格的に始めたい方は、以下の5つのアイテムから揃えてみてください。
季節によって見える天体は異なりますが、天体観測をするための道具は共通しています。一度揃えてしまえば、1年中天体観測を満喫できるでしょう。天体観測を本格的に始めたい方は、以下の5つのアイテムから揃えてみてください。
①星座早見盤
現在の日時に見られる星座を瞬時に把握するために、星座早見盤は大活躍します。方角や時刻が書かれた円盤と、日付や星が書かれた円盤が重なっているのが特徴です。
日付と時刻が合うように円盤を回したら、自分が向いている方角を手前にして外にかざしてみましょう。すると、現在見える星や星座が特定できます。星座早見盤は電池や電波が不要なので、山間部や電波の届かない場所でも安心です。
②双眼鏡・望遠鏡
天体観測で双眼鏡と望遠鏡のどちらを選ぶべきか、迷われる方も多いのではないでしょうか。双眼鏡は軽量かつコンパクトなので、手軽に天体観測を楽しみたい方に最適です。価格も望遠鏡より安く設定されているので、初心者でも揃えやすいでしょう。
一方の望遠鏡は、双眼鏡よりも複雑な構造をしているため、より詳細な観察が実現します。本格的に天体観測を趣味にして、より遠くの天体を細かく観察したい方におすすめです。
③懐中電灯
天体観測では、夜間の作業や移動が多いため懐中電灯が欠かせません。星が綺麗に見えるような暗い場所では、足元の安全を確保する必要があります。天体を探すために必要な星座早見盤も、懐中電灯で照らさなければ見えにくくなります。
天体観測で使用する懐中電灯は、赤色系のライトがおすすめです。星を鮮明に見るためには目が暗闇に慣れている状態が望ましいですが、白色系のライトだと暗順応を妨げてしまいます。赤色系の懐中電灯が手に入らない場合は、赤いセロハンを巻きつけておきましょう。
④コンパス
コンパスは、天体観測をスムーズに進めるために必要なアイテムです。星座早見盤で夜空に見える星を確認するためには、コンパスで見ている方角を把握しなければなりません。
星座や惑星は特定の方角に現れるため、コンパスがあれば正確に観測ポイントを設定できます。機材の正確なセッティングも可能にするため、これから本格的に天体観測を趣味にしたい方にとっては必需品と言えるでしょう。
⑤ポータブル電源
天体観測を快適に楽しむためには、ポータブル電源が必要です。ポータブル電源とは、内部に大量の電気を蓄電し、コンセントがない屋外でも電化製品に給電できる機器を指します。天体観測でポータブル電源が活躍する場面は、以下のとおりです。
・電気ストーブや電気毛布を稼働し、温まりながら長時間天体観測を楽しめる
・電子レンジや電気ケトルを使い、簡単な軽食が作れる
・LEDライトを点灯し、足元の安全を確保できる
・天体を調べるためのスマホを常にフル充電にしておける
・星空を撮影するためのカメラのバッテリーを、複数回満充電にできる
特に星が見えやすい場所は標高が高くなる傾向にあるので、寒さ対策が欠かせません。万が一、ライトの充電や電池が切れてしまうと、辺りは真っ暗闇に包まれて危険です。ポータブル電源を用意して、安全で快適な天体観測を実現しましょう。
天体観測で使用するポータブル電源は、創業から13年間で世界販売台数500万台を突破した実績を誇るJackery(ジャクリ)製品がおすすめです。耐振動、耐衝撃性、耐熱性などに優れているため、屋外での使用にも向いています。
リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しているので、10年以上も天体観測に役立つでしょう。業界最大級の軽量コンパクト設計により、持ち運びの邪魔にもなりません。
もっと多くの商品を見る
関連人気記事:星空観察に最適なおすすめの場所9選|天体観測に必要なもちもの
5.【季節別】天体観測に必要なアイテム4選
天体観測を楽しむには、季節ごとの気温に適したアイテムも必要です。夏には虫も多くなるので、対策しなければ天体観測を十分に楽しめないでしょう。季節別の天体観測に必要なアイテムは、以下のとおりです。
①【春・夏】虫除けスプレー
気温が暖かくなる春や夏には虫が多くなるため、虫除けスプレーを用意しましょう。蚊が最も活発になる気温は、22℃〜30℃と言われています。
特に星が綺麗に見られるような山奥には虫が多く生息しているので、体に虫除けスプレーを噴射しておく必要があります。虫によって効果のある成分は異なるので、複数の虫除けアイテムを使い分けるのがおすすめです。
②【春・夏】ポータブル扇風機
春や夏の夜は、汗をかくほど蒸し暑くなることもあります。ポータブル扇風機があれば、冷風を浴びながら快適な気温で天体観測に集中できるでしょう。長時間天体観測を楽しむ方は、両手を自由にできる首掛け扇風機がおすすめです。
ポータブル電源も併せて用意しておくと、ポータブル扇風機の充電が切れる心配はありません。静音性の高いDCモーターが搭載されたタイプを選ぶと、動作音が気にならずに天体観測を満喫できます。
③【秋・冬】防寒着
秋・冬の寒さ対策として、防寒着の着用が欠かせません。汗冷えを防ぐために、インナーには汗を素早く吸水拡散する素材を選びましょう。中間着には、保温着を重視してフリースがおすすめです。毛と毛の間に空気の層を作り、熱を逃がしづらくなります。
アウターには、防水・防風性に優れたジャケットを選びましょう。星が綺麗に見える場所は、駐車場から離れている場合があります。突如雨が降ってきて車内で雨宿りしようにも、防水性に劣るアウターでは、駐車場までの道中で服の内部まで雨が浸透してしまいます。
④【秋・冬】電気ストーブ
スイッチを入れてすぐに暖が取れるアイテムとして、電気ストーブがあると便利です。石油や灯油を使ったストーブよりも軽量かつコンパクトなので、天体観測を行う場所まで気軽に持ち運べます。電気ストーブの主な種類と特徴は、以下のとおりです。
|
電気ストーブの種類 |
特徴 |
|
カーボンヒーター |
・炭素繊維に電気を流し、遠赤外線で暖める ・リーズナブルな価格で購入できる |
|
グラファイトヒーター |
・黒鉛に電流を流して、遠赤外線で暖める ・スイッチを入れてから暖まるまでが早い |
|
ハロゲンヒーター |
・ハロゲンランプが放出する遠赤外線で暖める ・コンパクトなサイズが多い |
6.天体観測を楽しむための注意点3選
満天の星空を眺めるひとときは、忘れられない思い出になること間違いありません。しかし、星を見たいがために安全対策を疎かにすると、大事故につながる恐れがあります。天体観測を楽しむための注意点は、以下のとおりです。
①危険な場所に近づかない
星が綺麗に見える場所は、明かりが少なく、危険も伴います。川や池、崖のそばなどの危険な場所には近づかないようにしましょう。水辺では転倒や溺水、高台や崖付近では滑落のリスクがあります。
山間部や森林では、熊や猪などの野生動物に遭遇するリスクもあるため、一人で山奥に入っていくのは危険です。星が見やすい場所は電波が通っていない場合もあり、駐車場から離れすぎると、帰り道が分からなくなる可能性があります。
②暗闇は足下を照らしながら進む
暗闇では、懐中電灯で足元を照らして安全を確保しながら進みましょう。暗い森の中で足元を確認せずに突き進むと、木の根や段差につまづいて怪我を負うリスクが高まります。
崖に気付かず進んでしまうと、転落して命を落とす事態にもなりかねません。天体観測場所に着いたら、目を慣らすために安全面に支障のない範囲で懐中電灯の光を消してください。
③周囲の迷惑にならないよう配慮する
天体観測では、周囲の迷惑にならないように十分な配慮が必要です。星が見やすいからといって、他人が所有する敷地には許可なく入ってはいけません。周囲に住宅がある場合には、騒音を出さないように気を付けましょう。
車のドアを開閉する音や話し声は、騒音トラブルにつながりかねません。天体観測スポットでは、他の人がすでに観測している場合もあるため、車のヘッドライトは極力消灯しましょう。
まとめ
天体観測で見える天体は、季節によって異なります。満天の星空を鮮明に見たい方は、空に不純物が少ない冬の時期がおすすめです。秋・冬の観測では、寒さ対策グッズを忘れないようにしましょう。ポータブル電源があると、快適な天体観測が実現します。
この記事で紹介した天体観測グッズを揃えて、季節ごとに変わる天体を楽しんでください。




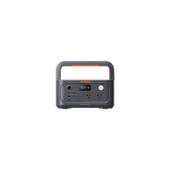

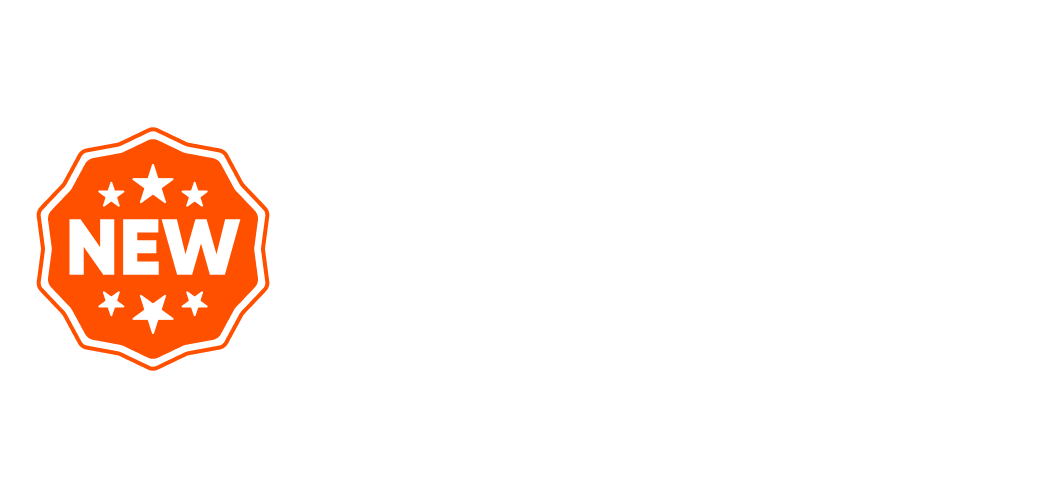






































































































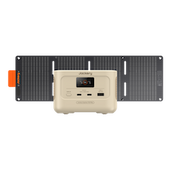






























コメント