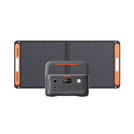1.耐震補強する前に知っておくべき基礎知識
耐震補強が必要か判断するには、まず基本的な知識を身につけることが必要です。工法の種類や必要性を理解すると、自宅に最適な対策を選べます。
●耐震補強の種類|耐震・制震・免震
耐震補強の種類は、大きく分けて以下の3つです。
|
方法 |
特徴 |
効果 |
主な対象 |
コスト・工事のしやすさ |
|
耐震 |
建物の構造を強化する(壁・柱・梁を補強) |
建物全体の強度を高め、地震に耐える |
既存住宅、新築住宅 |
最も一般的で、既存住宅でも簡単に工事できる |
|
制震 |
制震装置(ダンパー)で地震のエネルギーを吸収する |
耐震よりも揺れを軽減、家具の転倒や内装の損傷を減らす |
高層ビル、マンション、近年は戸建て住宅でも増加 |
耐震よりコスト高めだが後付けもできる |
|
免震 |
建物と地面の間に免震装置を設置する |
免震よりもさらに揺れを軽減できる |
主に大規模建物や高額な住宅 |
コストが高く、既存住宅への後付けはできない |
それぞれの特徴を理解したうえで、予算や建物の状況にあわせて方法を選ぶことが、効果的な地震対策につながります。
●耐震補強工事のやり方は?4つの主な工法
耐震補強工事の主な工法は、以下の4つです。
|
補強方法 |
内容 |
効果 |
|
耐力壁の増設 |
・既存の壁に構造用合板や筋交いを追加する ・施工が簡単で住みながら工事ができる |
・横揺れに強くなり、建物全体の強度が高まる |
|
基礎の補強 |
・無筋コンクリート基礎に鉄筋を追加、または基礎を増し打ちする |
・建物を支える基礎部分が強化され、耐震性が向上する |
|
屋根の軽量化 |
・重い瓦屋根を軽い金属屋根材に交換する |
・建物の重心が下がり、揺れにくくなる ・壁や柱への負担も軽減される |
|
接合部の補強 |
・柱と梁、柱と土台などの接合部に金物を追加する |
・地震時に破損しやすい接合部を補強し、倒壊リスクを減らす |
複数の工法を組み合わせて、建物全体の耐震性能を向上できます。
●木造住宅は住みながら耐震補強できる?構造別の違い
木造の住宅では、壁の一部を解体して耐力壁を増やしたり、基礎の補強をしたりする際も、多くの場合で住む場所を確保しながら工事を進められます。工事期間中は騒音や粉塵が発生しますが、仮住まいの必要はありません。
一方、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物では、大規模な工事が必要になる場合があります。一時的な仮住まいが必要になることもあるため、事前に施工業者と詳細な打ち合わせが必要です。
住みながらの工事を希望する場合は、工事のスケジュールや生活への影響について、施工前に確かめましょう。
参照:内閣府防災情報「耐震補強方法の例」
●耐震補強工事が必要な家の特徴
耐震補強が必要な住宅には特徴があります。該当する場合は、耐震診断を早急に受けることをおすすめします。
|
建物の特徴 |
内容 |
|
昭和56年以前に建てられた建物 |
・旧耐震基準で建築されており、強度不足の可能性がある |
|
壁面積が少ない建物 |
・1階が車庫などで壁が少なく、上階を支える力が足りないと1階部分が潰れやすい ・大きな吹き抜けがあると、壁や柱が少なく力が集中しやすいため倒壊リスクが高い |
|
基礎にひびが入っている建物 |
・地盤沈下の可能性がある ・軟弱な地盤に建つ住宅は揺れが増幅しやすく、建物全体の耐震性が低下する恐れがある |
|
耐震診断で評点1.0未満 |
・倒壊の可能性があると評価され、早急に耐震補強工事が必要である |
特徴に一つでも当てはまる場合は、耐震診断を受け、必要に応じて補強工事の実施しましょう。
2.「耐震補強は意味がない」と言われる5つの理由

「耐震補強は意味がない」と言われる背景には、耐震補強に対する誤解や地震に対する不安などがあります。しかし実際には、耐震補強が必要な住宅は少なくありません。耐震工事をしなければ、大地震の際にケガや命を落とす危険が高まります。
耐震補強に対する誤解を解消して、必要な耐震補強をすることで、地震から家族や住まいを守りましょう。
①耐震補強で揺れは防げないから
「耐震補強をしても地震の揺れは防げない」という声をよく耳にしますが、耐震補強は地震の揺れを無くすことはできません。耐震補強の目的は揺れを防ぐことではなく、建物が倒壊しないようにすることです。
地震時に建物が揺れること自体は避けられませんが、耐震補強により住宅の損傷を抑え、避難時間を確保できます。
②耐震補強しても効果が実感しづらいから
耐震補強の効果は目に見えにくく、工事後に日常生活で変化を感じることはほとんどありません。実感のしにくさが「意味がない」と思われる理由の一つです。
耐震補強の効果は、実際に大きな地震が発生した時に初めて発揮されます。普段の生活では工事前後の違いを感じることはなく、費用をかけた実感が得られにくいです。火災保険や生命保険と同様に、万一の事態に備える「保険」の役割があります。
③施工不良の事例を聞いたことがあるから
耐震補強工事における施工不良の報道を目にして、不安を感じる方もいます。施工不良が起きる主な原因は、技術力の低い業者による工事や、コスト削減を優先した手抜き工事です。必要な金物が使われていなかったり、必要な補強が見落とされていたりするケースが報告されています。
施工不良のリスクを避けるには、以下のポイントを確認して、信頼できる施工業者を選びましょう。
・自治体が認定している耐震改修事業者を利用する
・地域での実績が豊富な会社を選ぶ
・アフターフォローや保証がある
・疑問や不安に丁寧に対応してくれる
慎重に業者を選ぶことで、施工不良のリスクを減らし、耐震性能を向上できます。
④新耐震基準の建物で補強は不要だと考えられているから
1981年以降の新耐震基準で建てられた建物は、耐震補強が不要だと考える方も多いです。しかし、新耐震基準の建物でも、経年劣化により耐震性能が低下している可能性があります。
シロアリ被害や雨漏りによる木材の腐朽、基礎のひび割れなど、時間の経過とともに建物の強度は徐々に低下します。
また、2000年に建築基準法の改正があり、接合部の金物使用や耐力壁の配置バランスについて、より厳しい規定が設けられました。1981年から2000年の間に建てられた建物は、現行基準と比べると耐震性能が劣る場合があります。
新耐震基準の建物であっても、定期的な点検と必要に応じた補強により、より高い安全性を確保しましょう。
参照:東京都耐震ポータルサイト「新耐震基準の木造住宅への耐震化支援」
⑤大地震では補強しても倒壊すると思われているから
巨大地震が発生すれば、どんなに補強しても建物は倒壊する」という考えから、耐震補強を諦める方もいます。
たしかに想定を超える巨大地震では、どのような建物でも完全に安全とは言えません。しかし、耐震補強により倒壊までの時間を延ばし、避難の機会を増やすことは可能です。また、建物の損傷を軽減すると、地震後の復旧が早くなります。
2016年の熊本地震では震度7の地震が2回起きましたが、耐震等級3の住宅の87.5%が無被害で、残りの建物も軽微な被害にとどまりました。完璧な対策は存在しませんが、できる限りの備えをすれば、生存確率を高められます。
参照:国土交通省「耐震性能を等級で確認して、安心の住まいづくり」
3.倒壊リスクを下げるために耐震補強は意味がある!
耐震補強に否定的な意見があるものの、補強は確実に建物の安全性を向上させ、生命を守る効果的な手段です。地震による死傷者の多くは建物の倒壊や家具の転倒によるもので、耐震補強すれば建物の耐震性能が向上し、地震時の倒壊リスクを軽減できます。
2016年の熊本地震では以下の表のとおり、旧耐震基準の倒壊率は28.2%で、新耐震基準の2000年以降に建てられた建物の倒壊率2.2%と比較して顕著に高かったです。
|
建築時期 |
無被害 |
軽微・小破・中破 |
大破 |
倒壊・崩壊 |
|
旧耐震基準 |
5.1% |
49.1% |
17.5% |
28.2% |
|
新耐震基準 |
20.4% |
61.2% |
9.7% |
8.7% |
|
新耐震基準(2000年基準) |
61.4% |
32.6% |
3.8% |
2.2% |
また、建物の倒壊を防ぐことで、地震後の避難生活や生活の再建もしやすくなります。住まいを失うことの精神的・経済的負担は大きく、耐震補強により住み続けられる環境を維持する価値は高いです。
参照:国土交通省「「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント」
関連人気記事:【家族で生き抜く】災害に強い家の特徴とは?間取り・設備・メーカーを解説
4.耐震補強工事にかかる費用と工期の目安

耐震補強の費用相場や工事の流れを知ると、適正価格が分かりぼったくりや手抜き工事を防ぐ判断材料になるため、信頼できる業者を選べます。以下でチェックしておきましょう。
●耐震補強工事の費用相場
耐震補強工事の費用は建物の規模や補強内容・立地条件により大きく異なりますが、築40年〜50年の木造住宅では100万円から350万円が相場となっています。
具体的な工事内容別の費用は、以下のとおりです。
・耐力壁の増設:1か所あたり10万〜30万円
・基礎の補強:1平方メートルあたり2万〜5万円
・屋根の軽量化:80万〜300万円
・接合部の補強:1か所あたり1万〜15万円
解体が必要な場合や、狭小地での作業が必要な場合は、費用が高くなる傾向です。また、補強範囲が広範囲に及ぶ場合は、全体的な費用も増加します。
正確な費用を把握するには、複数の業者から見積もりを取り、工事内容と費用のバランスを比較しましょう。
●必要な期間は?耐震診断からリフォームまでの流れ
耐震補強工事は耐震診断から完成まで、一般的に3ヶ月〜6ヶ月の期間が必要です。
耐震診断には2週間〜1ヶ月を要します。診断結果に基づいて補強設計を行うには、さらに2週間〜3週間が必要です。
実際の工事期間は補強内容により大きく異なります。主な工事にかかる期間の目安は、以下のとおりです。
・部分的な耐力壁の増設:1週間〜2週間
・基礎の補強を含む場合:1ヶ月〜2ヶ月
・屋根を軽量化する場合:1週間〜2週間
部分的な補強なら2週間程度で完了する場合もありますが、診断から工事完了まで3ヶ月〜6ヶ月程度を見込んでおくと余裕を持って進められます。
5.補助金や税制優遇を活用して耐震補強工事の費用を削減!
耐震補強工事の費用負担を軽減するため、国や自治体のさまざまな支援制度があります。制度を上手に活用すれば工事費用を抑えることが可能です。
●耐震補強で使える補助金・助成金
多くの自治体で耐震診断や耐震改修工事に対する補助金制度が設けられています。補助内容は自治体により異なりますが、工事費用の一部を補助する制度です。
東京都文京区の場合、木造住宅の耐震改修助成では、工事費用の最大75%(上限120万円~240万円)が補助されます。耐震診断も、助成を受けられる制度を設けている自治体が多いです。
補助金の対象となる建物の条件は、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であることが基本です。ただし、自治体によっては平成12年5月31日以前の建物まで対象を拡大している場合もあります。
申請手続きは、必ず工事の契約前に行わなければいけません。事後申請は認められないため注意が必要です。
●耐震補強で使える税制優遇
耐震改修工事を行った場合、以下の表に示す所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けられます。
|
制度名 |
内容 |
|
所得税の耐震改修特別控除 |
耐震改修工事費用の10%(最大25万円)を所得税額から直接控除できる |
|
固定資産税の減額措置 |
耐震改修工事を行った住宅は、工事完了年の翌年度から一定期間、固定資産税が2分の1に減額される |
|
住宅ローン減税 |
耐震改修費用を住宅ローンで賄った場合、年末ローン残高の0.7%を所得税から控除できる |
税制優遇を活用するには、工事の時期や資金計画を慎重に確認する必要があります。税理士や自治体の相談窓口を活用し、状況に合った方法を選びましょう。
参照:越前市「耐震改修に伴う所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置について」
参照:国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」
6.耐震補強とあわせて行うべき防災対策4選

耐震補強工事と一緒に実施すると、地震に対する安全性を高められる防災対策があります。建物の強化とあわせて生活環境全体の安全性を向上させましょう。
①家具の転倒防止や窓ガラスの飛散防止など住宅内の安全対策
建物が倒壊を免れても、室内の家具や家電の転倒によってケガをする危険があります。以下のよう対策することで、家の中を安全に保てます。
・大型家具:L字金具や突っ張り棒を使って壁や天井に固定する
・食器棚や本棚:扉が勝手に開かないように耐震ラッチを取り付ける
・テレビや電子レンジなどの家電製品:耐震マットや耐震ベルトで固定する
・窓ガラス:飛散防止フィルムを貼る
低コストで実施でき、すぐに始められる防災対策としておすすめです。
関連人気記事:地震の備えとして家具にできる7つの対策|防災グッズと二段構えで万全
②ハザードマップや避難経路の確認
地震が発生した際、迅速かつ安全に避難するには、事前の準備が欠かせません。まずは自治体が公開しているハザードマップを確認し、自宅周辺の災害リスクを把握します。
ハザードマップでは地震による揺れやすさや液状化の危険度、津波の浸水想定区域などが確認できます。最寄りの避難所までの複数の経路を確認し、実際に歩いて確かめておくことが災害時に慌てないために大切です。
家族全員で避難計画を共有し、定期的に防災訓練をすれば、いざという時にパニックにならないように準備しましょう。
③飲料水や非常食など備蓄品の用意
大地震後は、ライフラインの復旧に時間がかかることが予想されます。最低でも3日分、できれば1週間分の備蓄を用意することが推奨されています。
飲料水は1人1日3リットルが目安です。非常食は缶詰やレトルト食品、乾パンなど調理が要らず、長期保存が可能なものを選びます。定期的に賞味期限を確認し、期限の近いものから消費する「ローリングストック」方式で管理すると無駄がありません。
その他、以下の防災グッズも準備しておきます。
・救急用品
・常備薬
・簡易トイレ
・懐中電灯
・ラジオ
季節に応じて、防寒具や冷却グッズも用意するのもおすすめです。
④停電・断水に備えたライフラインの確保
地震により停電や断水が発生すると、日常生活に大きな支障が生じます。特に停電は、情報収集や連絡手段を断たれるため、安全を確保するためにも停電対策は必須の防災対策です。
停電対策には以下のようなグッズがあります。
・モバイルバッテリー
・手回し発電機
・ポータブル電源
停電時に家電製品を動かしたい方は、大容量・高出力でコンセントも使えるポータブル電源がおすすめです。
断水対策には、以下の方法があります。
・普段から飲料水を多めに保管する
・お風呂の水を常に張っておく
・トイレ用水として雨水を収集するタンクを設置する
大地震では停電や断水が長期化する可能性もあるため、事前に準備をして万が一の時に慌てないようにしましょう。
7.Jackery(ジャクリ)ポータブル電源で停電時も安心して過ごせる

大規模な停電に備えるなら、持ち運びができる蓄電池ポータブル電源がおすすめです。ACコンセントが使えるため、電気ケトルや電子レンジ、冷蔵庫などの家電を動かせます。停電が長期化すると食事の準備が大変になるため、家電が使えると安心して過ごすことが可能です。
Jackery(ジャクリ)は幅広いラインナップのポータブル電源を販売しているメーカーで、取り扱っている製品は以下のような特徴があります。
・静音設計で夜間も安心して使用できる
・排気ガスを発生しないため、室内で安全に使用できる
・軽量・コンパクト設計で避難所への移動時も持ち運びやすい
・1年でわずか5%の自然放電で長期保管に向いている
ソーラーパネルと組み合わせれば、長期間の停電でも太陽光で充電しながら繰り返し使うことが可能です。Jackery(ジャクリ)のポータブル電源で、いつ起こるかわからない災害に備えましょう。
8.耐震補強に関するよくある質問
耐震補強を考える際に、多くの方が抱く疑問について回答します。耐震補強の工事を検討している方は参考にしてください。
●耐震補強工事にデメリットはある?
耐震補強工事には、以下のようないくつかのデメリットが存在します。
|
デメリット |
対策 |
|
工事中の騒音・振動・ほこりで日常生活に影響がある |
・工事期間や作業時間を事前に確認し、養生や清掃の対応を業者に依頼する |
|
仮住まいが必要になる場合がある |
・仮住まいが必要な期間を確認し、準備方法や費用を調べる ・仮住まい費用の補助金を確認する
|
|
耐力壁の増設で間取りの自由度が下がる |
・設計段階で専門家と相談し、最小限の変更で済む内容を選ぶ |
|
補強材や筋交いで外観が変わることがある |
・デザイン性の高い補強材を選ぶ ・外壁リフォームを同時にする |
事前にデメリットを把握し対策すれば、影響を抑えられます。
●耐震補強は自分でできる?
筋交いの補修や接続部の補強など、軽微な耐震補強ならDIYで対応できる場合もあります。一方、耐力壁の増設や基礎の補強、屋根の軽量化などの工事は、建築基準法に基づく設計と施工が必要です。
ただしDIYで間違った補強をすると、かえって建物の安全性を損なう危険性があります。まず専門家による耐震診断を受け、必要な補強内容を確認しましょう。そのうえで、自分でできる範囲と業者に依頼すべき範囲を判断してください。
まとめ
耐震補強が「意味がない」と言われる理由には、効果の実感しにくさや施工不良への不安、費用対効果への疑問などがあります。しかし、ほとんどは正しい知識と対策により解決できます。実際には、耐震補強は建物の倒壊リスクを減らし、地震時の命を守るために効果的な対策です。
また、耐震補強とあわせて家具の固定や備蓄品の準備などの地震対策をすれば、地震の時に安心して過ごせます。停電への備えはポータブル電源を用意して、地震が起きても安心して過ごせるように対策をしておきましょう。