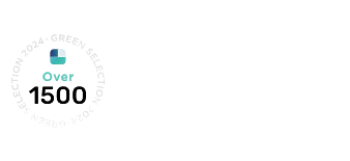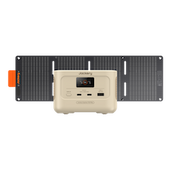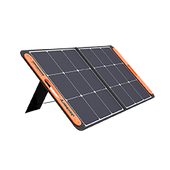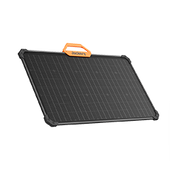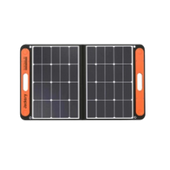1.南海トラフ地震がなかなか起きない理由は?|40年以内の発生確率は90%
南海トラフ地震がなかなか起きない理由は、その発生周期が90〜150年と長いからです。しかし「40年以内に発生する確率は90%」とも言われており、いつ起こってもおかしくない状況であることは間違いありません。ここでは、南海トラフ地震のメカニズムや過去に発生した地震の実例を紹介します。
●南海トラフ地震とは|フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界で起きる

引用元:気象庁
そもそも南海トラフとは、日本列島の南側にあるプレートどうしの溝のこと。フィリピン海プレートとユーラシアプレートが接する、海底の溝状の地形を形成する区域に位置しています。
フィリピン海プレートは、ユーラシアプレートの下に年間数cmの速度で沈み込んでおり、その過程でプレートの境界が固着します。この結果、陸側のプレートが地下に引きずり込まれ、ひずみが蓄積されるのです。そして陸側のプレートが引きずり込みに耐えられなくなると、限界に達して跳ね上がることで南海トラフ地震が発生します。
●南海トラフ地震は90〜150年に1回の周期!過去の地震の発生から次の地震までの間隔が長いから
下記表の過去に発生した南海トラフ地震歴から見ると、南海トラフ地震は、これまで90〜150年の周期で繰り返し発生しているとわかります。この長い周期が、南海トラフがなかなか起きない理由のひとつです。
しかし前回の1946年に発生した昭和南海地震からすでに80年近くが経過しています。いつ地震が起きてもおかしくない状況です。明日来るかもしれないと考えて防災対策を講じることが重要です。
過去に発生した南海トラフ地震の実例:
|
発生した年 |
名称 |
前回の地震からの周期 |
|
684年 |
白鳳(天武)地震 |
不明 |
|
887年 |
仁和地震 |
203年 |
|
1096年 |
永長東海地震 |
209年 |
|
1099年 |
康和南海地震 |
3年 |
|
1361年 |
正平(康安)東海地震 |
262年 |
|
1361年 |
正平(康安)南海地震 |
- |
|
1498年 |
明応地震 |
137年 |
|
1605年 |
慶長地震 |
107年 |
|
1707年 |
宝永地震 |
102年 |
|
1854年 |
安政南海地震 |
147年 |
|
1944年 |
昭和東南海地震 |
90年 |
|
1946年 |
昭和南海地震 |
2年 |
参考:内閣府防災情報のページ
2.南海トラフ地震が起きたらどうなる?|生き残る確率は?

ここまで、南海トラフがなかなか起きない理由を解説してきました。南海トラフ地震が発生した場合、西日本から東日本の太平洋側では震度7クラスの大地震が発生し、10m以上の津波が襲来すると予想されています。詳しく被害予想を見ていきましょう。
●最大震度7クラスの大地震が発生
南海トラフ地震が発生すると、マグニチュード8〜9の最大震度7クラスの強い揺れが予想されます。東日本から西日本の太平洋側にかけて多くの地域で、建物の倒壊やインフラの破壊を引き起こす可能性も。特に、耐震性が不十分な古い建物では、全壊など深刻な被害が発生する恐れがあります。
関連記事:震度7はどれくらいの大きさ?過去に起きた震度7の被害事例や地震対策も紹介
●10m以上の津波が発生

引用:気象庁
南海トラフ地震に伴い、10m以上の津波が発生する可能性があります。マグニチュード9.1を想定した津波被害の予想は下記のとおりです。
|
津波の高さ |
地域 |
|
10m以上 |
静岡県・和歌山県・徳島県・高知県・宮崎県など太平洋沿岸部 |
|
20m以上 |
関東から四国にかけての23市町村 |
|
33m以上 |
静岡県下田市 |
|
34m以上 |
高知県土佐清水市・高知県黒潮町 |
津波が沿岸地域に到達するまでの時間は、最速で地震発生後わずか4〜15分と非常に短いため、事前の警報があっても避難が間に合わないことがあります。そのため、日頃から高台への避難ルートや避難場所を確認しておくことが重要です。いざという時に少しでもロスがないように、準備しておきましょう。
●死者は32.3万人と想定
政府の予測によれば、南海トラフ地震による死者数は最大で32.3万人に達する可能性があるとされています。地震や津波による直接的な被害に加え、火災や交通網の寸断による救助活動の遅れなど二次災害も考慮したものです。その内訳は下記のとおり。
|
項目 |
死者数 |
|
建物倒壊による死者数 |
約82,000人 |
|
津波による死者数 |
約230,000人 (約117,000人) |
|
急傾斜地崩壊による死者数 |
約600人 |
|
地震火災による死者数 |
約10,000人 |
|
ブロック塀、自動販売機の転倒、落下物による死者数 |
約30人 |
|
死者数合計 |
約209,000〜323,000人 |
南海トラフ地震は、津波による死者数が多いのが特徴です。しかし早期避難を実施することで、津波被害を大幅に減少させられます。日頃から防災意識を高め、地域住民が津波警報に迅速に反応し、適切な避難行動をとることが命を守るために重要です。
関連記事:南海トラフが起きても安全な県ランキング|前兆・備え・危険な県も徹底解説
3.南海トラフ地震が来ない県は?生き残る地域は?
南海トラフ地震が発生した場合、どの県が影響を受けにくいのかを考察します。予想される被害エリアや、比較的安全とされる地域について詳しく解説するので、参考にしてみてください。
①予想されている被害エリア

引用元:国土交通省 気象庁「南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ」
静岡県から宮崎県にかけての沿岸地域では、甚大な被害が予想されています。太平洋沿岸の地域を中心に広範囲で震度6弱〜7の強い揺れが観測されるでしょう。また関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸地域では、10mを超える大津波の発生が予想されています。
②北海道・東北地方・日本海側は被害が少ない可能性が高い
北海道や東北地方、日本海側の地域は、南海トラフ地震の影響を比較的受けにくいとされています。これらの地域は震源から距離があるため、直接的な揺れや津波の影響が少ない可能性が高いです。特に北海道は震源から遠く離れているため、直接的な被害が少ないと予想されています。
しかし、完全に安全というわけではありません。これらの地域でも地震が発生する可能性があるため、日頃から地震対策をする必要があります。自治体のホームページをチェックして地域ごとのリスクを理解し、適切な防災対策を行うことが重要です。
関連記事:【北海道編】南海トラフ地震に備えろ!地域別の被害予想と備えまとめ
4.南海トラフ地震から命を守るために個人でやるべきこと

いつ起こるかわからない南海トラフ地震から命を守るためには、万全な防災対策が必要です。ここでは実践すべき項目を6つ紹介します。
①自宅の耐震化
地震による被害を最小限に抑えるために自宅の耐震化を検討するのをおすすめします。まずは今住んでいる家が「旧耐震基準」で建てられた家なのか「新耐震基準」で建てられた家なのかをチェックしてみてください。耐震基準の違いは以下のとおりです。
|
耐震基準 |
震度5強の中地震 |
震度6強程度の大地震 |
|
旧耐震基準 (1931年5月31日以前) |
倒壊・崩壊しない |
規定なし |
|
新耐震基準 (1981年6月1日以降) |
軽微なひび割れ程度にとどまる |
倒壊・崩壊しない |
築年数が43年以上の建物は、旧耐震基準に沿って建てられているため、新耐震基準で建てられた建物に比べて耐震性が不十分である可能性があります。耐力壁を追加したり、基礎を作り替えたりするなどの耐震補強を検討する必要があるでしょう。
②家具の固定
近年の地震による負傷者の30〜50%は、家具類の転倒・落下・移動が原因だとされています。大型家具は倒れると人に危害を加えるだけでなく、避難ルートを塞いでしまうリスクがあるため、壁にしっかりと固定する必要があります。以下の専用の固定金具を使用して、しっかりと固定しましょう。
● L字型金具
● 転倒防止ベルト
● 転倒防止粘着マット
● 家具転倒防止伸縮棒
● 家具転倒防止耐震バー
● 家具転倒防止プレート など
参考:東京都防災ホームページ「自宅での家具類の転倒・落下・移動防止策
家具を固定するだけで、下敷きになり死亡するリスクや、逃げ遅れるリスクが大幅に軽減できます。
関連記事:地震の備えとして家具にできる7つの対策|防災グッズと二段構えで万全
③防災グッズの準備
防災グッズは、家で過ごすためのアイテムと、持ち出し用のアイテムを分けて準備しましょう。持ち出し用の防災グッズは、あらかじめリュックに入れてすぐに持ち出せる場所に保管しておきます。
●家で数日過ごすための防災グッズ リスト:
・飲料水
・食料品
・カセットコンロ
・ポータブル電源
・懐中電灯・LEDランタン
・現金(2万円ほど)
・救急用品・衛生用品・生理用品
●持ち出し用の防災グッズ(防災リュック) :
・飲料水
・食料品
・懐中電灯・ヘッドライト
・モバイルバッテリー
・救急用品(ばんそうこう・包帯・常備薬など)
・衛生用品(マスク・ウェットティッシュなど)
・生理用品
・ヘルメット・防災ずきん
・タオル、防寒用アルミシート
・安眠用品(耳栓・アイマスク)
・衣類
・乳児用品(ミルク・哺乳びん・紙おむつなど)
・貴重品(預金通帳・印鑑・現金)
・医療関係備品(保険証・お薬手帳)
賞味期限や使用期限があるものは、定期的にチェックして更新する必要があります。
関連記事:経験者が語る防災グッズでいらなかったもの5選と本当に必要なものリスト
④自家発電システムの構築

南海トラフ地震発生後は、電力インフラが大きく損傷し復旧に時間がかかるため、長時間の停電が予想されます。そのため、事前に自家発電システムを構築しておくのをおすすめします。
ソーラーパネルと家電に給電できる持ち運び可能な電源装置「ポータブル電源」を組み合わせれば、手軽に自家発電システムを構築可能です。またポータブルソーラーパネルを使えば、避難所に持ち込んで電力を確保できます。
⑤避難場所・避難ルートの確認
津波が発生した場合、どの高台に避難するのかを確実に確認しておいてください。自治体のホームページでハザードマップをチェックし、高台への安全なルートを頭に入れておきましょう。また、複数のルートを確認しておくことで混雑時や通行止めに備えられます。事前にしっかりと頭に叩き込んでおけば、いざという時にも焦らず冷静に避難できるでしょう。
⑥家族での防災訓練|連絡手段の確認
家族で防災訓練を行い、各自の役割や連絡手段を確認しておくのをおすすめします。地震発生時の行動計画を話し合い、それぞれの役割を明確にしておきましょう。誰が子どもやペットを連れて避難するのか、電話回線が混雑した場合の連絡方法など、より具体的に話し合うことが大切です。
関連記事:災害時の連絡手段5選を徹底解説!携帯以外の安否確認方法も紹介
5.長期の停電でも安心!南海トラフの備えにおすすめの非常用電源「Jackery Solar Generator」

南海トラフ地震の停電に備えて、ソーラーパネルとポータブル電源のセット「Jackery Solar Generator」を準備しておくことをおすすめします。
「Jackery Solar Generator」は、創業13年のポータブル電源ブランド「Jackery」が誇る太陽光発電製品。設置工事や複雑なメンテナンスが不要で、手軽にソーラー発電システムを構築可能です。据付型の太陽光パネル&蓄電池とは違い持ち運びが可能で、避難所やキャンプ場などさまざま場所で電力を確保できます。スマホの充電から調理家電・暖房器具の使用まで、この1セットでOKです。
6.まとめ
南海トラフ地震がなかなか起きない理由は、その発生周期が90〜150年と長いためです。しかし前回の地震から80年近く経過しており、いつ起こってもおかしくない緊迫した状況にあることには間違いありません。地震から命を守るためには、万全の防災対策が不可欠です。
まずは、Jackeryの「Jackery Solar Generator」を準備するのをおすすめします。ソーラーパネルで自家発電できるため、停電が長期化しても電源を確保可能です。南海トラフ地震に備え、あなたに合った「Jackery Solar Generator」をご用意ください。