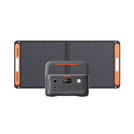1.耐震等級3とは?後悔しない家づくりの基本情報
耐震等級は地震に対する建物の強さを表す制度で、耐震等級3が最も高い性能を示します。耐震等級の仕組みや認定を取る方法、地震に強い建物の条件について解説します。
●耐震等級3は最高ランクの耐震性を証明された建物
耐震等級3は、住宅性能表示制度における最高ランクの耐震性能を示す等級です。数百年に一回程度発生すると想定される規模の地震の1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊しない強度を持つ建物を指します。
耐震等級3は第三者機関の審査を受け、客観的に耐震性能が証明された建物だけが取得できます。震度6強から7の地震が発生しても、建物が倒壊するリスクが低く、継続して住み続けられる可能性が高いです。
参照:国土交通省「耐震性能を等級で確認して、安心の住まいづくり」
●耐震等級3段階の違い
耐震等級は1から3までの3段階に分類され、基準は以下のとおりです。
・耐震等級1:建築基準法の耐震基準と同等(数百年に一度の地震に耐える)
・耐震等級2:建築基準法の1.25倍の強度(長期優良住宅で採用されている)
・耐震等級3:建築基準法の1.5倍の強度(災害時の避難所に相当する)
耐震等級が1ランク上がるごとに、地震に対する建物の耐震能力は大幅に向上します。耐震等級3の建物は警察署や消防署など、災害時の防災拠点となる建物と同じレベルの耐震性能です。
参照:国土交通省「耐震性能を等級で確認して、安心の住まいづくり」
●耐震性能と耐震等級の違い
耐震等級と耐震性能は混同されやすいですが、以下の違いがあります。
・耐震性能:建物が地震に対してどれだけ強いかを示す実際の能力
・耐震等級:耐震性能を第三者機関が評価・認定した結果
耐震等級は住宅性能評価機関による審査と計算に基づいて決められ、設計図書の確認や現場検査が実施されます。一方、「耐震等級3相当」などの表現は、建築会社が社内基準で判断した性能レベルを示すものです。
公的な認定を受けた耐震等級は、住宅ローンの優遇制度や地震保険の割引制度を利用できるため、経済的なメリットも期待できます。しかし、「耐震等級3相当」の建物は正式な認定を受けていない建物で、優遇制度などが使えないため注意が必要です。
●耐震等級3の証明書を取得するには認定が必要
耐震等級3の認定を取得するには、住宅性能評価機関による審査を受けなくてはいけません。認定は、設計段階と建設段階の2つの評価があり、両方をクリアすると正式な認定証が発行されます。
設計性能評価
・内容:設計図書を基に構造計算書や仕様書を審査
・審査期間:約2~3週間
・費用:20~40万円
建設性能評価
・内容:実際の施工が設計通りに行われているか現場検査を実施
・検査方法:複数回の検査を通じて品質を確認
・費用:10〜30万円
すべての検査に合格すると、建設住宅性能評価書が発行され、正式に耐震等級3の認定住宅と評価されます。
●耐震等級を決める4つのポイント
耐震等級の高い建物を建てるには4つのポイントがあります。バランス良く取り入れることで、地震に強い住宅を建てることが可能です。
①建物が軽いか
地震の揺れによって建物に加わる力は、重さに比例して大きくなるため、建物が軽いほど地震の影響を受けにくいです。
木造住宅は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比べて軽いため、同じ地震の力を受けても建物にかかる負担を抑えられます。他にも、以下の工夫で建物の重量を抑えることが可能です。
・屋根材は瓦よりスレートや金属屋根にする
・内装材や外装材に軽い素材を使う
・不要な壁や柱を減らす
ただし、軽量化を重視しすぎると強度不足を招くおそれがあるため、設計者と相談しながらバランスを取りましょう。
②耐力壁が多いか
耐力壁は地震の横揺れに抵抗する壁で、数が多いほど建物の耐震性能は高まります。耐震等級3の建物には、法律で定められた必要量の1.5倍以上が必要です。
種類には筋交いを入れた壁、合板を張った壁、ダンパーを組み込んだ壁などがあります。強度の高い壁を使えば壁の数を減らせますが、その分コストが上がるためバランスを取る必要があります。
また、大きな窓や吹き抜けがある家では耐力壁を置ける場所が限られるため、設計の段階からデザインと耐震性の両方を意識しなくてはいけません。
③耐力壁や耐震金物がバランス良く配置されているか
地震による倒壊を防ぐには、耐力壁をバランスよく配置する必要があります。建物の中心と耐力壁の位置がずれると、地震のときに建物がねじれ、特定の部分に負担が集中して壊れやすくなります。理想は外側と内側にまんべんなく配置し、四隅を補強することです。
また、柱と梁や土台のつなぎ目には専用の金具を使い、確実に取り付けることで建物全体の強さを高められます。
④基礎や床の耐震性能は問題ないか
基礎が弱いと、地震で建物が傾いたり沈んだりする恐れがあり注意が必要です。基礎には布基礎とベタ基礎があり、ベタ基礎は建物全体を面で支えるため耐震性に優れています。地盤調査を行い、必要なら地盤改良をして状態に合った基礎を選ぶことが必要です。
また、床も地震の力を壁に伝える役割があるため、地震に強い素材を選ばなくてはいけません。2階の床や屋根下の剛性が不足すると建物がゆがみやすくなるため、合板を使った剛床工法や火打ち梁で補強し、耐震性を高めます。
関連人気記事:【家族で生き抜く】災害に強い家の特徴とは?間取り・設備・メーカーを解説
2.耐震等級3は意味ない?後悔する?デメリットと注意点3つ

耐震等級3の建物は建築費用が高く、間取りに制限もあります。また、実際に地震が起きないとメリットを感じにくいため、「等級3にする意味ない」との声も聞かれます。
耐震等級3にするデメリットを事前に確認して、後悔しない家づくりをしましょう。
①建築費用が高くなりやすい
耐震等級3の建物を建てる場合、通常の建築費用に加えて追加の費用が発生します。一般的に、耐震等級1から等級3にグレードアップすると以下の費用が追加でかかります。
・建築費が5~10%増額
・構造計算書の作成費用:10~30万円
・住宅性能評価の申請・審査費用:20~40万円
費用を合計すると小さな金額ではないため、地震による被害のリスクと慎重に比較検討しましょう。
②間取りに制限がある
耐震等級3の建物は、間取りの自由度がある程度制限されます。耐力壁を正しく配置しなければならないため、大きな開口部や広いリビング空間が難しくなる場合があります。
また、ビルトインガレージや店舗併用住宅のような1階に大空間が必要な建物では、上階を支える構造の工夫をするために設計の難易度が上がる傾向です。ただし、最近では技術の進歩により、制限を緩和する方法も開発されています。
③着工前に依頼しないといけない
耐震等級3の認定を取得するには、着工前の段階で申請手続きを開始する必要があります。建築確認申請と同時期に住宅性能評価の申請を行うため、後から等級を上げることは原則不可能です。
建築が始まってから「やっぱり耐震等級3にしたい」と思っても、構造計算のやり直しや設計変更が必要となり、大幅な工期の延長とコストの増加を招きます。最悪の場合、すでに施工した部分の取り壊しが必要になることもあります。
設計契約を結ぶ前に、ハウスメーカーや工務店に耐震等級3対応できるか確認してください。対応可能な場合でも、標準の仕様でどの程度の耐震性能があるのか、等級3にするための追加費用はいくらかなど、具体的な情報を入手しましょう。
関連人気記事:耐震補強は「意味がない」と言われる理由と本当に必要な地震対策を解説
3.耐震等級3は必要か?4つのメリット
デメリットがある一方で、耐震等級3にはメリットも存在します。耐震等級3を選ぶことで得られる4つのメリットを確認して、メリット・デメリットのバランスを確認しましょう。
①大地震でも建物が損壊しにくい
耐震等級3の最大のメリットは、大地震でも建物が壊れにくく安全性が高いことです。震度7クラスでも大きく損傷する可能性が低く、家族と財産を守れます。
2016年の熊本地震では震度7の地震が2回発生しましたが、耐震等級3の住宅の約87%がほぼ無被害で、多くは軽微な損傷にとどまり居住を継続できました。一方、等級1相当では約4割が損壊し、大破や倒壊も確認されています。
耐震等級3の建物では地震後も軽微な補修で済む可能性が高く、早期復旧が期待できます。
参照:国土交通省「耐震性能を等級で確認して、安心の住まいづくり」
②住宅ローンの金利優遇制度を受けられる
耐震等級3の住宅は、住宅ローンで金利優遇を受けられる点も大きなメリットです。
代表的なのが住宅金融支援機構の「フラット35S(金利Aプラン)」で、当初5年間は金利が0.5%下がります。例えば3,000万円を35年ローンで借りた場合、返済総額の差は約80万円です。
さらに民間銀行や信用金庫でも、等級3の住宅に対して0.1~0.3%の金利優遇を行う例が増えています。複数の金融機関の条件を比較すれば、有利な条件で住宅ローンが組めるでしょう。
③地震保険料を抑えられる
耐震等級3の認定住宅は、地震保険料の割引対象です。耐震等級割引として、等級3の場合は保険料が50%割引されるため、大きな経済的メリットが期待できます。
具体的な割引額を試算してみましょう。木造住宅で建物評価額2,000万円・家財500万円の地震保険に加入する場合、以下の計算ができます。
・年間保険料は地域によって異なるが、東京都は約5万円程度
・耐震等級3の50%割引が適用されれば、年間2.5万円・30年間で75万円節約
耐震等級3であれば、保険料負担を抑えながら、万が一の備えを充実させられます。
④資産価値が上がりやすく売却しやすい
耐震等級3の住宅は、資産価値が高く売却しやすい点もメリットです。中古住宅の市場では耐震性能が一つの評価ポイントで、高い等級の住宅は人気が高く、有利な条件で取引されやすくなります。
4.耐震等級3を実現できるハウスメーカーの選び方

耐震等級3の住宅を建てる際、施工技術や認定取得の有無が会社によって異なるため、ハウスメーカー選びは慎重に行う必要があります。選ぶときのポイントは、以下のとおりです。
|
ポイント |
チェック内容 |
|
標準仕様の耐震性能 |
・大手メーカーでも「相当」と表示している場合は、認定取得の有無や追加費用を確認する |
|
施工実績・技術力 |
・耐震等級3の住宅を年間何棟手がけているか、自社で構造計算できるか確認する |
|
アフターサービス |
・地震被害時の対応体制、定期点検の頻度・内容、保証期間を確認する |
総合的に判断し、信頼できるハウスメーカーを選べば、安心して耐震等級3の家を建てられます。
5.大地震には耐震等級3だけでは不十分!必要な防災対策3選
耐震等級3の住宅でも、地震への備えは不十分です。住宅の耐震性能とあわせて実施すべき3つの地震対策を解説します。
①家具の固定をして家の中の損壊を防ぐ
地震のときは建物が無事でも、家具の転倒でケガをするリスクがあります。そのため、以下のような家の中を安全に保つ対策も必要です。
・大型の家具や家電を金具や突っ張り棒で固定する
・金具が取り付けられない場合は耐震マットを敷く
・食器棚やガラス扉の家具には、飛散防止フィルムを貼る
・観音開きの扉には、耐震ラッチを取り付けて揺れによる扉の開放を防ぐ
特に寝室や避難経路上の家具は、命を守るために優先して対策しましょう。家具の固定は簡単に行える地震対策です。
②食料や水などの備蓄品で長期災害に備える
大地震後はライフラインが止まり物資が不足するため、最低3日分、できれば1週間分の食料と水を備えることが推奨されています。
水は1人1日3リットルが目安で、4人家族なら3日で36リットル、1週間で84リットルが必要です。食料は缶詰やレトルト食品、乾パンなど保存が利くものを用意し、ローリングストック法で日常的に入れ替えながら備蓄すると良いでしょう。
また、以下の防災グッズも必須です。
・簡易トイレ、救急用品
・懐中電灯、ラジオ、乾電池
・季節に応じた防寒具や冷却グッズ
・家族構成に応じた乳幼児用品、介護用品、常備薬
備蓄品は定期的に点検し、期限切れは交換して、万が一の災害に備えてください。
③停電や断水に備えて防災グッズを用意する
電気やガス、水道などのライフライン停止に対応するため、代替手段を確保する必要があります。停電に備えるには、以下の対策がおすすめです。
・常にモバイルバッテリーを持ち歩く
・懐中電灯やランタンを用意する
・ポータブル電源を準備する
大地震では長期間の停電も予想されるため、ポータブル電源とソーラーパネルがあると繰り返し充電できるため安心です。
また断水に備えて、簡易トイレや給水タンク、ポリタンクの用意も役立ちます。
関連人気記事:地震の不安を吹き飛ばす13の地震対策!すぐ動ける準備はできてる?
6.Jackery(ジャクリ)ポータブル電源があれば地震で停電しても安心

地震による停電に備えるには、持ち運べる蓄電池であるポータブル電源がおすすめです。ポータブル電源はACコンセントでの出力ができるため、以下のような家庭内にあるさまざまな家電を動かせます。
・調理家電で食事の準備
・扇風機や電気毛布で寒暖対策
・情報収集に必須のスマホやパソコンの充電
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源は、1年間でわずか5%の自然放電と電池残量の減りが少なく、長期保管に向いています。また、業界トップクラスの軽量・コンパクトモデルで保管場所にも困りません。
地震の備えは家の倒壊を防ぐだけでなく、停電などのライフラインの停止にも対応できる準備が必要です。Jackery(ジャクリ)のポータブル電源を用意して、万が一の災害時も安心して生活が送れるように備えましょう。
7.耐震等級3に関するよくある質問
耐震等級3について、多くの方が疑問に思う点をまとめました。地震に強い家づくりの参考にしてください。
●「耐震等級3相当」とは?
「耐震等級3相当」とは耐震等級3と同等の耐震性能がありますが、住宅性能評価機関による正式な認定を受けていない建物のことです。
実際の耐震性能は期待できますが、住宅ローンの金利優遇制度や地震保険料の割引制度を利用できません。また、中古住宅として売却する際も、客観的な品質の証明がないため評価が下がる可能性があります。
ハウスメーカーや工務店が「相当」という表現を使う理由は、認定取得の手間やコストを削減するためです。正式な耐震等級3の認定を希望するなら、契約前に伝え、認定取得を前提とした契約を結びましょう。
●長期優良住宅に耐震等級3は必要?
長期優良住宅の認定要件は「壁量計算または許容応力度計算による耐震等級2以上」で、認定取得に耐震等級3は必須ではありません。
しかし、より高い安全性を求める場合や、住宅ローンの優遇制度を最大限活用したい場合には、耐震等級3の取得を検討しましょう。
参照:国土交通省「長期優良住宅のページ」
●熊本地震で耐震等級3の建物は倒壊した?
2016年の熊本地震において、耐震等級3の認定を受けた建物で倒壊したものは報告されていません。
震度7を2回記録した益城町でも耐震等級3の建物の87%は被害を受けず、残りの住宅も軽微な被害にとどまっています。
参照:国土交通省「耐震性能を等級で確認して、安心の住まいづくり」
●長期優良住宅の認定において耐震等級3が必須となったのはいつからですか?
長期優良住宅の認定において、耐震等級3が必須となったことは基本的にありません。制度開始当初から現在まで、耐震等級2以上が要件となっています。
2009年の長期優良住宅認定制度スタート時から、耐震等級2以上が基準です。
2022年10月~2025年3月の期間のみ「壁量計算に基づく申請の場合は耐震等級3が原則必要」(暫定措置)という運用がありました。
2025年の制度改正では計算方法に関する要件が明確化され、「壁量計算または許容応力度計算による耐震等級2以上」に変更され等級3は必須ではありません。
参照:国土交通省「長期優良住宅のページ」
●耐震等級3は大地震に何回耐えられますか?
耐震等級3は、震度6強から7の地震の1.5倍の力に対して「倒壊・崩壊しない」ことを基準としていますが、具体的な耐えられる回数は不明です。
熊本地震の事例では、震度7を2回経験しても、耐震等級3の建物は大きな損傷を受けませんでした。理論上は、定期的にメンテナンスを行えば、複数回の大地震にも耐えられる設計となっています。ただし、想定を超える巨大地震や、特殊な揺れ方をする地震に対しては、被害を完全に防ぐことは困難です。
耐震等級3は「絶対に壊れない」わけではありません。「壊れにくく、命を守れる可能性が高い」と考えておくのが良いでしょう。
まとめ
耐震等級3は建築基準法の1.5倍の耐震性能を持つ最高等級で、大地震時の建物損壊リスクを大幅に軽減できます。ただし、建物の耐震性だけでは地震から完全に身を守れません。
家具の固定や備蓄品の準備、停電対策などの防災対策をあわせて行うことが地震の備えには必要です。
停電への備えには、ポータブル電源を準備しておけば安心して過ごせます。長期保管に向いているJackery(ジャクリ)のポータブル電源を用意して、万が一の災害に備えましょう。