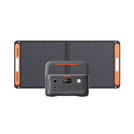1.首都直下型地震はいつ来る?定義と想定される被害規模
首都直下地震は、首都圏を直撃する大規模地震で、政府が警戒している災害の1つです。発生確率や被害想定を解説します。
●「日本終了」とも言われる首都圏直撃の大規模地震の特徴
首都直下地震は、首都圏の地下にある活断層やプレート境界で発生するマグニチュード7クラスの地震を指します。主な特徴は以下のとおりです。
|
項目 |
内容 |
|
震源地 |
東京23区を中心とした首都圏 |
|
特徴 |
政治・経済機能が集中する日本の中枢部を直撃する可能性がある |
|
想定される被害 |
建物倒壊・火災・津波などが同時に発生し、短時間で被害が広がる危険性 |
人口密度が極めて高い地域での発生により、建物倒壊や火災などの被害が一気に拡大する危険性があります。
首都機能の停止は全国の経済活動にも深刻な影響を及ぼすため、「日本終了」という表現で危機感が示されています。
参考:東京都防災ホームページ|首都直下地震等による東京の被害想定 報告書
●発生確率は30年以内70%!「いつ発生するのか」を最新予測
政府の地震調査委員会は、首都直下地震の発生確率を今後30年以内に70%と発表しています。発生確率は、過去の地震発生パターンやプレートの動きを分析した結果です。
マグニチュード7程度の地震が首都圏で発生する可能性は、過去の統計をもとに算出されています。前回の関東大震災から100年近くが過ぎ、次の発生への危機感が強まっています。
地震の発生時期を正確に予測することは現在の科学技術では困難とされており、いつ発生するかは不明です。ただし、70%という高い確率は決して軽視できる数字ではありません。
●死者2.3万人・経済損失95兆円と試算される被害シミュレーション
内閣府による首都直下地震の被害想定は、以下のとおりです。
|
項目 |
想定内容 |
|
死者数(最大) |
約2.3万人 |
|
建物被害 |
約61万棟 |
|
電力 |
発災直後に約5割の地域で停電 |
|
上下水道 |
都区部で約5割が断水 |
|
経済損失 |
建物等の直接被害:約47兆円 生産・サービス低下による間接被害:約48兆円 |
首都直下地震が発生すれば、建物被害約61万棟、経済損失95兆円に及ぶと試算されています。インフラや交通も長期にわたり麻痺し、社会全体に深刻な影響を与えるでしょう。
参照:内閣府|特集首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)‐内閣府防災情報のページ
関連人気記事:首都直下型地震が来ない確率は?安全な県や助かるには何を対策すべきか解説
2.首都直下型地震の津波はどこまで及ぶのか?想定範囲を解説

首都直下型地震による津波は、主に東京湾の臨海部と関東沿岸部で被害が想定されています。
●東京都内で津波が想定される臨海部(江東区・品川区など)
東京湾に面した臨海部では、首都直下型地震による津波被害が想定されており、とくに以下の地域では浸水リスクが高くなります。
・江東区
・大田区
・品川区
3つの地域は多くが埋立地であり、もともと海だった場所を人工的に陸地化したため、津波に対して脆弱な地盤構造です。埋立地特有のリスクは以下のとおりです。
・地震時に液状化現象が発生しやすい
・液状化と津波被害が同時に起こる可能性がある
・地盤の沈下や傾斜によって浸水範囲が広がる危険がある
・標高が低いため津波の影響を受けやすい
江戸川区や中央区など東京湾沿いの各区域でも同様の特徴があり、事前の備えが欠かせません。
●千葉県房総半島・神奈川県三浦半島など関東沿岸部の津波リスク
関東沿岸部は東京湾の外側で太平洋に面しているため、湾内よりも津波の危険性が高いです。津波到達が早い房総半島や三浦半島では、震源域に近いため迅速な避難行動が求められます。
また、海岸沿いには住宅地も密集しており、地域住民と観光客の両方への対策が求められます。とくに以下の人気観光地は、平日でも多くの観光客が訪れているため注意が必要です。
・鎌倉(海岸エリアや観光客が集まる由比ヶ浜など)
・江の島(観光スポットが集中し、観光客が多い)
・三浦海岸(海水浴場として有名で夏季はとくに混雑)
・館山市(館山湾・北条海岸)
・鴨川市(鴨川シーワールド周辺・鴨川海岸)
・勝浦市(勝浦海水浴場・勝浦港周辺)
海水浴場や港湾施設では、津波警報の発表を待たずに強い揺れを感じた時点で高台へ避難しましょう。
3.首都直下型地震の津波をハザードマップで確認すべきポイント
津波から身を守るためには、事前の備えに加えて複数のツールを利用した確認が不可欠です。ハザードマップの種類と利用方法を確認していきましょう。
●東京都「東京マイ・タイムライン」で被害を想定した確認方法
東京マイ・タイムラインは、災害発生前に家族一人ひとりの避難行動を時系列で整理できるツールです。津波だけでなく、地震による火災や停電といった複合災害も想定した行動計画を策定できます。行動計画の策定方法は以下のとおりです。
|
ステップ |
内容 |
ポイント |
|
1. 準備 |
ガイドブックとシールを用意 |
家族で一緒に取り組むことが大切 |
|
2. 行動整理 |
「いつ」「誰が」「何をするか」を決める |
例:震度5弱 → 津波警報確認・避難準備開始 |
|
3. 家族に合わせる |
高齢者や子どもに合わせて避難時間を調整 |
早めの行動で安全性を高める |
|
4. 計画完成 |
シールを貼ってタイムラインを仕上げる |
津波だけでなく火災や停電も想定に含める |
|
5. 見直し・共有 |
定期的に更新して家族全員で共有 |
環境変化や最新情報に合わせて修正する |
計画は一度作って終わりではなく、定期的に見直して家族全員で共有する必要があります。災害は予測できないからこそ、早めに備えを進めておきましょう。
●国土地理院「重ねるハザードマップ」で浸水想定を調べる方法
重ねるハザードマップは、住所を入力するだけで津波浸水想定エリアを地図上で詳細に確認できる国土地理院の無料ツールです。津波以外にも洪水や土砂災害、高潮といった複数の情報を同時に表示できるため、災害リスクの把握に役立ちます。
使い方は以下のとおりです。
1.サイトのトップページを開き「住所から探す」を選択する
2.調べたい住所を入力して検索する
3.「災害種別で選択」から津波アイコンをクリックする
4.色分けされた浸水想定区域が表示されるのでリスクを確認する
5.「すべての情報を選択」から避難所を選んで位置を確認しておく
スマホからも利用可能で、外出先でも現在地周辺のリスクをすぐに調べられる便利さがあります。
参考:ハザードマップポータルサイト|身のまわりの災害リスクを調べる
●横浜市・千葉市など地域別ハザードマップを確認するポイント
各自治体が作成する地域別ハザードマップでは、国の想定よりもさらに詳細な浸水深や避難所情報が公表されています。各自治体のハザードマップのメリットは以下のとおりです。
|
メリット |
内容・具体例 |
|
地域特性を反映 |
例:横浜市:区ごとの津波避難ビルを確認可能 |
|
生活動線の安全確認 |
居住地だけでなく、職場・通学先周辺もチェックでき、外出時の安全確保につながる |
|
停電時でも利用可能 |
・冊子版とウェブ版を提供 ・冊子版は停電時にも確認できる |
|
避難計画に役立つ |
避難所の収容人数や開設条件を把握でき、混雑を避けた計画づくりに活用可能 |
地域特性を踏まえた詳細な浸水想定や避難施設の情報に加え、生活動線や外出先での安全確認にも活用できます。
年に一度は最新版への更新を確認し、家族全員がマップの見方を理解しておきましょう。
4.首都直下型地震による津波の到達時間と想定される高さの目安

首都直下型地震の津波は地域ごとに到達時間や高さが異なるため、早めの避難行動が安全につながります。
●東京都臨海部は3〜7分で到達、津波高は最大2m程度
東京湾北部地震では、波源域に近い南側で津波の到達時間が3〜7分程度と極めて短い時間です。避難準備を考慮すると残された時間は少ないため、揺れを感じたら速やかに行動を始めましょう。
津波高は東京湾沿岸で最大2.0m程度の想定ですが、都市部では低い津波でも深刻な被害をもたらします。大人の腰程度の高さでも水流の力により歩行困難となり、港湾施設では荷役用クレーンやコンテナが流される場合もあるでしょう。
地下街が浸水すると避難路が使えなくなる可能性があるため、速やかに地上へ出る行動が必要です。
参考:東京都防災ホームページ|首都直下地震等による東京の被害想定 ―概要版―
●千葉県外房や神奈川県三浦半島の津波高は6〜8m
太平洋に直接面した千葉県外房や神奈川県三浦半島では、津波高が6〜8mと東京湾内の約4倍の規模になる想定です。2階建て住宅の屋根に相当するため、平地の建物は甚大な被害の可能性があります。
銚子港や三浦港といった漁港では停泊中の漁船が陸上に打ち上げられ、住宅地では家屋の全壊や流失が相次ぐ恐れがあります。
また、津波は内陸部へ数キロメートル遡上するため、海岸から離れた場所でも安全ではありません。命を守るためには、高台や避難タワーへの迅速な避難が不可欠で、複数の経路を事前に確認しておきましょう。
参考:内閣府防災情報|首都直下地震の被害想定 対策のポイント
関連人気記事:地震から津波までの時間は?過去の事例とシミュレーションで学ぶ防災対策
5.首都直下型地震と南海トラフ地震はどっちがやばい?津波被害想定を比較
日本で最も警戒される巨大地震である首都直下地震と南海トラフ地震は、それぞれ異なる特徴を持ちます。両者の津波被害の違いを確認しましょう。
●発生確率は首都直下70%・南海トラフ80%!津波は南海トラフがより深刻
30年以内の発生確率は首都直下地震が約70%、南海トラフ地震が約70〜80%とほぼ同等の高い数値です。被害の規模を比較した内容は以下のとおりです。
|
項目 |
首都直下地震 |
南海トラフ地震 |
|
被害の範囲 |
東京を中心とした6都県 |
24都府県に広がる広範囲 |
|
被害の性質 |
人口密集地への直撃で都市機能が麻痺する恐れ |
津波による被害が広域に及ぶ |
|
想定避難者数 |
約300万人 |
約650万人 |
首都直下地震では東京湾内や関東沿岸部で津波が発生し、臨海部の港湾施設や地下街に被害をもたらす恐れがあります。一方、南海トラフ地震では24都府県に被害が広がり、津波での死者は最大で約21万人と予測されます。震源地が海岸となる南海トラフ地震の方が、広域にわたって深刻な津波被害をもたらす想定です。
参照
内閣府経済社会総合研究所|南海トラフ巨大地震による想定津波高と 市区町村間人口移動の実証分析
内閣府防災情報|南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について
東京都防災ページ|東京都の新たな被害想定~首都直下地震等による東京の被害想定~
●南海トラフは太平洋沿岸に津波が広範囲、首都直下は関東沿岸に限定
津波被害の及ぶ範囲を比べると、以下のようになります。
|
項目 |
南海トラフ地震 |
首都直下地震 |
|
津波の範囲 |
関東~九州の太平洋沿岸 (376市町村) |
東京湾内および関東沿岸部 |
|
津波の高さ |
最大10m超 |
最大2m程度 |
|
被害対象 |
沿岸部の住宅地・商業施設に大規模な被害 |
港湾施設の停止、地下街の浸水 |
|
特徴 |
広範囲で津波被害の恐れがある |
都市圏に集中し首都機能が麻痺する恐れがある |
南海トラフ地震では、静岡県から九州にかけて広範囲での被害が予測されています。津波は3階建てビルを超える高さで、沿岸部の住宅地や商業施設に大規模な被害をもたらすでしょう。
一方、首都直下地震の津波は東京湾内や関東沿岸部に限定されるものの、都市圏への影響は極めて深刻です。被害範囲は限定されていますが、日本の中枢への直撃という点で首都直下地震の脅威は計り知れません。
参考
内閣府経済社会総合研究所|南海トラフ巨大地震による想定津波高と 市区町村間人口移動の実証分析
内閣府|南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループにおける検討状況について
東京都防災ホームページ|首都直下地震等による東京の被害想定 ―概要版―
6.首都直下型地震で助かるには?事前対策と避難のポイント

首都直下型地震から身を守るには、事前の備えと避難計画を用意しておく必要があります。
●発生直後の行動を想定した避難タイムラインを作る
地震発生時の混乱を避けるため、家族で役割分担を以下の例のように決めておきます。
・お父さんはガスの元栓と電気のブレーカーを確認
・お母さんは子どもの安全確保と避難準備
・中学生以上の子どもは非常持出袋の準備
また役割を決めるだけでなく、行動の順序も共有しておく必要があります。初動の動きは以下の内容を家族で共有し備えましょう。
1.安全を確保する
2.火の始末をする
3.避難の可否を決める
地震後は自宅の安全を確認し、問題なければ在宅避難、被害があれば即座に避難所へ行くと決めておけば迷わずに行動できます。作成したタイムラインは定期的にチェックし、家族で避難行動を練習しておくと安心です。
●自宅から最寄りの避難所・高台ルートを家族で共有する
家族が災害時に別々の場所にいても安全に集合できるよう、徒歩で利用できる避難経路を事前に確認しましょう。避難経路を2つ以上設定し、実際に歩いて所要時間や危険箇所を把握します。
津波の危険がある地域では、海抜10m以上の高台や避難ビルへの経路を確認し、集合場所も事前に決めておきます。
また、平日昼間と夜間・休日で集合場所を変えるなど、状況に応じた計画を立ててください。
●災害時に命を守るための防災グッズを準備する
命を守るための備えとして、以下の防災グッズを準備しましょう。
・1人あたり最低3日分の食料
・水(1日3リットル)
・簡易トイレ
・救急用品
・持病の処方薬
また、停電が長引く恐れがある首都直下地震では、コンセントが使える持ち運び式蓄電池「ポータブル電源」の準備が欠かせません。ポータブル電源があれば、停電中もスマホを充電して安否確認や情報収集ができ、さらに冷蔵庫を稼働させて食材の保存も可能です。
7.首都直下型地震に備えた「ポータブル電源」を選ぶならJackery(ジャクリ)がおすすめ

首都直下型地震の備えとして非常電源を選ぶなら、Jackery(ジャクリ)のポータブル電源がおすすめです。
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源は震度7の揺れにも対応できる耐震性能を備えており、首都直下地震のような大規模災害時でも安心して使用できます。ソーラーパネルのエネルギー変換効率は業界最高峰の最大25%を誇り、災害による長期停電時でも太陽光による電力確保が可能です。
首都直下型地震への備えには、信頼性の高いJackery(ジャクリ)ポータブル電源を導入しましょう。
まとめ
首都直下型地震の津波は東京湾内で最大2m程度、到達時間3〜7分と極めて短時間です。関東沿岸部では6〜8mの津波が予想され、南海トラフ地震と比較すると被害範囲は限定的ですが都市機能への影響は深刻となります。
命を守るには、避難タイムラインの作成や避難ルートの確認、防災グッズの備えなどの事前準備が欠かせません。
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源があれば、長期停電時でも電力確保が可能です。首都直下型地震への万全な備えとして、ぜひJackery(ジャクリ)ポータブル電源を取り入れましょう。