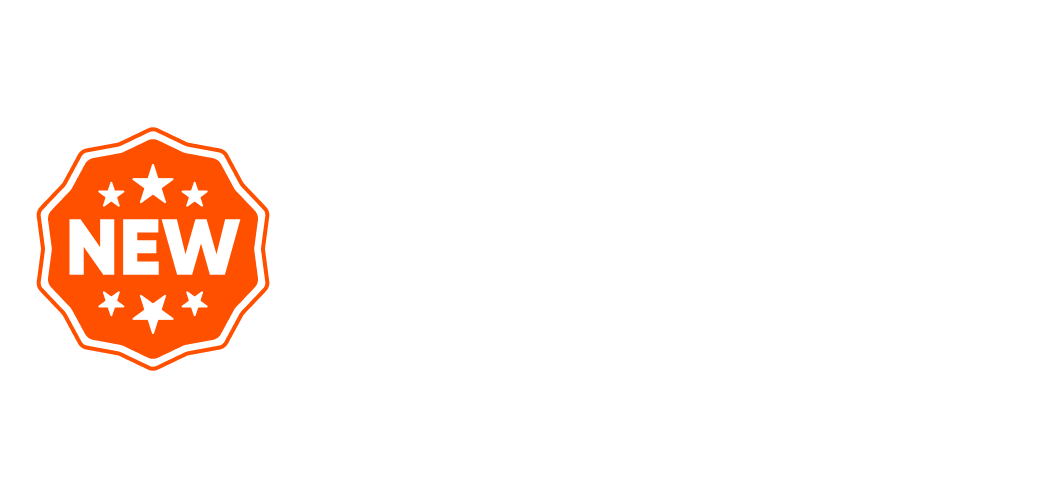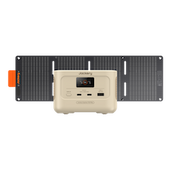1.防災倉庫とは?設置場所と役割・使い方
防災倉庫は災害発生時に必要となる備品を備蓄しておくための施設ですが、設置場所や使い方などをよく知らない方が多いです。
そこで防災倉庫の設置場所や役割、使い方を詳しく紹介していきます。
●防災倉庫は学校・公園・自治会施設を中心に設置されている
防災倉庫は、災害時に多くの人が避難しやすい以下のような場所に設置されています。
・学校
・公園
・自治会施設
とくに小学校などの学校は、避難所として活用されることが多く地域住民が集まりやすいため、防災物資の保管場所に最適です。誰でも利用しやすい場所に防災倉庫を設置することで支援が行き届きやすくなり、地域全体の防災力アップが期待できるでしょう。
●防災倉庫は「共助」の基盤としての役割がある
防災倉庫には、共助の基盤としての役割があります。災害発生直後には、行政からの支援が行き届くまでに時間がかかることも多く、地域住民同士で助け合う「共助」が欠かせません。
防災倉庫には非常食や毛布など共助に必要な物資が保管されているため、避難所での生活を地域住民同士で支え合うことができるのです。物資を共有しながら助け合い、混乱の中でも地域の安全と安心を守っていきましょう。
●防災倉庫の使い方と鍵の保管方法
防災倉庫を使用する際には、鍵が必要になります。自治体の代表者や防災組織の責任者が管理している場合が多いです。
例えば、千葉県の習志野市では小学校内の防災倉庫の鍵を各学校や自治体の代表者が所持し、災害発生時に迅速に鍵が開けられる体制が整えられています。
さらに近年では、震度5弱以上の揺れを感知すると自動的に鍵の入ったボックスが開錠される「感震式の鍵ボックス(防災BOX)」を導入するケースも見られるようになりました。この取り組みは鍵の管理者がすぐに駆けつけられない場合に備えた対策として、内閣官房の「国土強靱化 民間の取組事例集」にも掲載されています。
災害時に円滑な共助を行うために、倉庫の場所だけでなく鍵の保管方法や使い方も地域で共有しておきましょう。
参考:習志野市ホームページ
参考:内閣官房
関連人気記事:防災グッズは外に置くべきか?注意点とその他おすすめの置き場所も紹介
2.災害に備えよう!防災倉庫の中身チェックリスト

防災倉庫には、災害時に必要なものを備えておく必要があります。
ここでは、災害時に必要となる防災倉庫の中身を紹介していきます。
●食料・飲料水:缶詰・カップ麺・レトルト食品など
防災倉庫には、災害時でもすぐに食べられる食品や飲料水の備蓄が必要です。調理に手間がかからず、長期保管できる以下のようなものを備蓄しましょう。
・飲料水(1人1日3リットルを目安)
・缶詰(魚・肉・果物など)
・レトルト食品(カレー・おかゆ・スープなど)
・カップ麺、インスタント麺
・クラッカー、乾パン
・栄養補給食品(栄養バー、ゼリー飲料など)
・アレルギー対応食
・粉ミルク、ベビーフード
災害発生時は支援物資が届くまでに数日かかることを想定して1人あたり最低でも3日分、可能であれば7日分を備蓄しておくと安心です。
●生活用品:毛布・簡易トイレ・生理用品など
災害時には食料や水だけでなく、生活用品の備蓄も欠かせません。地域住民や学校・公共施設の利用者など複数人の避難生活を想定し、以下のような生活用品を防災倉庫に備蓄しましょう。
・毛布、アルミブランケット
・簡易トイレ、携帯トイレ
・トイレットペーパー、ティッシュ
・生理用品
・ウェットシート
・ゴミ袋、ポリ袋
・付き合い捨ての食器やコップ、割り箸
・携帯ラジオ、乾電池
生活用品は、想定する利用者数に応じた量を備蓄する必要があります。とくにウェットシートなどの衛生用品やトイレ用品は早期に不足しやすいため、余裕を持った量を備蓄しておきましょう。
●医療用品:包帯・マスク・消毒液など
災害時は怪我や体調不良が起こりやすく、医療機関もすぐに利用できるとは限りません。そのため、防災倉庫には応急処置に対応できる下記のような医療用品を揃えておきましょう。
・包帯、ガーゼ、止血パッド
・絆創膏、テープ類
・消毒液
・使い捨て手袋
・マスク
・体温計
・冷却シート、使い捨てカイロ
・三角巾、ハサミ、ピンセットなどの応急処置用具
・AED(自動体外式除細動器)
軽い怪我の手当や感染予防に役立つ基本的なアイテムを中心に、「利用者数×数日分」を目安に備蓄しておくのがおすすめ。定期的に使用期限や数量を点検し、不足や劣化がないように管理しておくといざという時に役立ちます。
●救助資材・機材:ヘルメット・担架・ロープなど
災害時に負傷者の避難や安全な避難ができるように、防災倉庫には基本的な救助資材・機材を備える必要があります。誰でも扱いやすく、多目的に使える以下のようなものを備えておくと安心です。
・ヘルメット
・担架
・ロープ
・バール、ジャッキ
・のこぎり、ハンマー、スコップ
・発電機
・懐中電灯
・防塵マスク、ゴーグル
・蛍光ベルト
これらの資材は、避難所運営者や地域の防災担当者が迅速に使えるように収納場所や使用方法をあらかじめ知らせておくのがポイント。また年に1回程度、防災訓練で実際に使ってみるなど、いざというときに慌てない準備をしておきましょう。
●非常用電源:ポータブル電源
災害時には停電が長期間続くこともあり、明かりの確保・スマホやテレビでの情報収集・冷暖房器具の使用などに電力が必要になります。そんなときに役立つのが、持ち運び可能な大容量バッテリー「ポータブル電源」です。
ポータブル電源があれば、停電時などの電気が使えない場合にも家電への電力給電ができるようになります。ソーラーパネルと併用すれば停電が長期化した場合でも繰り返し充電できるため、避難生活を支える心強いアイテムとなってくれるでしょう。
関連人気記事:防災バッグの中身に最低限必要なものとは?必要になる状況を考えて厳選することが大切
3.画像で見る!防災倉庫の中身
防災倉庫にどのような物資が備えられているのか、実際のイメージがあるとよりわかりやすくなります。
そこで防災倉庫の中身を画像と共に、よりわかりやすく解説していきます。
●自治会の防災倉庫の中身


引用元:内閣府
自治体が管理する防災倉庫には、避難想定人数に合わせた備蓄品が備えられていることが多いです。例えば港区では、避難想定人数に基づいて2日分の食糧を備蓄しており、高齢者や乳幼児向けに白粥や粉ミルクなども用意されています。
学校のプール水から飲料水を確保するための「ろ過装置」や救助活動・避難生活を支援するための備品など、多くの避難者に対応できる体制が整えられています。
参考:内閣府
●家庭用防災倉庫の中身

家庭用防災倉庫には、災害時に自宅で安全に過ごすための最低限の備えが必要です。停電や断水、物流の停止などに備えて食料や飲料水以外にも以下のようなものを備蓄しましょう。
・カセットコンロ
・ガスボンベ
・トイレットペーパー
・ティッシュ
・簡易トイレ
・食器
・鍋、やかん
・ランタン
・寝袋
食料や飲料水の備蓄は家族構成に合わせて最低でも3日分、可能であれば1週間分用意しておくと安心です。定期的に使用期限や数量を確認し、災害時に慌てず行動できるように日頃からしっかりと備えておきましょう。
参考:内閣府
4.防災倉庫の中身の選び方

防災倉庫の中身は地域の特性や災害リスク、想定される避難者数に応じて適切に選ぶのがポイントです。
ここでは、防災倉庫の中身の選び方を「自治体」「学校」「家庭用」にわけてそれぞれ解説していきます。
●自治体の防災倉庫:地域全体を支える備蓄・機材を用意する
自治体の防災倉庫の中身を選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。
・想定避難者数に応じた数量を確保する
・高齢者・乳幼児・障害者などへの配慮を行う
・長期保管可能な食品や水を選ぶ
・救助・医療・生活維持に必要な機材も備える
・誰でも扱えるシンプルな機材や用品を選ぶ
自治体の防災倉庫では、多くの人が共同で利用することを前提に長期的かつ実用的な備蓄が必要になります。災害発生直後から避難生活を想定し、地域の特性や人口構成に応じて防災倉庫の中身を検討しましょう。
●学校の防災倉庫:児童と地域住民両方を想定して備蓄する
学校の防災倉庫の中身を選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。
・児童・生徒と教職員の人数に応じた食料・水を確保する
・教室内での避難生活に対応できるものを備える
・地域住民の受け入れも考慮し、余裕のある数量を確保する
・子どもでも扱いやすく、わかりやすい備品を中心に選ぶ
・備品の使用場所・用途を明記し、誰でも取り出しやすい配置にする
学校の防災倉庫は在校中の児童・生徒だけでなく、地域住民の避難場所としての役割も果たせるように備える必要があります。幅広いニーズに対応することが求められるため、児童の安全を守ることと同時に地域全体の防災力が高められる備蓄を行いましょう。
●家庭用の防災倉庫:家族構成に合わせて備蓄する
家庭用防災倉庫の中身を選ぶポイントは、下記のとおりです。
・家族全員が最低3日間過ごせる食料・水(1人1日3リットルが目安)を確保する
・アレルギーや持病、服薬の有無を考慮して医療・衛生用品を揃える
・乳児・高齢者・ペットなど特別な配慮が必要な家族のものも忘れずに備蓄する
・停電・断水時に役立つアイテムを揃える
・定期的に見直しを行い、使用期限の管理や季節に合わせた調整を行う
家庭用の防災倉庫は、家族が数日間自宅で安全に過ごせるように備蓄するのがポイント。家庭ごとの人数や年齢、健康状態に合わせて必要な物資を選びましょう。
5.防災倉庫の設置や整備に補助金がもらえる?
防災倉庫の設置や整備には、国や自治体から補助金が受けられます。
ここでは補助金の概要や申請方法、注意点についてそれぞれ解説していきます。
●国や自治体による補助金が受けられる
防災倉庫の設置や整備には、国や自治体による補助金の受け取りが可能です。例えば、国土交通省の「地域防災拠点建築物整備緊急促進事業」では、地方公共団体が防災倉庫を整備する際の費用を支援しています。
また、各自治体でも自主防災組織が資機材を整備する際の補助制度を設けている場合があるので、事前に確認してみましょう。
参考:国土交通省
●補助金の申請方法と手順
補助金を申請する際の一般的な手順は、以下のとおりです。
1.自治体の担当部署に事前に相談し、申請要件や必要書類を確認する
2.申請書・事業計画書・支出予算書・見積書・設置場所の図面などを用意する
3.必要書類を揃えて、所定の窓口に提出する
4.審査の結果、補助金の交付が決定すると通知が届く
5.交付決定後に事業を開始し、完了後に実績報告書を提出する
6.報告書の内容が承認されると補助金が支払われる
具体的な手続きや必要書類は自治体によって異なるため、各自治体の公式サイトや担当部署に確認してから申請しましょう。
●申請時の注意点
補助金の申請時には、以下の点に注意しましょう。
・申請前に資機材を購入すると補助対象となる場合がある
・防災倉庫の設置場所が公共スペースの場合、別途許可が必要となる場合がある
・倉庫の規模や構造によっては、建築確認申請が必要となる場合がある
・補助金交付後も定期的な報告や点検が求められる場合がある
上記に注意しながら計画的に進めていくことで、スムーズに補助金を受け取れます。また、補助金制度は年度ごとに内容が変更されることもあるため、最新情報を確認してから申請を行いましょう。
6.自然放電が少なく、緊急時にすぐ使える「Jackery」ポータブル電源で災害に備えよう
防災倉庫に非常用電源を備えるなら、「Jackery(ジャクリ)」のポータブル電源がおすすめです。自然放電が少なく長期保管に適しているため、防災倉庫や自宅での備えにぴったり。例えば「Jackery ポータブル電源 3000 New」なら1年間保管しても自然放電はわずか5%なので、いざという時にすぐに活用できます。
【Jackery(ジャクリ)のおすすめポイント】
・全世界500万台以上の販売実績を誇るポータブル電源メーカー
・リン酸リチウムイオン電池内臓で毎日使っても10年以上長持ち
・防災製品等推奨品マーク取得済みだから災害時にも安心して使える
・ラインナップ豊富で自分にぴったりのモデルが見つかる
・静音レベル約30db以下だから避難所など人が多い場所でも動作音が気にならない
・ソーラーパネル対応だから停電が長期化しても繰り返し使える
スマホの充電だけでなく、電子レンジなどの消費電力が大きい家電も使用できる「Jackery(ジャクリ)」のポータブル電源で地域住民が安心安全に過ごせる環境を整えましょう。
もっと多くの商品を見る
7.防災倉庫の中身に関するよくある質問
ここでは、防災倉庫の中身に関するよくある質問について回答していきます。
●防災倉庫の中身は何日分・何人分必要ですか?
防災倉庫の備蓄量は、「最低3日分」が目安です。備蓄する人数の目安は、自治体・学校・家庭用ごとに以下のように異なります。
・自治体:地域人口の3〜5割程度を想定して備蓄する
・学校:児童や生徒、教職員に加えて地域住民も想定して備蓄する
・家庭用:家族構成に合わせて備蓄する
例えば100人分の水を3日分備蓄する場合、「1人1日3リットル × 3日 × 100人分=900リットルが必要になります。災害規模や被害状況によっては、支援物資が届くまでに1週間以上かかるケースもあるため、余裕を持った量を備蓄しましょう。
●必要な防災倉庫の中身は災害の種類によって異なりますか?
防災倉庫の中身は、以下のように災害の種類によって必要なものが異なります。
・地震:ライフライン寸断を想定して水・食料・トイレ用品が重視される
・風水害:浸水対策の土のうや水中ポンプ、雨具などが必要となる
・大雪:毛布やストーブなどの防寒具が必要となる
また災害リスクは地域によっても異なるため、ハザードマップを確認して適切な防災対策を行いましょう。
●防災倉庫の中身を地域住民が確認する方法は?
防災倉庫の中身を地域住民が確認方法は以下のとおりです。
・自治体や町内会の防災訓練に参加する
・自治体や市区町村の防災担当者に問い合わせる
・広報誌や掲示板、公式サイトを確認する
・防災マップ・地域防災計画を確認する
地域住民が防災倉庫の存在や中身を把握することは、災害時に落ち着いて行動するための第一歩でもあります。いつ起こるかわからない災害だからこそ、日頃からの意識と備えで安全を守っていきましょう。
まとめ
今回は防災倉庫の中身や選び方、補助金制度の活用方法などを紹介しました。防災倉庫は、地域住民の命綱となる設備です。地域の特性にあわせ、災害リスクに応じた中身を備えておきましょう。
防災倉庫に非常用電源を備えるなら、自然放電が少ない「Jackery(ジャクリ)」のポータブル電源がおすすめ。避難所でも住民たちが快適に過ごせる環境を整えましょう。