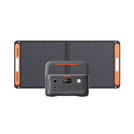1.津波の高さは3種類ある|表記や測り方も解説
私たちが普段ニュースで目にする津波の「高さ」には、大きく分けて下記3種類があります。
・津波高(つなみだか)|海岸線や港湾で観測される津波の高さ
・遡上高(そじょうこう)|津波が陸地を駆け上がった高さ
・浸水深(しんすいしん)|津波が海岸から内陸まで進んだ距離
それぞれ異なる定義や測り方を見てみましょう。
①津波高(つなみだか)|海岸線や港湾で観測される津波の高さ
津波高(つなみだか)は、津波が海岸線に到達したときの海面からの高さです。通常は海面の高さを基準に測定され、港や海岸付近の潮位計や観測所で記録されます。
ニュースで「津波の高さ〇〇メートル」と報じられる場合、多くは津波高を指しています。津波高は到達した瞬間の波の頂上部分の高さであり、陸に押し寄せる水深とは別物です。
近年では福岡県近海の海域活断層で震度6以上の地震が発生した際、津波高が最大約2メートルを上回るという予想も出ています。
参考:福岡TNCニュース
②遡上高(そじょうこう)|津波が陸地を駆け上がった高さ
津波の遡上高(そじょうこう)は、津波が陸上を遡って到達した最も高い地点の高さです。通常は海抜(標高)で測定され、海からどれだけ高い場所まで津波が達したかを表す指標となります。
たとえ津波高が低くても、地形や湾の形によって津波が勢いを増し、遡上高が大きくなるケースも珍しくありません。2011年の東日本大震災では、岩手県宮古市で津波高約8mに対し、遡上高は約40mが記録されています。
参考:内閣府 防災情報のページ
③浸水深(しんすいしん)|津波が海岸から内陸まで進んだ距離
浸水深(しんすいしん)は、津波によって実際に陸上がどのくらいの深さまで水に浸かったかを示す指標です。地表面から水面までの高さが基準で、津波による被害の大きさを知るうえで重要な数値となります。
浸水深が2mの場合、人の胸から肩の高さまで水が到達するイメージです。たとえ同じ津波でも地形や建物の有無によって浸水深は異なり、平地では深くなりやすく、高台では浅くなりやすい傾向があります。
2.津波注意報・警報の指標を高さ・危険度別に解説

「津波注意報や警報は高さ何mで発令される?」と気になる方に向けて、それぞれの指標を解説します。今後ニュースや速報を見るときの知識として頭に入れておきましょう。
●津波注意報|高さ1m未満
津波注意報は、予想される津波の高さが1m未満の場合に発令されます。たとえ0.2m〜1m程度の小さな津波でも、海辺の潮位(潮の高さ)に急激な変化が生じるため大変危険です。
特に港湾や河口付近では水の流れが強くなるため、船舶や漁業施設に被害を及ぼすケースがあります。「注意報だから大丈夫」と安易に判断せず、津波注意報が出た時点で海水浴や釣りは中止するのが鉄則です。
関連人気記事:津波注意報発令!命を守るために取るべき行動と防災対策を徹底解説
●津波警報|高さ3〜5m
津波警報は、高さ3〜5mの津波発生が見込まれる際に発令されます。この規模になると、沿岸部では道路の水没など大きな被害につながる危険性が高まります。
河川を遡上する津波によって内陸部でも浸水する危険があるため、海から離れているからといって油断は禁物です。海岸付近にいた場合、すぐに高台や頑丈な建物の上階へ移動してください。
関連人気記事:3mの津波はどれくらいやばい?想定被害や避難方法・対策のポイントを紹介
●大津波警報|高さ5m以上
大津波警報は、予想される津波の高さが5m以上と極めて危険な場合に発令されます。5m以上の津波は建物を飲み込み、広範囲に甚大な被害を及ぼします。
大津波警報が出た場合、河川沿いや低地でも大規模な浸水被害が想定されるため、一刻も早い避難が必要です。ハザードマップや最新ニュースをリアルタイムで確認しつつ、少しでも早く安全な場所へ移動して命を守りましょう。
参考:気象庁「津波警報・注意報、津波情報、津波予報について」
3.過去日本で発生した津波の高さランキングまとめ
過去に日本で発生した津波の高さをランキング形式でまとめました。
|
地震の名称 |
発生日 |
最大津波高 |
|
東日本大震災 |
2011年3月11日 |
約40.5m |
|
明治三陸地震 |
1896年6月15日 |
約38.2m |
|
昭和三陸地震 |
1933年3月3日 |
約28.7m |
|
宝永地震 |
1707年10月28日 |
約25.7m |
|
能登半島地震 |
2024年1月1日 |
約11.3m |
参考:農研機構公式サイト
参考:失敗知識データベース
参考:宮古市災害資料アーカイブ
参考:MRO北陸放送公式サイト
東日本大震災では、岩手県宮古市にて最大40m超の津波が発生。三陸沿岸を中心に甚大な浸水被害をもたらし、多くの住宅や交通インフラに壊滅的な打撃を与えました。
また阪神淡路大震災では最大震度7を観測したものの、発生した津波の大きさは0.4m未満に止まる結果となっています。津波が大きくならなかった理由は、主に下記のとおりです。
・震源が兵庫県の内陸直下型だったため
・横ずれ断層型で海底の上下変動が小さかったため
・震源域が津波を発生させる海域から離れていたため
津波の高さは地震の大きさに比例するとは限らないものの、地震速報が来てすぐに波が押し寄せるリスクを頭に入れておきましょう。
参考:気象庁公式サイト
関連人気記事:東日本大震災の津波高さは最大どれくらい?今後の地震対策のポイントも解説
4.南海トラフで予想される津波の高さは「最大30m以上」

今後30年以内に起きるといわれる南海トラフ地震では、同時に最大30m以上の津波の発生が予想されています。南海トラフ地震により、各地で想定される津波の高さは下記のとおりです。
|
エリア名 |
予想津波高 |
|
東京 |
最大約28m |
|
大阪 |
最大約5m |
|
静岡 |
最大約31m |
|
名古屋 |
最大約22m |
|
三重 |
最大約26m |
|
広島 |
最大約5m |
|
岡山 |
最大約4m |
|
徳島 |
最大約24m |
|
香川 |
最大約5m |
|
大分 |
最大約15m |
南海トラフ地震では、東京をはじめ多くのエリアで10mを超える津波の発生が予想されています。対策を怠ると、ある日突然津波が発生した際に命を落とすリスクが高まるでしょう。
今すぐに始められる地震や津波への対策について、下記段落にて詳しく解説します。
5.大きな津波への対策で今からできること
今後発生が予想される大津波に備えて、下記の対策を今からでも実施しましょう。
・避難経路や安全な場所を確認しておく
・津波に関する情報をキャッチする体制を整える
・急な避難に備えて非常用バッグを用意する
・家族や友人間で複数の連絡手段を確保しておく
いつ来るかわからない津波への備えを進めてください。
●避難経路や安全な場所を確認しておく
津波から命を守るためには、揺れを感じた瞬間すぐに高台や避難場所へ移動する必要があります。事前に自宅や職場、学校から「どのルートで避難すればよいか」を確認しておきましょう。
自治体ごとに公開されているハザードマップを活用すると、浸水予想区域や避難所の位置を一目で把握できます。日中や夜間など、複数の時間帯を想定したシミュレーションも行っておきましょう。
●津波に関する情報をキャッチする体制を整える
津波は地震発生から数分~数十分で到達することがあり、情報をいち早く受け取れる体制づくりが欠かせません。津波に関する情報をリアルタイムで受け取るなら、下記のアプリやサイトが便利です。
「情報を受け取れるかどうか」は避難のスピードに直結する要素です。いつ発生するかわからない地震や津波に備えて、今のうちからスマホの準備を整えましょう。
●急な避難に備えて非常用バッグを用意する
津波発生時には、揺れを感じた直後にすぐ避難を始めなければなりません。物探しでバタバタしないよう、非常用バッグをあらかじめ玄関や寝室など取り出しやすい場所に用意しておくのが大切です。
防災バッグの中には、下記のアイテムを入れておく必要があります。
・飲料水・非常食(人数×3日分)
・ポータブル電源・モバイルバッテリー
・懐中電灯
・常備薬
・簡易トイレ
・防雨グッズ
・身分証明書
・現金など
定期的に中身をチェックし、生活に最低限欠かせないアイテムを備蓄しておきましょう。
●家族や友人間で複数の連絡手段を確保しておく
大きな津波が発生すると、通信障害や回線の混雑により家族や友人と連絡が取りにくくなります。電話かインターネットどちらかが使えなくなることを想定し、安否確認の方法を複数用意しておきましょう。
災害時には、LINEや電話のほかに下記の方法も活用できます。
・災害用伝言ダイヤル(171)|被災地や避難先から171に電話をかけると、安否情報を録音・再生できるサービス
・災害用伝言板サービス|携帯各社やYahoo!防災速報によって提供されるウェブ上の安否登録サービス
家族や親しい友人と「災害時はこのアプリで連絡を取る」などのルールを決めておくのもおすすめです。
6.津波の発生に備えてJackery(ジャクリ)のポータブル電源を用意しておこう

津波や地震発生時の非常用バッグには、Jackery(ジャクリ)のポータブル電源を用意しておきましょう。持ち運び可能なバッテリーとしての役割を果たすため、停電時やコンセントのない避難所生活で重宝するアイテムです。たとえコンセントが使えない環境下でも、電気ポットや炊飯器など調理家電を使って家族に温かいご飯を食べさせてあげられます。
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源は自然放電率が365日で5%と低いため、有事の際に備えて長期的に保管できます。防災製品等推奨品マークも取得しており、家庭や企業における災害対策グッズとして注目されているアイテムです。
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源には、防災バッグに入れて持ち運べるコンパクトなモデルも多いです。急な地震でも電源を確保したい方、避難所生活でもコンセントに困りたくない方は、今後の非常時に備えて導入を検討しましょう。
7.津波の高さに関してよくある質問
最後に、津波の高さに関してよくある下記の質問へ回答します。
●世界最大の津波は高さ何m?
世界で記録された最大の津波は、1958年にアメリカ・アラスカ州のリツヤ湾で発生した約524mの「メガ津波」です。マグニチュード7.8の地震による大規模な山体崩壊が海に流れ込み、その衝撃で巨大な水塊が持ち上げられました。
参考:Forbes Japan
通常の地震津波とは異なり、陸地の崩落が引き金となった特殊なケースです。津波の高さは一般的に数m〜十数mであるものの、地形条件が重なると数百m級の津波も起こり得ることがわかっています。
日本でも2011年の東日本大震災で遡上高40mを超える津波が観測されているため、今後も油断は禁物です。
●津波は高さ1m未満でも危険?
結論、津波は1m未満でも非常に危険です。津波は巨大な水の塊となって押し寄せるため、人や車を簡単に押し流す力があります。
たとえ高さ50cmの津波でも、その水圧は成人男性が立っているのが難しいほど強いです。1mを超える津波の場合、小型車両や建物の一部が流される危険性があります。
さらに津波は第一波よりも第二波、第三波の方が高くなるケースも多いです。津波注意報が発令されたらすぐに海岸や河口から離れ、高台へ避難しましょう。
●高い津波が起きやすい場所はどこ?
高い津波が発生しやすいのは、海溝型地震(プレートの沈み込みに伴って発生する地震)が起きやすい地域や湾奥部です。日本周辺では、下記などプレートの境界で巨大地震が発生するリスクがあります。
・南海トラフ|東海から九州沖にかけて広がる海溝
・日本海溝|東北地方沖に位置する海溝(東日本大震災を引き起こした震源域)
・千島海溝|北海道東方沖から千島列島にかけて続く海溝
さらに湾の奥や入り組んだ海岸線では津波のエネルギーが集中し、波高がさらに高くなる「増幅効果」が生み出されます。自宅や職場周辺の地震リスクについては、自治体が公表しているハザードマップで事前に確認しておきましょう。
まとめ
津波の高さには津波高、遡上高、浸水深の3種類があり、どれも定義や測り方が異なります。ニュースでは津波高が取り上げられるケースが多く、東日本大震災では最大40m以上が観測されました。
また日本では、今後30年以内に南海トラフ地震の発生が予想されています。想定被害はエリアによって異なるものの、多くのエリアで10m超の津波が発生するリスクが高いです。
地震発生に備えるためには、早めかつ徹底的な対策が欠かせません。大きな災害から自分や大切な人の命を守れるよう、防災バッグや情報収集の準備を怠らない意識が大切です。急な停電や避難も想定し、防災バッグの中にJackery(ジャクリ)のポータブル電源を用意しておきましょう。