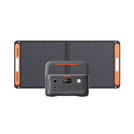1.猫にとって冬の室温20度以下は厳しい!快適な室温
冬は暖房をつけないと室内も寒さが厳しくなり、飼い主からは「猫にとって室温は何度が最適?」「13〜15度くらいなら大丈夫?」など疑問の声が聞かれます。
室温が低すぎると猫が体調を崩すリスクが高まるため、猫に合った室温や寒さ対策を知っておくことが大切です。
結論、猫が冬を快適に過ごすには室温を20度以上に保つことが理想です。ここでは、猫が寒いときに見せるサインやおすすめの室温設定を詳しく解説します。
●猫が寒さに弱い理由と寒いときに見せるサイン
猫は肉球にしか汗腺がなく、人間のように全身で汗をかけません。そのため、体温を調節する能力が低く外気温の影響を受けやすいです。また、皮下脂肪が少なく体温を維持しにくい特徴があります。
寒いときに見せる行動は以下のとおりです。
・体を丸めて小さくなる
・毛を逆立てて体を膨らませる
・暖かい場所を探して移動する
・飼い主の膝や布団に潜り込む
・震える、鼻水が出る
・活動量が減り、じっとしている時間が増える
猫が寒がっているサインが見られたら、室温が低すぎる可能性があります。暖房器具を使用したり毛布を用意したりして、環境を整えましょう。
●冬場の室温・湿度の目安は個体差あり|設定温度は20〜28度がおすすめ
猫にとって快適な冬の室温は20〜28度が目安です。ただし、猫の年齢や体型、毛の長さによって適温は異なります。毛が短い種類の猫や痩せ型の猫は寒さを感じやすく、一方で毛が長い種類や体格の良い猫は寒さに比較的強いです。
また、猫にとって理想の湿度は50〜60%です。冬は暖房の使用により空気が乾燥しやすくなります。湿度が40%を下回ると呼吸器系のトラブルや皮膚の乾燥を引き起こす可能性があるため、加湿器の併用がおすすめです。
●子猫やシニア猫は室温調節がより必要
生後3ヶ月未満の子猫は体温調節の機能が未発達なため、成猫よりも温かい環境にする必要があります。子猫の場合、室温は25〜28度程度に保ちましょう。
子猫は体が小さく体温が失われやすいです。また、免疫力も十分でないため、寒さによる体調不良が命に関わることもあり細心の注意が必要です。
7歳以上のシニア猫も若い頃と比べて体温調節能力が低下しています。筋肉量の減少や基礎代謝の低下により自力で体温を保つことが難しくなるため、室温は22〜25度程度の設定がおすすめです。
また、シニア猫は関節炎などの持病を抱えていることも多く、寒さによって症状が悪化する場合があります。暖かい環境を維持すると関節の痛みを和らげ、快適な生活を送れます。
●できれば冬は暖房(エアコン)つけっぱなしが◎
猫の健康を考えると、冬場は暖房を24時間つけっぱなしにするのがおすすめです。エアコンであれば一定の室温を保ちやすく、猫にとって快適な環境を維持できます。
電気代が気になる場合は設定温度を20〜22度程度の低めに設定し、省エネモードを活用するとコストを抑えられます。暖房をつけっぱなしにするメリットは以下のとおりです。
・急激な温度変化による体調不良を防げる
・夜間や早朝の冷え込みから猫を守れる
・留守番中も安心して外出できる
・猫のストレスを軽減できる
ただし、暖房をつけっぱなしにするなら、涼しい場所も確保しておく必要があります。猫が暑すぎると感じたときに避難できる場所を作り、熱中症のリスクを減らしましょう。
関連人気記事:愛猫の寒さ対策は大丈夫?電源なしでも暖かい環境をつくる方法と便利アイテム
2.猫がいる家で暖房器具を使うときの注意点と対策4選

暖房器具は猫の冬の快適な生活に欠かせませんが、正しく使わないと事故につながるリスクがあります。
安全に暖房器具を使うための注意点と対策を紹介します。
●こたつや湯たんぽによる低温やけどを防ぐ
猫はこたつが大好きですが、長時間入り続けると低温やけどのリスクがある暖房器具です。低温やけどは40〜50度程度の比較的低い温度でも、長い時間皮膚に触れ続けることで起こります。
猫は毛に覆われており、飼い主が低温やけどに気づきにくい問題があります。こたつを使用する際は以下の対策がおすすめです。
・温度を低めに設定する
・タイマー機能を活用して定期的に電源を切る
・猫がこたつに入っているときは1〜2時間おきに外に出すよう促す
湯たんぽを使う場合は必ずタオルやカバーで包み、直接肌に触れないようにします。電気カーペットやペット用ヒーターも同様に、設定温度を低めにして猫が長時間同じ場所にいないよう注意しましょう。
●部屋を温めすぎないようエアコンの設定温度を調節する
エアコンの設定温度が高すぎると、猫が熱中症や脱水症状を起こすリスクがあります。また、直接温風が当たると目や鼻の粘膜が乾燥し、結膜炎や鼻炎を引き起こす可能性があります。そのため、エアコンの風が直接猫に当たらないよう風向きの調整が必要です。
部屋の温度にムラがないか定期的にチェックし、必要に応じてサーキュレーターを併用して空気を循環させるのもおすすめです。部屋全体を均一に暖められ、猫がどこにいても快適に過ごせる環境を作れます。
●乾燥による脱水を防ぐため水分を積極的に与える
暖房の使用により室内が乾燥すると、水分が不足しやすいです。冬は活動量が減り喉の渇きを感じにくくなるため、意識して水分補給を促す必要があります。
猫の脱水を防ぐには、複数の場所に水飲み場を設置してください。さまざまな場所に水を置けば、猫が移動したときにいつでも水分補給ができる環境を整えられます。
他にも以下の工夫で猫の水分摂取を促せます。
・流れる水を好む猫には自動給水器を使う
・ぬるま湯を用意して飲みやすくする
・ウェットフードや猫用のスープを与える
・水飲み場を清潔に保ち、毎日水を交換する
寒い冬でも猫が水分を取りやすい環境を作り、脱水を防ぎましょう。
●やけどやケガ、火災などの事故に備える
暖房器具の使用には常に事故のリスクが伴います。特にストーブやファンヒーターなど高温になる暖房器具はやけどやケガの危険があるため、以下の使うときの注意点を事前に確認しましょう。
・石油ストーブやガスファンヒーターの周りに柵やガードを設置する
・コードカバーをする
・暖房器具は転倒時自動停止機能やチャイルドロック機能が付いているものを選ぶ
万が一の事故に備えて、ペット保険への加入や動物病院の緊急連絡先の確認も大切です。やけどや熱中症の応急処置方法を事前に調べておけば、迅速な対応で猫の命を守れます。
3.冬の夜を猫が暖房なしで過ごすには?おすすめの寒さ対策5選
電気代の節約や停電時の備えとして、暖房なしでも猫が暖かく過ごせる方法を確認しましょう。ここでは、暖房に頼らない寒さ対策を紹介します。
①湯たんぽや毛布を使う
湯たんぽはお湯を入れるだけで6〜8時間程度暖かさが持続し、じんわりとした温もりがあります。電気を使わない暖房グッズとしておすすめです。
湯たんぽを使うときは、以下のポイントに注意して活用してください。
・厚手のタオルや専用カバーで包む
・猫が爪を立てても破れにくい丈夫な素材を選ぶ
・温度は40度程度が適温で、熱すぎると低温やけどの原因になるため注意する
毛布は保温効果が高く、猫が自由に潜り込める環境を作れます。フリース素材やマイクロファイバー素材の毛布は軽くて暖かく、猫も気に入りやすいです。
②ケージやベッドを窓から離した場所に置く
窓際は外気の影響を受けやすく冬場は特に冷気が入り込みやすいため、猫のケージやベッドは窓から最低でも1メートル以上離して設置してください。
部屋の中でも、壁際の角や家具に囲まれた場所は比較的暖かい空気がたまりやすいです。また、床からの冷気を防ぐため、ケージやベッドを少し高い位置に設置することもおすすめです。台や棚の上に置いたり、専用のスタンドを使えば、床の冷たさから猫を守れます。
猫は高い場所を好む習性もあるため、キャットタワーの上段に毛布を敷いて寝床を作るのもおすすめです。暖かい空気は上に溜まる性質があるため、高い位置ほど暖かく猫にとって快適な環境を作りやすいです。
③水飲み場やトイレを寒い場所に置かない
水飲み場やトイレが寒い場所にあると、猫が利用を避けるようになり、健康問題につながる恐れがあります。
トイレを寒い場所に置くと、猫が我慢してしまい、膀胱炎や尿路結石などの泌尿器系疾患のリスクが高まります。リビングなど、家族が過ごす暖かい部屋の隅にトイレを置き、猫が安心して用を足せる環境を作りましょう。
水飲み場も同様に、暖かい場所に複数設置すると水分摂取を促せます。冷たい水を嫌がる猫には、ぬるま湯を用意すると飲んでくれる場合もあります。
猫の動線に合わせた環境作りも必要です。ベッドからトイレ、水飲み場までの通り道が寒くないよう、カーペットを敷いたり暖かいエリアを通るよう工夫すれば猫のストレスを軽減できます。
④ブラッシングやマッサージをする
ブラッシングは猫の血行を促進し体温を上げる効果があります。毎日5〜10分程度のブラッシングを習慣化すると良いでしょう。
根元までしっかりブラッシングすると毛の間に空気の層ができ、保温効果が高まります。また、抜け毛を取り除くことで毛玉ができるのを防ぐことが可能です。
マッサージも血行促進に効果的です。猫の首筋から背中、お腹周りを優しくなでるようにマッサージすると体が温まります。肉球のマッサージも末端の血行を良くするため、冷え対策としておすすめです。
⑤窓や隙間からの冷気を防ぐ
窓や扉の隙間から入る冷気は室内の温度を下げる要因であり、以下の断熱対策をすると暖房なしでも室温を保ちやすいです。
・窓に断熱シートを貼り冷気を防ぐ
・カーテンは厚手で床まで届く長さのものを選ぶ
・ドアの下の隙間には、隙間テープやドラフトストッパーを使う
・使わない部屋のドアは閉めておく
・床にカーペットやラグを敷く
・壁際に家具を配置して断熱層を作る
冷気を防ぐ対策により部屋全体の保温性が高まり、猫が快適に過ごせる環境を維持できます。省エネにもつながる、環境にも家計にも優しい対策です。
4.停電時に猫を寒さから守るにはポータブル電源がおすすめ

災害や計画停電などで電気が使えなくなると、暖房器具が動かず猫の体温管理が難しくなります。毛布やタオルでしのげますが、猫が快適に過ごすにはこたつやヒーターといった電化製品が欠かせません。
持ち運び可能な蓄電池であるポータブル電源があれば、停電時でも電気毛布などの電化製品を使えます。おすすめの活用例は以下のとおりです。
・電気毛布やペット用ヒーターで猫が過ごす場所を温める
・電気ケトルでお湯を沸かして、温かい飲み物を与える
豊富なラインナップを持つJackery(ジャクリ)のポータブル電源はコンパクトサイズのモデルが多く、保管場所に困りません。また、独自技術の採用により1年間の自然放電が5%と少なく、長期保管にも向いています。
いざというときに備えてポータブル電源を準備し、寒い日の停電でも猫と一緒に安心して過ごしましょう。
5.猫が冬を快適に過ごすための室温に関するよくある質問
猫がいる環境の冬の室温管理について、飼い主さんからよく寄せられる質問にお答えします。
●冬に猫が留守番をするときエアコンなしでも大丈夫?
短時間の留守番であればエアコンなしでも大丈夫です。ただし、室温が15度を下回る環境では、エアコンを使いましょう。
日中の数時間程度の留守番なら、日当たりの良い場所に毛布を敷いたベッドや湯たんぽで対応できます。猫が自由に移動できるよう、複数の暖かい場所を作ることがポイントです。
ただし、長時間の留守番や夜間の留守番の場合は、エアコンを20度程度に設定してつけておく方が安全です。また、子猫やシニア猫、持病のある猫の場合は短時間でも暖房の使用をおすすめします。
●長毛猫は暖かそうだから暖房なしで大丈夫?
長毛猫は短毛猫に比べて寒さに強い傾向ですが、冬の寒さ対策は必要です。室温が15度を下回る環境では体調を崩すリスクがあります。
長毛猫の毛は保温性に優れていますが、体の芯から冷えることは防げません。特に高齢の猫や室内飼いで寒さに慣れていない猫は、慎重な室温の調節が必要です。
ペルシャ猫やメインクーンなどの長毛種でも、冬場の理想的な室温は20〜22度程度です。短毛種より低めでも大丈夫ですが、完全に暖房なしは避けた方が良いでしょう。
●子猫は「冬も室温30℃」が適温って本当?
生後1ヶ月未満の子猫の場合、室温28〜30度が適温です。ただし、成長とともに必要な室温は下がります。
生まれたばかりの子猫は体温調節機能が未発達で、母猫の体温に頼って生きています。母猫がいない場合は、人工的に高い室温を保つことが必要です。子猫に合った室温の目安は以下のとおりです。
・生後1ヶ月未満…28〜30度
・生後1〜2ヶ月…26〜28度
・生後3ヶ月〜…25度前後
子猫の成長に合わせて室温を調整しましょう。
まとめ
猫が冬を快適に過ごすには、室温20〜28度が理想です。特に子猫やシニア猫は体温調整が苦手なため、より暖かい環境づくりが欠かせません。暖房器具の活用や猫に合わせた温度管理、寝床の位置などを工夫すれば寒さによる体調不良を防げます。
冬の寒い日の停電に備えるにはポータブル電源がおすすめです。電気が止まっても、ポータブル電源で暖房器具を動かして猫を寒さから守りましょう。