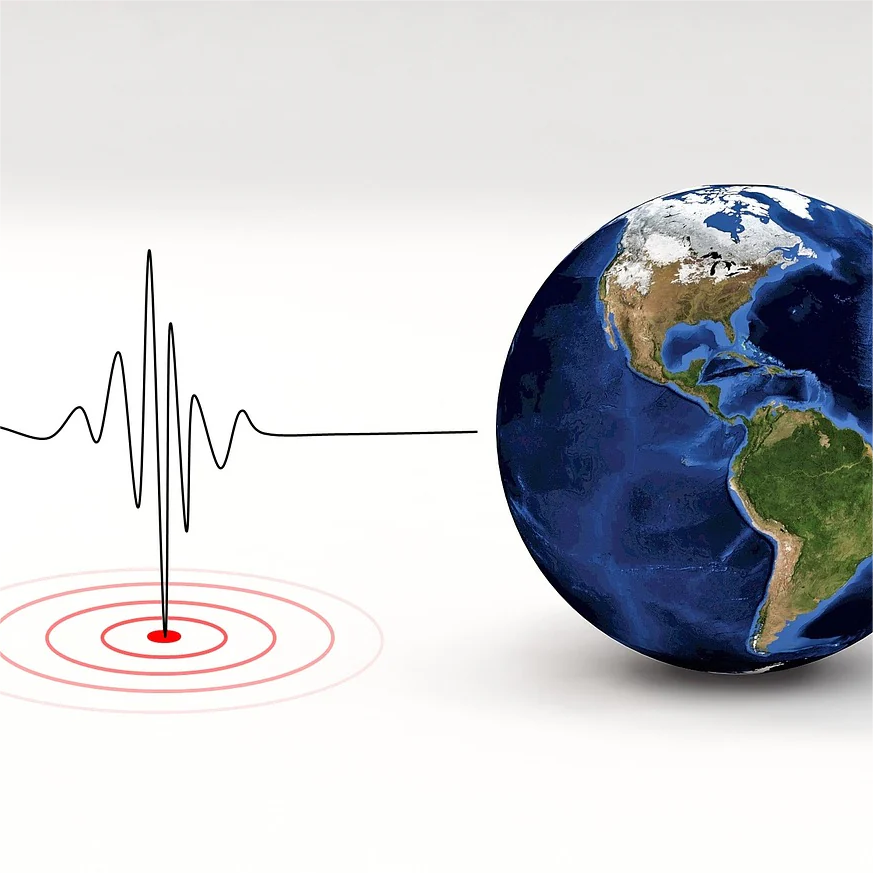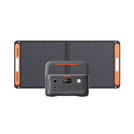1.南海トラフ地震と富士山噴火の連動は十分起こりうる
南海トラフ地震と富士山噴火の連動は、十分起こりうると考えられています。地震と噴火が連動したと思われる過去の事例や、専門家の意見を紹介します。
●南海トラフの地殻変動が富士山の火山活動に及ぼす影響
地震と火山の噴火は、どちらも大陸のプレートが動くことで発生する現象です。南海トラフ地震では、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界で大規模な地殻変動が起こります。この変化が富士山の火山活動に影響を与える可能性があります。

噴火に必要なマグマの形成も、プレートが動くことで起こる現象です。プレートの動きによってマントルが溶けてマグマが生成され、地下のマグマだまりに蓄積されます。マグマの移動やマグマから発生するガスの上昇、地下水の移動などに伴って地震が発生します。これが噴火の前兆として観測される火山性の地震です。

引用:国土交通省 気象庁「火山噴火の仕組み」
参考:文部科学省「地震がわかる! 防災担当者参考資料 Ⅰ. 地震の起こる仕組み」
●地震と富士山の噴火が連動したと思われる過去の2事例
歴史的に見ると、巨大地震と富士山噴火が連動したと思われる事例が2つあります。
〇貞観噴火(864〜866年)
富士山の北西斜面から大量の溶岩が流れ出し、現在の青木ヶ原樹海を形成しました。この時期には貞観地震(869年)も発生しており、地震活動と火山活動が同時期に活発化した可能性が指摘されています。
〇宝永噴火(1707年)
宝永噴火は宝永地震(1707年)の49日後に発生しており、地震と噴火の関連がより高いと考えられています。宝永地震は南海トラフを震源とするマグニチュード8.6の巨大地震で、現在想定されている南海トラフ地震と類似した規模でした。
過去に南海トラフ地震と富士山噴火が連動したと思われる事例が観測されており、将来的にも発生する可能性が高いと考えられます。
また、2025年7月30日に発生し日本にも津波をもたらした「カムチャツカ半島地震」では、地震後24時間以内に半島東部の火山が噴火しました。明確な関連性は判明していませんが、おそらく地震による地殻変動誘発された火山噴火だろう、との見解が上がっています。
●南海トラフ地震と富士山噴火が連動する確率は?専門家の見解を解説
専門家の間では、南海トラフ地震と富士山噴火が連動する可能性は否定できないものの、直接的な因果関係を示す証拠は十分ではないとされているのが現状です。
しかし、東北大学の研究では、大地震が起こってから10年間は火山噴火の可能性が2〜3倍に上昇する統計的データが示されています。
参考:東北大学「大地震によって誘発される火山噴火 火山噴火が誘発されるメカニズムと噴火発生頻度を提示」
過去の歴史的事例では実際に連動した可能性が高い地震・噴火が発生していることから、十分な警戒と備えは必須です。
気象庁は南海トラフ地震について、今後30年以内に発生する確率を80%程度と発表しています。この高い発生確率を踏まえると、富士山噴火が連動して起こる可能性も含めた防災対策が必要です。
2.南海トラフ地震と富士山噴火が同時に起きたとき想定される被害
南海トラフ地震と富士山噴火が同時発生した場合、単独の災害を上回る大きな被害が想定されます。複合災害により、救助・復旧活動が著しく困難になり、被害が長期化するかもしれません。
●首都圏・東海地方のインフラ停止
南海トラフ地震と富士山噴火の連動による災害で想定される、首都圏や東海地方のインフラへの影響は以下のとおりです。
|
影響を受けるインフラ |
想定される被害 |
|
交通 |
東海道新幹線や東名高速道路などの基幹路線が同時に機能停止し、人や物資の移動が困難になる |
|
電力供給 |
地震による発電所の停止に加え、火山灰による送電線の絶縁不良や変電設備の故障が重なると、広範囲にわたる長期停電が発生する恐れがある |
|
通信 |
携帯電話基地局の損壊や停電により、災害時に必要とされる情報伝達手段が機能しなくなる可能性が高い |
インフラは相互に関連し合っており、一つのシステムの復旧が遅れると他のシステムの復旧も困難になる悪循環が生まれます。平時には当たり前に利用している社会インフラが、複合災害によって同時に失われる事態を想定した備えが必要です。
●南海トラフ地震による建物損壊や津波被害
南海トラフ地震単体でも、想定される建物倒壊や津波被害は甚大です。
建物の損壊は、1981年以前の旧耐震基準で建てられた構造物を中心に、大規模な倒壊や損傷が発生すると予測されています。
津波による被害は、下記の画像のとおり沿岸部を中心に広い範囲に被害をもたらす想定です。

引用:国土交通省 気象庁「南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ」
最大で20メートルを超える津波高が予想されている地域も存在し、海抜の低い平野部では内陸深くまで浸水する可能性があります。
地震・津波被害に富士山噴火が重なることで、避難所の確保や被災者の救助活動がさらに困難になり、人的被害の拡大が懸念されます。
●富士山噴火による大量の火山灰による被害
富士山が噴火した場合、首都圏を含む関東地方に大量の火山灰が降り注ぐと想定されています。実際に火山灰が降る地域の想定は以下の画像のとおりです。

また、噴火により降り注ぐ火山灰で想定される主な被害は、以下のとおりです。
・火山灰が送電線に付着すると、広範囲にわたり停電が発生する
・火山灰により視界が悪化し、自動車や航空機の運行が困難になる
・線路に堆積した火山灰により、電車の運行が困難になる
・人体への影響は喘息や肺疾患を悪化させる恐れがある
火山灰はインフラや人体へ多くの影響を及ぼすことが分かっています。火山灰が降る可能性がある地域に住んでいる方は、停電に対する非常時電源の確保や人体への影響を減らすマスクの準備などが必要です。
参考:内閣府防災情報「⼤規模噴⽕時の広域降灰対策について」
●復旧・救助活動の大幅な遅延と被害拡大
地震と噴火が連動した場合の深刻な問題は、救助・復旧活動の大幅な遅延です。地震による道路の寸断や、火山灰による交通機能の停止により、救助隊の現場到達が難しくなります。
医療機関も同時に被災するため、負傷者の受け入れ能力の低下が想定されます。停電や断水により、被害が少なかった医療施設でも十分な治療を提供することが困難になりかねません。
復旧・救助活動の遅延は、被害の拡大や、復興期間の長期化につながる要因です。東日本大震災の復興が10年以上を要していることを考えると、南海トラフ地震と富士山噴火の複合災害からの復興は、さらに長期間を必要とする可能性が高いです。
●大規模な人的被害と経済被害
内閣府の試算によると、南海トラフ地震だけでも最大約30万人の死者が想定されています。これに富士山噴火が重なった場合、火山灰による健康被害や避難の遅れにより、さらに多くの人的被害が発生する恐れがあります。
経済被害も南海トラフ地震単体で約270兆円の経済損失が見込まれていますが、富士山噴火が同時発生すれば、被害額は大幅に増加するでしょう。首都圏の経済機能停止により、日本全体の経済活動が長期間にわたって麻痺する可能性があります。
参考:内閣府防災情報「南海トラフ巨大地震対策について(報告書)」
関連人気記事:富士山噴火と地震が連動する!?起こりうる被害や防災対策を解説
3.南海トラフ地震と富士山噴火の両方に備える!5つの防災対策
地震と火山噴火の両方を想定した防災対策を実施すれば、被害を最小限に抑えられます。今すぐできる防災対策を確認し、できる内容から実践しましょう。
①ハザードマップと避難経路の確認をする
災害時スムーズに避難するには、事前のハザードマップ確認と避難経路の把握が大切です。
南海トラフ地震について、住んでいる地域の想定震度や津波の高さ・到達時間を気象庁のデータで確認しましょう。同時に、富士山噴火時の溶岩流や火砕流の影響範囲を富士山ハザードマップで確認します。
下記の画像は、南海トラフ地震の際に想定される津波のハザードマップです。

引用:国土交通省 気象庁「南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ」
下記の画像は富士山噴火時のハザードマップの一例で、噴火による複数の被害想定が重ねて示されています。

避難経路は、複数のルートを確認しておくことが大切です。避難場所も地震と噴火の両方に備えられる安全な場所を選びましょう。家族全員でハザードマップを見ながら避難計画を話し合い、連絡方法や集合場所を決めておくと、災害時の混乱を最小限に抑えられます。
②防災グッズと備蓄品の準備をする
通常の地震対策に加え、火山灰の対策グッズも準備しましょう。
基本的な備蓄品として、最低3日分、できれば1週間分の食料と飲料水を確保してください。火山灰により物流が長期間停止する可能性があるため、通常よりも多めに備蓄することが推奨されます。備蓄品の一例は以下のとおりです。
・非常食(アルファ米、缶詰、レトルト食品)
・飲料水(1人あたり1日3リットル)
・懐中電灯・ラジオ・乾電池
・救急用品・常備薬
・防塵マスク・ゴーグル(火山灰対策)
・携帯トイレ・衛生用品
備蓄品は定期的に点検し、賞味期限の確認や不足品の補充をしましょう。
③停電時に備えて電源を確保する
火山灰による停電は長期間に及ぶ可能性があるため、非常用電源の確保は必須の対策です。停電時、非常用電源が必要な主な活用シーンを下記に挙げます。
・携帯電話の充電
・照明
・情報収集のラジオ
・暑さ対策の扇風機・寒さ対策の電気毛布
・食事を準備する調理家電
生活の中で電力が必要な場面は多く、モバイルバッテリーや予備の乾電池では不十分なこともあります。停電中も家電を使って、食事の準備や寒冷対策をしたい方は、容量の大きなポータブル電源の準備がおすすめです。
さらにソーラーパネルもセットで用意しておけば、繰り返し充電できるため、長期間の停電でも安心して過ごせます。非常用電源は定期的に動作確認し、いざという時に確実に使える状態を保ちましょう。
④自宅の耐震強化と火山灰対策をする
住宅の耐震強化や火山灰対策は、地震や噴火による被害を軽減する効果的な対策です。
耐震基準が1981年に新しくなり、それ以降に建てられた住宅は地震に対する安全性が大幅に上がりました。1981年より前に建築された住宅は、耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強工事を実施してください。
火山灰対策として、屋根の補強も必要な対策です。火山灰の重量により屋根が崩壊する危険があるため、自宅を守るために強度の確認と補強が役立ちます。
また、家に火山灰を入れないための対策として、窓やドアの隙間を塞ぐ準備をしておきます。養生テープやビニールシートを用意し、火山灰の室内侵入を最小限に抑える方法を事前に確認しておけば、いざという時に安心です。
⑤地域の防災訓練や情報交換に参加する
地域コミュニティとの連携は、災害時の生存の可能性を高めます。定期的に開催される防災訓練に積極的に参加し、近隣住民との協力体制を構築しておきましょう。自治会や町内会が主催する防災活動では、地域の防災資源や避難計画についての詳しい情報も得られます。
日頃からの情報交換も大切です。高齢者世帯や一人暮らしの方の安否確認方法を話し合ったり、特別な支援が必要な方がいる場合の対応方法を検討したりしておけば、災害時の対応がスムーズになります。防災に関する最新情報や防災対策の共有で、地域全体の災害に備える力を向上させましょう。
関連人気記事:南海トラフ地震はいつ起こる?生き残るために万全の対策をしよう
4.Jackery(ジャクリ)のポータブル電源があれば長期間の停電も安心

南海トラフ地震と富士山の噴火が同時に起こると、長期間の停電が起こるリスクもあります。情報収集や家族との連絡、食事の準備などさまざまな場面で電源は必要なため、非常時の電源確保は大切な防災対策です。
持ち運びができる蓄電池であるポータブル電源があれば、停電時も電力を確保できるため、多くの家電が使えます。
Jackery(ジャクリ)は幅広いラインナップのポータブル電源を販売しており、家族の人数や使いたい家電に合わせた容量・出力の製品を選べます。また、Jackery Solar Generatorシリーズはソーラーパネルとセットで、繰り返し充電でき長期の停電に対応可能です。
停電時に温かい食事を食べたり、電気毛布で寒さを防いだりして、安心して過ごせるようにポータブル電源を準備しましょう。
5.南海トラフ地震と富士山噴火に関するよくある質問
南海トラフ地震や富士山噴火に関する疑問や不安を解消するため、よくある質問をまとめました。
●南海トラフ地震・首都直下型地震・ 富士山噴火の3つが同時に起こることはある?
3つの災害が同時発生する可能性は極めて低いものの、短期間に連続して発生する確率はゼロではありません。
南海トラフ地震による地殻変動が、首都直下型地震の発生確率を高める可能性があります。また、大規模な地震活動は火山活動を誘発する要因となるため、連続して地震と噴火が起こる可能性も否定できず警戒が必要です。
●南海トラフ、首都圏直下型、富士山噴火の3つの災害に耐えられるエリアはどこですか?
3つの災害から絶対に安全なエリアを見つけるのは難しいですが、リスクが低い地域として、九州や東北など活断層から離れた場所が挙げられます。
ただし南海トラフ地震の直接的な影響は受けにくいものの、経済的な影響や物流の混乱による間接的な被害は避けられません。また、これらの地域にも異なる地震や噴火のリスクが存在します。
引っ越すよりも、現在住んでいる場所でできる限りの備えを行う方が現実的です。どの地域に住んでいても、その土地のリスクを理解し、必要な対策を講じることが大切です。
●富士山噴火が起こったとき、富士吉田市、富士宮市、御殿場市など富士山付近の家は溶岩流に飲み込まれますか?
富士山ハザードマップによると、これらの市では溶岩流の影響を受ける可能性があります。ただし、噴火の火口がどこにできるかによって被害を受ける地域は異なるため、どの市に溶岩流が到達するか事前に特定できません。
下記の画像の色で示されている地域が、溶岩流の影響が及ぶ可能性がある地域です。

溶岩流の到達には数時間から数日の時間的余裕があるため、迅速な避難により命の危険は回避できる可能性が高いです。富士山が噴火したら、気象庁の噴火警報や自治体の避難指示に従い、指定された避難所へ速やかに移動して安全を確保しましょう。
●富士山がなかなか噴火しない理由は?
富士山が噴火しない理由は、地下のマグマだまりの圧力バランスが安定していることが考えられます。また、現在の富士山は比較的安定した状態で、地震など噴火を引き起こすだけの外的要因が不足している可能性もあります。
富士山の最後の噴火は1707年の宝永噴火から300年以上が経過していますが、火山活動が停止したことを意味するものではありません。地下では現在もマグマ活動が継続しています。
地震や地殻変動により、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況で、自然災害に対する備えは必要な状況が続いています。
関連人気記事:南海トラフ地震がなかなか起きない理由は?来ない確率ある?今やるべき防災対策も紹介
まとめ
南海トラフ地震と富士山噴火は、連動して発生する可能性が十分考えられる自然災害です。2つの災害が同時に発生した場合、単独の災害を上回る被害が想定され、両方に備えた防災対策が必要です。
地震と噴火が連動するとインフラの復旧や救助が遅れる可能性が高く、個人の防災対策が被害を抑えることにつながります。停電に備えるには、幅広い家電を動かせるポータブル電源がおすすめです。Jackery(ジャクリ)のポータブル電源を用意して、万が一の自然災害に備えましょう。