1.【100均】雪道でも安心!靴の滑り止めグッズ3選
雪道を安心して歩くには、靴の滑り止めグッズを使うのがおすすめです。100均で購入でき、シールタイプやかかとにつけるタイプなど、装着の仕方も装着部分もさまざまです。
100均で販売されている靴の滑り止めグッズのすべてが100円とは限りませんが、雪の降る日に備え準備しておくと良いでしょう。
①靴の滑り止めステッカー

出典:靴の滑り止めステッカー
靴の裏に貼るだけで手軽に滑り止め効果が得られるグッズです。靴と接着する面はシール状になっているため、工具を準備する必要もありません。
革靴やパンプスなど、もともと滑りやすい靴に使うと効果的です。接着する際にはシール部分の粘着力が弱まらないよう、使用前に靴底をしっかり乾かしてから貼りましょう。
②靴底すべり止めパッド

厚みのあるゴム製の滑り止めパッドで、雪道や凍結路面で滑るのを防いでくれるグッズです。シールタイプなので、スニーカーやブーツなどさまざまな靴に使用できます。実用性が高く、冬場の外出時に備えておくと安心です。
③紳士かかと用トップリフト

紳士靴の修理用素材ですが、ゴム素材であるため滑りやすい雪道でかかとのグリップ力を上げるのに役立ちます。セットになっている釘でかかと部分に打ち付けるタイプ。シールタイプのものと比べると、使用中にはがれてしまう心配は少ないでしょう。
2.雪道で活躍する靴の滑り止め|100均グッズの使い方
雪道で活躍する靴の滑り止め100均グッズは、使い方を工夫することで効果をしっかり得られます。雪道を安全に歩くために、以下のポイントを押さえましょう。
・靴底をきれいにしてから滑り止めを貼る
・地面と確実に接触する位置に貼る
・サイズを調整して、接着面がはみ出ないようにする
・接着剤で貼り付けるタイプの場合はしっかり乾燥させる
・定期的に滑り止めの状態をチェックする
靴の滑り止めを装着する際には、粘着力を高めるために貼り付け面の靴底をきれいにしてから貼りましょう。また、靴底を見て自分の歩き癖を考え、きちんと地面に接地する部分に滑り止めを貼らなければ、滑り止めの効果が出にくいので注意が必要です。
接着剤タイプの場合は乾燥時間通りに乾燥しないこともあるので、時間に余裕を持ってしっかり固定させるのもポイントです。そして、靴の滑り止めがはがれそうになっていないか、接地面が劣化していないかを定期的に確認するとよいでしょう。
3.100均の靴滑り止めで雪道を歩く際の注意点3選

靴の滑り止めをつけて雪道を歩く場合、普段通りに歩くよりいくつかの点に注意して歩くと、より滑り止めの効果が発揮されます。滑り止めをつけて雪道を歩くときは、以下の点に注意して歩いてみてください。
●注意点1|雪道を走らない
靴の滑り止めをつけていても、雪道を走るのは避けましょう。歩く場合と走る場合とでは力の入り方が変わり、滑り止めグッズをつけていても滑る可能性が高まります。特に、凍結した道では走った瞬間に足が滑ることもあるので、雪道を走らないよう心がけましょう。
●注意点2|小さな歩幅で歩く
滑り止めをつけて雪道を歩く場合は、普段より小さな歩幅で歩くのもポイントです。普段通りの歩幅で歩くと、滑り止めが地面に接地する面が少なくなってしまいます。足を高く上げないようにし、意識して歩幅を小さくするのを心がけてみてください。
●注意点3|靴底の全体で歩く
雪道を歩く際には、靴底全体が地面につくように歩きましょう。滑り止めグッズをつけているつま先やかかとがしっかり地面に接するようにするためです。靴底全体で歩くようにすると安定感が増し、滑るリスクを軽減できます。
4.雪道に最適な靴の滑り止めの選び方3選
雪道で使える靴の滑り止めは、素材や形状、装着の仕方も含めるとさまざまな種類があります。装着が手軽であっても、滑り止めの効果が弱いと安心して雪道を歩くのは難しいでしょう。雪道に最適な滑り止めを選ぶ際は、どんな点に注目すればよいかを解説していきます。
①防滑力が優れている
雪道に最適な靴の滑り止めを選ぶ際は、防滑力(ぼうかつりょく)が優れているものを選びましょう。滑り止めグッズの中には、見た目はしっかりしていても実際のグリップ力が弱く、雪道で効果を発揮しないものもあります。
防滑力が十分かどうか見極めるには、素材と構造に注目すると良いでしょう。ゴム素材のものや凹凸のある構造のものは、防滑力が高いといえます。また、パッケージに「滑り止め強化」のような表記がある商品を選ぶのもおすすめです。
②靴の形状に合っている
靴の形状に合っているかに注目するのも、雪道に最適な滑り止めを選ぶ方法の一つです。靴の形状に合っていないと、滑り止めがズレたりはがれたりしやすくなり、転倒したり滑ったりする危険性が高まります。
シールタイプやパッドタイプの滑り止めは、靴の形状に合わせてカットできるタイプの商品もあります。購入前にカットして使えるタイプか確認して購入すると良いでしょう。
③耐久性のある素材を採用する
雪道に最適な靴の滑り止めを選ぶ際は、耐久性のある素材を選ぶのもポイントです。雪道で滑り止めグッズを使うと、寒さと摩耗で劣化しやすいからです。耐寒性のある合成樹脂素材のものや、厚みのあるゴム素材の商品を選ぶと良いでしょう。
5.【雪道】靴の滑り止めグッズを販売する100均店舗

雪道でも使える靴の滑り止めグッズは、100均の店舗でも購入可能です。しかし、100均にはダイソーやセリア、キャンドゥなどいくつか種類があります。それぞれの100均でどのような靴の滑り止めグッズがあるか、簡単にまとめました。
●ダイソー
全国に店舗を展開するダイソーでは、冬の時期になると雪道の滑り止めグッズが多く並びます。靴底に貼るステッカータイプの商品やゴム製の滑り止めパッドなど、種類も豊富です。
しかし、ダイソーは店舗によって取り扱い商品が異なります。あまり雪が降らない地域では靴の滑り止めグッズの種類は少ない可能性があるため、注意が必要です。
●セリア
セリアでは、デザイン性の高い雪道用の滑り止めグッズが販売されています。女性の靴にも使いやすい商品がそろっているのが特徴です。靴底とはいえ、かわいい模様が入ったものを使いたいと考えている人は、セリアの商品をチェックしてみると良いでしょう。
●キャンドゥ
キャンドゥでも、ダイソーで販売しているような靴の滑り止め商品がそろっています。店舗によって商品のバリエーションは異なりますが、靴底に貼るシートタイプ、雪道対応の滑り止めなど、主な商品が並んでいるようです。
6.【100均以外】雪道で使える靴の滑り止めの購入先
近くにダイソーなどの100均の店舗がない場合でも、雪道で使える靴の滑り止めを購入できます。主な購入先は、ホームセンターや靴の専門店、通販です。
ホームセンター、靴の専門店、通販それぞれに良い点があるので参考にしてみてください。
●ホームセンター
ホームセンターでも雪道で使える靴の滑り止めを購入できます。100均より種類が豊富ですが、時期や店舗によっては取り扱いがない場合もあるので注意が必要です。100均より値が張る商品が並びますが、高い防滑性や耐久性を備えているものを見つけられるでしょう。
靴に装着するスパイクタイプの滑り止めのような、本格的な滑り止めグッズを置いている店舗もあります。絶対雪道で滑りたくない!と考えている人はホームセンターで滑り止めグッズを探してみるのがおすすめです。
●靴専門店・靴修理店
靴専門店や靴の修理店でも、雪道用の滑り止めを購入できます。靴の専門家から雪道で使う滑り止めにはどんなものが良いか、アドバイスを受けられるのがメリットです。
靴の専門店や修理店では、グッズを買う以外にも滑り止め加工をほどこすサービスを提案してくれる場合もあります。靴の見た目を損なわずに雪道での滑り止め効果をつけたいなら、靴専門店や靴修理店を利用するのも良いでしょう。
●通販
雪道で使える滑り止めグッズは、通販でも購入可能です。通販サイトではレビューを参考に、使用感をイメージしながら商品を選べるのでおすすめです。100均やホームセンターでは見かけないような特殊素材の商品もそろっているのも通販ならではと言えるでしょう。
ただし、サイズや仕様を手に取って確認できない点には注意が必要です。場合によっては出品者やメーカーに問い合わせをして、自分の靴に合うものを選びましょう。
7.雪の日に大活躍するポータブル電源とは

大雪によって起こりえる二次災害として、3日以上にのぼる大規模な停電が挙げられます。停電が起きている間も電気の供給を継続するためには、ポータブル電源が欠かせません。
ポータブル電源とは、内部のバッテリーに大量の電気を蓄え、コンセントが使えない状況でも電化製品に給電できる機器を指します。大雪による停電時に、ポータブル電源が活躍する場面は、以下のとおりです。
・エアコンや電気ストーブを稼働し、常に快適な気温で生活できる
・電子レンジや電気ケトルを使い、簡単に料理を温められる
・冷蔵庫に給電し、食品の腐敗を防ぐ
・停電情報を調べるためのスマホを常にフル充電にしておける
・LEDライトを点灯させて、夜間に暗闇を照らせる
・電動除雪機を使い、簡単に除雪作業が行える
雪の日に使用するポータブル電源は、創業から13年間で世界販売台数500万台を突破した実績を誇るJackery(ジャクリ)製品がおすすめです。業界トップクラスのコンパクト・軽量設計なので、持ち運びの負担になりません。
BMSとNCM制御機能が発火や火災を防ぎ、屋外で使用しても安全です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しているので、10年以上も活躍します。
8.雪の日に最適!100均の輪ゴムで滑り止め靴の作り方
急な雪で外出が心配な場合には、100均の輪ゴムで簡単に滑り止め効果のある靴を作れます。作り方のポイントは以下のとおりです。
・足の指の付け根から足の甲の間に輪ゴムを巻く
・輪ゴムは幅の太いものを使う
・滑りにくさを高めるために2~3本程度の輪ゴムを巻く
輪ゴムを複数本巻くことでゴム特有のグリップ力を持たせることができ、防滑力を高める溝を作る役割も果たせます。また、ゴムの幅が広いほど地面との接地面が広くなるので、安定性を高めることができます。幅広のゴムを購入しておくと、急な雪の日にも安心ですね。
9.100均の滑り止めだけでは不十分!雪道用の靴の選び方
100均の滑り止めは簡易的なものが多いため、劣化や粘着力の低下によって効果が衰えやすく、雪のシーズンを乗り切るには不十分です。そのため、雪道用の靴を1足準備しておくと安心できるでしょう。雪道用の靴を選ぶ際のポイントを解説していきます。
●ラバーソールを選ぶ
雪道用の靴を選ぶ際は、ラバーソールの靴を選びましょう。ラバーソールは摩擦力が高く、滑りにくい素材だからです。柔軟性も高く、凍りついた路面でもグリップしてくれます。天然ゴムや合成ゴムを使用したソールなら、雪で硬くなりにくいのでおすすめです。
●EVA・TPU素材のソールを選ぶ
雪道には、EVA(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)やTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)素材でできた、弾力があり柔らかいソールの靴も適しています。EVAはスニーカーのミドルソールに使われるような柔らかい素材で、幅広い靴に使われている素材です。
TPUはゴムとプラスチックが持つ硬さを持ち、サッカーのスパイクのように耐久性が必要な靴に使われている素材です。この2つの素材でできたソールの靴はグリップ力があり、滑りにくいといえるでしょう。
●深い溝がついている靴を選ぶ
雪道を歩く際は、靴底に深い溝がついているものを選んでみてください。深い溝が滑る原因となる雪や水を逃がしてくれ、滑りにくくなります。
また、溝のパターンが複雑なものほど水を逃がしやすく、地面と接する面を増やしてくれます。なかでもギザギザパターンの溝はグリップ力が高く、おすすめです。
まとめ
雪道で安全に歩くには、靴底に滑り止めをつけたり、滑りにくい素材でできた靴を選んで対策すると良いでしょう。100均グッズは手軽に試せますが、住んでいる地域の降雪状況によっては、専門店や通販でも滑り止めグッズをチェックしておくと安心につながります。
この記事で紹介した滑り止め対策をとり、雪道で安全に歩けるよう試してみてください。









































































































































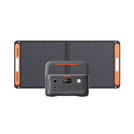


コメント