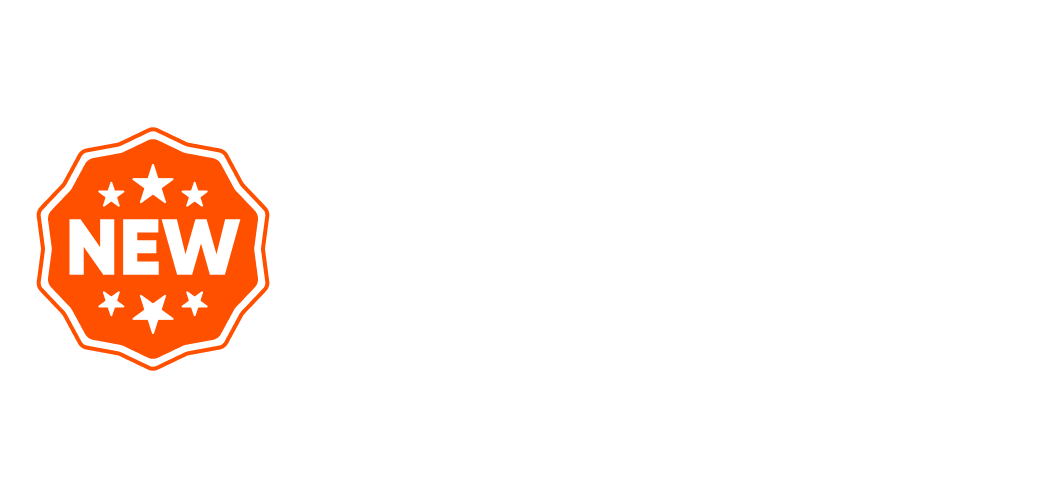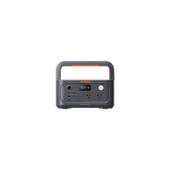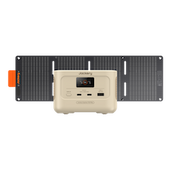1.首都直下型地震はいつ発生する?発生確率と最新シミュレーション
首都直下型地震の発生が予想される時期や被害の予測を、政府機関の最新データをもとに解説します。
●首都直下型地震の定義
首都直下型地震とは、東京都心や周辺を震源とするマグニチュード7クラスの大きな直下型地震です。震源が浅いため揺れのエネルギーが地表に伝わりやすく、人口の多い首都圏では甚大な被害につながる恐れがあります。
首都の機能が止まり、経済にも大きな影響を与える恐れがあるため、十分な備えが必要です。過去の関東大震災の経験を踏まえ、国は首都直下型地震を防災における課題のひとつと考え、備えを強化しています。
●発生確率は30年以内で70%!最新予測データから解説
地震調査研究推進本部は、首都直下地震が30年以内に70%起きると予測しています。2025年現在「首都直下地震はいつ起こるのか」との疑問に、専門家の分析から「いつ発生してもおかしくない」と指摘されている状況です。
現在の技術では正確な発生日時の予測はできません。70%という予測は明日起きても不思議ではなく、一方で数年、あるいは10年以上先に発生する可能性もあります。
発生時期を予測できないからこそ、常に備えを見直し、家族や地域での防災意識を高めておきましょう。
参考
内閣府|特集 首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)‐内閣府防災情報のページ
●最新の被害想定シミュレーションは死者約2.3万人・全壊焼失棟数約61万棟
内閣府が公表した首都直下型地震の被害想定シミュレーションは、以下のとおりです。
|
項目 |
想定 |
|
死者数(最大) |
約2万3千人 |
|
建物被害 |
全壊・焼失棟数:約61万棟 |
|
経済損失 |
約95兆円 |
|
ライフライン |
電力:発災直後に約5割の地域で停電 水道:都区部の約5割が断水 |
|
交通機関 |
地下鉄:約1週間運休 私鉄・在来線:約1か月運休 |
首都直下型地震が発生すれば、死者は最大約2万3千人に達し、建物は全壊・焼失棟数で約61万棟におよぶ予想となっています。経済損失は95兆円に上り、建物被害だけでなく、生産やサービスが止まることによる影響も甚大です。
首都直下型地震は生活や経済に影響を与えるため、日頃から備えて防災意識を高めましょう。
参考
内閣府|特集 首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)‐内閣府防災情報のページ
関連人気記事:首都直下型地震が来ない確率は?安全な県や助かるには何を対策すべきか解説
2.首都直下型地震の影響が少ない安全な県
首都直下型地震は主に首都圏に大きな被害を及ぼすとされ、遠方の地域は被害が軽くなると考えられます。ここでは、安全性が高いとされる県を確認しましょう。
●関東以外は影響が少ないとされる安全な県|北海道、長崎県など
首都圏から大きく離れた地域では、首都直下型地震による被害は限られています。被害が少ないとされる県の例は以下のとおりです。
・北海道
・長崎県
・熊本県
・福岡県
震源からの距離が遠く太平洋に面していないため、建物倒壊や火災、津波などの被害は低いと予想されています。
ただし、首都機能の停止により物流や金融システムが麻痺し、食料品や日用品の供給に支障をきたします。ほかにも広い範囲にわたる停電や交通網の混乱などにより、震源から遠い県でも経済活動に影響がおよぶでしょう。全国的な影響が長引くと考えられるため、どの地域でも最低限の備えは必要です。
●避難先・一時滞在先として考えられる安全な県|青森県、岩手県など
関東地方からアクセスしやすく、首都直下型地震の被害が小さいとされる東北地方は避難先の候補に挙がります。青森県や岩手県は首都直下型地震の影響を受けにくく、建物被害や火災の危険性が低いと考えられます。
安全な地域への避難を検討する場合は、以下の点を考慮しましょう。
・親族や知人宅を拠点として利用できるかを事前に確認する
・災害時は泊まる場所確保が難しくなるため、避難先の候補をいくつか探しておく
・交通機関の運行状況に影響されやすいため、複数ルートを想定する
「どこへ逃げ、どう移動するか」を事前に想定しておけば、いざというときの安心につながります。
関連人気記事:首都直下型地震は津波の心配がある?到達時間と範囲からわかる危険度と対策
3.首都直下型地震と南海トラフはどっちがやばい?発生時期と被害の違いを比較

首都直下型地震と南海トラフはどちらも高い発生確率で予想される大きな地震ですが、発生する時期や被害の特徴には大きな違いがあります。両者の違いを確認しましょう。
●首都直下型地震と南海トラフの発生確率と時期の違い
首都直下型地震は30年以内に70%、南海トラフ地震は70〜80%の確率で発生すると予測されています。発生する確率は近い数値を示していますが、どちらが先に起こるか判断できないのが現状です。
「首都直下地震と南海トラフはどっちが先」という疑問もありますが、専門家からも発生時期を断定する根拠は示されていません。
首都直下地震も南海トラフ地震も、いつ発生しても不思議ではない状況にあります。また、地震の活動は互いに影響し合うケースがあるため、どちらかの地震がもう一方を誘発するケースも想定しておくべきです。
「どちらが先か」ではなく「どちらにも備える」を意識し、命を守るための準備をしてください。
参考:内閣府|地震災害
●首都直下型地震と南海トラフの被害想定の比較
首都直下型地震と南海トラフ地震では、被害の規模と特徴が大きく異なります。主な違いは以下のとおりです。
|
項目 |
首都直下型地震 |
南海トラフ地震 |
|
死者数 |
約2.3万人 |
約32万人 |
|
全壊・焼失棟数 |
約61万棟 |
約239万棟 |
|
経済損失 |
約95兆円 |
約220兆円 |
|
被害の特徴 |
都市の機能が集中して麻痺する |
津波による広い範囲の大きな被害 |
|
影響範囲 |
首都圏を中心とした限られた地域 |
関東から九州まで広い範囲 |
首都直下型地震の被害は都市の機能が失われるのが大きな被害です。政治や経済の中心が集まる東京への打撃が深刻な問題となります。それに対し、南海トラフ地震は津波による広い範囲の甚大被害が特徴で、被害の規模は首都直下型地震を大きく上回る予想です。
首都直下型地震と南海トラフ地震は性質こそ違いますが、どちらが起きても深刻な影響は避けられません。状況に応じて柔軟に対応できるよう、防災への意識を高めてください。
参考
内閣府|特集 首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)‐内閣府防災情報のページ
内閣府防災情報|南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について
内閣府|平成26年版 防災白書|特集 第1章 2 首都直下地震及び南海トラフ地震
関連人気記事:南海トラフ地震はいつ起こる?生き残るために万全の対策をしよう
4.首都直下型地震で危ない県ランキング|被害想定データから解説
首都直下型地震による被害は震源地からの距離や地域特性によって大きく異なります。首都圏を中心に大きな被害が想定される県を確認しましょう。
●東京都23区が最も危険とされる理由|人口密集・建物老朽化
東京都23区は首都直下型地震で大きな被害が予想される地域です。人口が密集しており(約15,000人/km²)災害での避難と救助に支障をきたします。
とくに次の繁華街は、発災時に混乱が避けられない地域です。
・新宿
・渋谷
・池袋
また、老朽化した木造住宅が密集する地域では火災延焼のリスクが高く、東京都の被害想定では最大約11万棟の焼失が予想されています。
さらに、狭い道や古い建物の倒壊により消防車や救急車の通行が難しくなり、初期消火や救助活動が遅れるケースもあります。
人口の過密や老朽建築の課題に備えるには、住民一人ひとりが防災への意識を持つことが大切です。
参考
科学技術振興機構|M7級の首都直下地震で都内死者6150人 都防災会議が被害想定
●神奈川県(横浜・川崎)の危険度|人口規模と火災リスク
横浜市と川崎市は、東京都についで高い人口密度と都市機能が集まっているため、首都直下型地震で被害が予想されます。
横浜市の人口は約377万人、川崎市は約155万人と大都市圏を形成しており、発災時の避難者数は多くなるでしょう。。災害のリスクは以下のとおりです。
・高層マンションや住宅密集地が多く、火災時に延焼しやすい
・石油コンビナートや化学工場の出火・漏洩による二次災害の可能性がある
・港湾・空港・新幹線などのインフラが集中し、物流や交通へ大きな影響がある
住宅密集地や高層マンションが多いため延焼リスクが高く、工業地帯の石油・化学施設で二次災害が起こる恐れもあります。さらに港湾・空港・新幹線などの被害は首都圏の物流や交通に大きな影響をおよぼすでしょう。
参考
川崎市|川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和7年9月1日現在)
●埼玉南部・千葉西部の被害想定|住宅密集と液状化の懸念
住宅が集中する埼玉県南部と千葉県西部では、首都直下型地震で倒壊や火災の被害が想定されます。住宅密集地では火災が発生すると延焼しやすく、埼玉県では約1,500棟、千葉県では約8,100棟の火災での焼失が見込まれています。
また、埼玉県と千葉県の次にあげる地域は、液状化の危険が高い地域です。
・さいたま市
・川口市
・越谷市
・習志野市
・浦安市
・市川市
建物の沈下や道路の陥没など被害で、住民の生活が困難になる可能性があります。復旧作業の遅れにより、避難生活が長くなると予想されます。
火災や液状化の危険を正しく認識し、行政の対策に加えて住民も自主的な備えが必要です。
参考
千葉県の地震被害想定調査結果について(平成28年5月)|千葉県
5.首都直下型地震はいつ来るかわからない!助かるには備えが必須

首都直下型地震の発生する時期は予測できないため、日常の備えが命を守る力となります。日常生活のなかでできる防災対策を確認していきましょう。
●家具を固定し耐震対策で自宅の安全性を高める
地震による家具の転倒や建物倒壊から身を守るために、転倒防止器具による家具固定と耐震補強が欠かせません。
転倒防止器具を使用すれば、以下の家具や家電を固定できます。
・本棚
・食器棚
・テレビ
寝室では、寝ているときの事故を防ぐために重い家具を置かないか、置く場合は必ず固定してください。また、建物の耐震補強も生存率を向上させます。
1981年以前に建てられた住宅は旧耐震基準のため、耐震診断を受けて必要に応じて補強工事をおこなってください。
●家族で避難経路と集合場所を決めて共有する
災害時に家族を守るためには、避難ルートと集合場所をいくつか設定し、家族が全員で確認しておく必要があります。
自宅や学校、職場からの避難ルートを歩き、かかる時間や危険なポイントをチェックします。また、道路の陥没や建物が倒壊して通行できない場合に備えて、必ず2つ以上のルートを用意してください。
家族の集合先には公園や学校などのわかりやすい場所にして、全員で場所と行き方を確認すると安心です。
●水・食料・電源など最低限の防災グッズを準備する
ライフライン停止に備えて、最低でも3日分、できれば1週間分の防災グッズを備蓄しておく必要があります。
準備しておくものは以下のとおりです。
・飲料水(1人あたり1日3リットル)
・保存食(缶詰、レトルト食品など調理不要で栄養価の高いもの)
・医薬品(常備薬・救急用品・衛生用品など)
・モバイルバッテリーやポータブル電源(停電時の通信手段や照明の確保)
とくに停電が長くなると予想される首都直下型地震では、大容量のポータブル電源があると避難での生活が安全で快適になります。日頃から必要な防災グッズを揃えておけば、首都直下型地震のような大きな災害でも落ち着いて行動ができるでしょう。
6.首都直下型地震に備えるならJackery(ジャクリ)「ポータブル電源」がおすすめ!

首都直下型地震の長い停電に備える非常電源を選ぶなら、Jackery(ジャクリ)のポータブル電源をおすすめします。ポータブル電源とは、大容量のバッテリーを内蔵した持ち運び可能な蓄電装置で、コンセントのない場所でも家電製品を動かせるアイテムです。
Jackery(ジャクリ)は世界累計500万台以上の販売実績を誇る信頼性の高いブランドです。震度7の揺れにも耐えられる耐震試験に合格しており、地震による本体の損傷リスクを軽減できます。最大5年の無料保証が付いているため、購入後は安心して使用できるでしょう。
さらに、業界最高峰のソーラーパネル変換効率(最大25%)によって、停電が長期化しても太陽光で電力を確保できる点が魅力です。
災害への備えとしてJackery(ジャクリ)のポータブル電源を準備し、停電時でも安心して過ごせる環境を整えてください。
7.首都直下型地震についてよくある質問
首都直下型地震についてよく寄せられる質問とその答えを紹介します。
●首都直下型地震はなぜ「日本終了」と表現されるのか?
首都直下型地震が「日本終了」と表現される理由は、被害が日本の政治・経済・社会の中枢を直撃し、国の機能がとまる可能性があるためです。
東京には、以下のような政治・経済の中枢があり、被災すると国の意思決定や経済活動が停止します。
・政府機関
・日本銀行
・主要企業の本社
・証券取引所
さらに、首都圏の物流や通信機能が失われれば、流通や情報のやりとりが滞り、地方経済にも影響がおよびます。国際的な信用失われ外国からの投資撤退や円安が進行し、日本全体が混乱する恐れがあるのです。
●首都直下地震は来ない可能性もありますか?
起きない可能性はゼロではありませんが、30年以内に70%という予測から見ると、首都直下地震が発生する確率は高いです。
地震は予測ができず、実際より早まったり遅れたりする可能性があります。しかし「来ない可能性があるから備えなくてよい」という考えは危険です。
首都直下地震は時期を特定できない以上、私たちにできる対策は日常での備えをおこたらないことです。
まとめ
首都直下型地震から命を守るには、30年以内に70%とされる高い発生確率を踏まえ、事前の備えが必要になります。最大約2万3千人の死者と約61万棟の全壊・焼失が想定されており、発生する時期は予測ができません。
東京23区はリスクが高い地域とされており、神奈川や埼玉南部・千葉西部でも大きな被害が予測されています。家具固定と耐震補強や最低でも3日分の防災グッズを準備するなど家族で対策をとってください。
地震が発生した後の停電に備えて、Jackery(ジャクリ)のポータブル電源を用意し、災害時も安全に過ごしましょう。