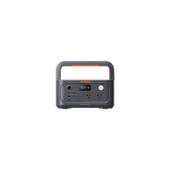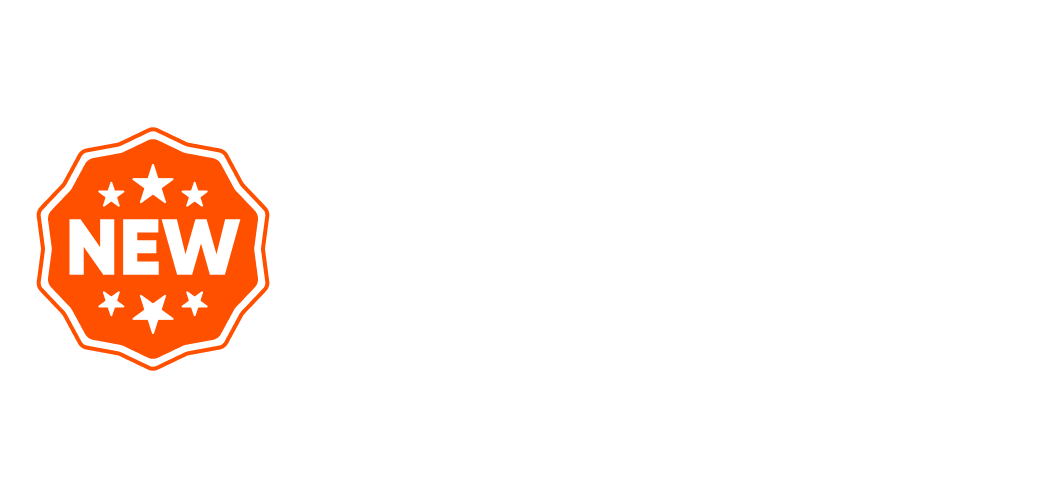1.余震とは大地震の後に続けて起こる地震のこと
まずは地震と余震についてよくある疑問にお答えします。
・余震はなぜ起こるの?
・余震がくるのは何分後?いつまで起こる?
・地震の余震が本震より大きいことはある?
大地震の後に続けて起こる余震は、決して被害の小さいものではありません。むしろ、状況によっては被害を拡大させる恐れもあります。余震について正しい知識を身に付けましょう。
●余震はなぜ起こるの?
余震が起こるのは、大地震が発生した地点の深い場所で力のつり合いが悪化するためとされています。
そもそも地震が起きる原因は、地下にあるプレート(巨大な岩盤)が押し合ったり引っ張り合ったりするからです。このプレートの跳ね上がりや破損時の衝撃によって、地震が発生します。動いたプレートが安定を取り戻そうとする過程で、余震が発生するという説が一般的です。
参考:気象庁「地震について」
●余震がくるのは何分後?いつまで起こる?
地震活動が収まって初めて「余震だと思っていた地震が、本当に余震だったのか」がわかります。つまり、余震が来るタイミングや収束するまでの正確な時間は予測できません。ただし、巨大地震が起きれば大きな余震が続きやすくなります。
例えば2004年に起きた新潟県中越地震では、震度7の地震発生から約1カ月もの間、震度5弱以上の地震が続きました。地震が起きた際は、余震がいつ起きてもいいように対策を心がけましょう。
●地震の余震が本震より大きいことはある?
余震が本震(※1)より大きかった事例として、熊本地震があげられます。2016年4月14日にマグニチュード(※2)6.5の地震が発生し、2日後の16日により強いマグニチュード7.3の地震が続きました。
※1:地震活動の中で最大規模の地震
※2:マグニチュードは地震の規模、震度は揺れの強さ
発生した地震が余震かどうかは判別できないため、より強い地震が起きる可能性はあります。迅速に避難して身の安全を守りましょう。
参考:気象庁「本技術報告における前震・本震・余震という用語について」
関連人気記事:地震による二次災害の一覧と対策とは?地震後の対応やペット対策も紹介
2.気象庁が「余震」という単語を使わなくなったワケ

現在「余震」という単語は、防災情報発信の際に使われていません。余震という言葉には、最初に起きた地震よりも大きい地震が発生しないイメージがあったためです。
熊本地震の発災時には、最初の大地震から2日後により大きな地震が発生しています。この事例から大地震発生時には、危険性を正しく注意喚起するため「最初の大地震と同程度の地震」という言葉を使うようになりました。
参考:地震調査研究推進本部事務局「「大地震後の地震活動の見通しに関する情報のあり方」の公表にあたって」
3.地震活動の3種類のパターン
地震活動は以下の3つのパターンに分けられます。
・本震-余震型
・前震-本震-余震型
・群発的な地震活動型
それぞれ詳しく解説します。
①本震-余震型
本震-余震型は、特に起きやすい地震のパターンで次の傾向があります。
・本震直後に余震が発生しやすい
・時間経過で頻度が下がっていく
・余震の規模は基本的に小さい
規模は小さくなりやすいのが特徴ですが、発生頻度は高めです。また、大地震が起きれば同じくらいに強い地震が起きる可能性はあります。大地震が起きたときは、再び強い地震が起きることを想定しなければなりません。
②前震-本震-余震型
前震-本震-余震型は、本震前に規模が小さい地震が起きるパターンで、熊本地震がこれに当たります。
また、余震が長期間起き続けた東日本大震災を前震-本震-余震型とする説も。本震から1年以上余震が続き、最大で震度6の地震が起きています。
参考:気象庁「本技術報告における前震・本震・余震という用語について」
③群発的な地震活動型
このパターンは明確に断定できるものではなく、激しい地震と穏やかな地震を一定期間繰り返す傾向にあります。
一例としてあげられるのは、1965年から数年間に渡って起き続けた「松代群発地震」です。体で感じられる震度の地震が6万回を超え、最大規模はマグニチュード5.4に達しました。
群発地震は火山の近くで起きやすいとされますが、火山がどう関係しているかは判明していません。
関連人気記事:地震の種類と特徴は?発生原因はプレート?揺れ・大きさもわかりやすく解説
4.過去に起きた大地震の余震事例

過去には以下の3つの巨大地震で、強い余震が発生しました。
・東日本大震災の余震
・熊本地震の余震
・台湾地震の余震
日本以外の事例も解説します。
●東日本大震災の余震
東日本大震災においては、次の規模で余震が起きています。
・余震活動期間は1年以上
・幅200km、長さ500kmの広範囲
・マグニチュード5以上の余震活動が8カ月以上
本震による大津波以外にも、盛土で作られた土地が長期間の余震によって崩落する事故も多発しました。6,531件調査した土地のうち、1,456件もの場所が倒壊するリスクがあると判断されています。
●熊本地震の余震
熊本地震は、4月14日から8月31日まで震度5弱以上の地震が続きました。最後の強い地震は前回から2カ月以上経ってから発生し、忘れたころにやってくる地震の怖さを伝えてきます。具体的な地震の規模は以下のとおりです。
・最大震度7の地震が2回
・震度6弱以上の地震が7回
・余震の発生回数は4,364 回
震度7の地震が2回も起きたのは、熊本地震が観測史上初めてです。
なお、大規模地震にもかかわらずライフラインは迅速に復旧されました。電気は18日午後に、ガス・水道も4月30日に復旧しています。地震発生後の支援は、スムーズにおこなわれたと言えるでしょう。
●台湾地震の余震
2024年4月3日にマグニチュード7.2の地震が起きた台湾では、同年中にM5.5以上の地震が42回発生しました。被災者数は1,183人に上り、日本の沖縄やフィリピンでも津波警報が発令されています。
また、2025年1月21日にもM6.4の強い地震が発生。「今まで経験した中でもっとも強い地震だ」とコメントする被災者もいます。
なお、建物の壁の倒壊やケガ人多発などの被害がありますが、さらに強い地震が起きるという意見もあります。日本にも津波が押し寄せる可能性もあるため、地震の情報を常にチェックしましょう。
参考:フォーカス台湾「2024年の台湾、М5.5以上の地震多発 5日までに42回」
5.前震と本震の見分け方は無し!地震から助かるための対策7選

前進と本震は見分けられず、地震活動が収まって初めて地震のパターンが分類されます。地震から助かるためには、以下の対策を普段から実践することが効果的です。
・防災グッズを揃える
・ポータブル電源とソーラーパネルを用意する
・安否確認方法を用意する
・非常食を1週間分用意する
・家具を固定して転倒を防止する
・災害支援ステーションの場所を把握する
・ハザードマップで安全な場所を調べておく
内閣府の記録によると、過去に起きた南海トラフ大地震の翌日に強い余震が起きた事例もあります。いつ地震が起きても行動できるように、地震対策を充実させましょう。
参考:内閣府「南海トラフで過去に発生した大規模地震について」
①防災グッズを揃える
地震発生時の安全性を高める方法として、以下の防災グッズが有効です。
・マスク
・下着や衣類
・ずきんやヘルメット
・懐中電灯やLEDランタン
・携帯ラジオ
・救急用品
・歯ブラシや歯磨き粉
・ウェットティッシュ
・石けんやハンドソープ
マスクや石けんなどの衛生用品は、感染症や体調不良の抑止に効果があります。軽視されがちですが、虫歯や歯周病を防ぐためにも、歯ブラシ・歯磨き粉は欠かせません。
また、非常用の明かりを用意するなら、Jackery(ジャクリ)が販売している充電式LEDランタンがおすすめ。USBポートが備わっているため、スマホやタブレットを充電できます。防災グッズを揃えて、地震対策を万全にしましょう。
②ポータブル電源とソーラーパネルを用意する
ポータブル電源とソーラーパネルは、停電が起きやすい地震への対策に欠かせません。ポータブル電源は携帯式のバッテリー装置で、モバイルバッテリー以上の大容量と高出力が強みです。例えばJackery(ジャクリ)の小型モデルと大容量モバイルバッテリーを比べると、スマホの充電回数で以下の差があります。
・20,000mAh(約74Wh)のモバイルバッテリー:約3~5回
・Jackery ポータブル電源 240 New(256Wh):約11回
小型モデルでも、スマホの充電回数はモバイルバッテリーの約2~3倍。ソーラーパネルもあれば、旅行先や避難所でもポータブル電源を充電できるため、長期間の停電に対応可能です。
また、より大きなモデルなら冷蔵庫や電子レンジを動かすこともできます。地震が起きても普段の生活を維持する方法として、ポータブル電源とソーラーパネルがおすすめです。
③安否確認方法を用意する
大切な人の生存が確かめられるように、複数の安否確認方法を用意しておきましょう。地震発災時は通信回線がパンクしやすく、携帯がつながらない可能性があります。例えば、確実に安否を確認するなら以下の方法が有効です。
・災害用伝言ダイヤル
・災害用伝言板(web171)
・携帯電話会社ごとの災害用伝言板サービス
・LINE
・公衆電話
・避難所の掲示板
以上の方法は、すべて緊急時に無料で利用できます。回線の混雑やスマホのバッテリー切れなどの事態でも、連絡が取れるようにしましょう。
参考:NTT東日本「災害用伝言板(web171)ご利用方法」
④非常食を1週間分用意する
農林水産省が推奨する非常食の量は1週間分です。緊急時は人命救助やライフラインの復旧が優先され、支援物資が届くまでは3日ほど。ただし、道路や被害の状況によってはさらに日数がかかります。
支援が遅れても健康を保つための非常食としては、以下の例がおすすめです。
・食パン・シリアル
・レトルトご飯・アルファ米
・カップ麺・うどん・パスタ
・肉類・魚類の缶詰
・牛丼・カレーなどのレトルト食品
・日持ちしやすいバナナやりんご
・飴・せんべい・チョコレートなどの菓子類
体調を崩しやすい人や食べ物にアレルギーがある人は、食事に気を配る必要があります。日常的に非常食を食べ比べておけば、緊急時でも安全な栄養補給が可能です。
⑤家具を固定して転倒を防止する
地震による被害は、家具の転倒に巻き込まれる割合が30~50%。家具をしっかり固定することで、倒れたタンスに巻き込まれたり玄関への道が塞がれたりするリスクを抑えられます。
参考:東京都総務局総合防災部防災管理課「自宅での家具類の転倒・落下・移動防止対策」
家具を固定する方法として、以下の道具が効果的です。
|
対象の家具 |
道具類 |
|
タンス |
● ストッパー ● ポール式器具
|
|
食器棚 |
● 留め金 ● ワイヤー ● L字型金具 ● ガラス飛散防止フィルム |
|
テレビ |
● ワイヤー ● 粘着マット |
|
本棚 |
● ワイヤー ● L字型金具 ● ひも・ベルト |
|
窓ガラス |
● ガラス飛散防止フィルム |
|
冷蔵庫 |
● ワイヤー |
もし家具が倒れても被害が小さくなるように、背が低い家具を使うのもおすすめです。
参考:政府広報オンライン「災害時に命を守る一人ひとりの防災対策」
⑥災害時帰宅支援ステーションの場所を把握する
災害時帰宅支援ステーションは、災害が起きたときに徒歩で帰宅する人を支援する施設です。水・トイレ・休憩場所・道路や災害の情報などを提供してもらえるため、体を休めながら安全に帰ることができます。
災害時帰宅支援ステーションとして機能する施設の例は以下のとおりです。
・学校
・コンビニ
・ファミレス
・ガソリンスタンド
地震が起きれば道路や建物が壊れ、危険な道での徒歩を強いられるかもしれません。「災害時帰宅支援ステーション 市町村名」で検索して、施設の場所を調べておきましょう。
参考:内閣府(防災担当)「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」
⑦ハザードマップで安全な場所を調べておく
ハザードマップは、お住いの区域における危険性・安全性を網羅している地図です。これを見れば、近くの避難所や安全な避難経路を調べられます。
国土交通省が公開しているハザードマップポータルサイトは、市町村名を入力すれば一目で災害情報を把握できるものです。ただし、最新の災害情報については、各市町村が作成する地図のほうがより詳しく載っています。
参考:国土交通省 水管理・国土保全局 防災課「ハザードマップポータルサイト」
関連人気記事:小さい地震が頻発すると危険?大地震の主な前兆や今すぐ必要な対策も紹介
6.地震の停電対策に必須!ポータブル電源ソーラーパネルのセット
大地震が発生すれば、停電や断水が長期間続く可能性があります。ライフラインの復旧まで耐える方法として、携帯性に優れたポータブル電源とソーラーパネルのセットがおすすめです。
ポータブル電源だけでも、数日間スマホやタブレットなどを充電可能。ソーラーパネルがあればポータブル電源を充電できるので、ライフラインの長期間停止への対応力が頼もしくなります。
AC電源(コンセント)も対応しているため、USB機器から一般的な家電まで幅広く動かせるのも特徴です。一例として、当社の「Jackery ポータブル電源 2000 New」の家電の稼働時間をまとめました。
・扇風機(30W):54.5時間
・電気毛布(55W):25時間
・車載冷蔵庫(60W):72時間
・電子レンジ(500W):3.3時間
・電気ケトル(850W):2時間
※稼働時間はおよその目安
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源は、13年間で500万台以上売り上げた実績があります。また、能登半島地震や大雨の被災地に支援物資として提供されたこともあり、地震対策としての信頼性はバツグンです。
気象庁の想定によれば、南海トラフの巨大地震が30年以内に起こる確率は70~80%。次の大地震が今日明日に襲ってくるかもしれません。地震がいつ起きても生活を維持できるようにしたい人は、ポータブル電源とソーラーパネルのセットを1台備えておきましょう。
もっと多くの商品を見る
まとめ
この記事では、地震と余震の関係に加えて7つの地震対策を紹介しました。大地震が起きたとき、余震がどれだけ続くかは予測できません。地震活動が収まった段階でデータを分析し、初めて地震活動のパターンを当てはめることができます。
地震の被害を避けるためには、日々の対策が不可欠。ポータブル電源とソーラーパネルなどの防災グッズを揃え、地震対策に力を入れましょう。