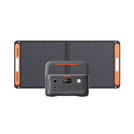1.地震速報の誤報が起こる原因
地震速報でなぜ誤報が出るのかは、複数の要因が関係しています。ここでは、代表的な5つの原因についてわかりやすく解説します。
●観測データが少なく誤差が出た
地震速報は、震源に近い地震計のデータをもとに自動的に解析されています。したがって、観測点が震源から遠かったり数が少なかったりすると、地震の規模や位置を正確に把握できず誤報につながるケースがあるのです。
地震速報の精度は観測網の密度に大きく依存しており、震源が海底など観測点の少ない地域で発生した場合、震度予測が大きく外れる場合がある点に留意しておきましょう。
●地震観測網が遠く誤差が出た
観測網の距離が、震源地から遠い場合も誤報の原因となります。例えば、観測点が本州に集中していて遠く離れた海域で地震が起きた場合、初期データの取得が遅れ、誤った震度や到達時間が予測される場合があるのです。
遠方の地震では震源の深さや規模を正確に把握しにくいため、速報の精度が低下するのはやむを得ない面があるといえます。
●複数の地震を1つと誤認した
地震速報の誤報では、下記を1つの大地震と誤認してしまうケースもあります。
・短時間に複数の地震が連続して発生する「群発地震」
・規模の大きい「本震」
・大地震のあとに続いて起こる小地震「余震」
システムは最初の揺れをもとに地震の規模を推定するため、次に発生した本震の揺れが大きくても見落とされたり、逆に余震が大きく見積もられたりする場合があるのです。
●地震以外の揺れを検知した
地震速報システムは「強い揺れ」を検知するよう設計されていますが、必ずしも自然の地震だけを感知するとは限りません。例えば、大規模な工事や爆発などで異常な揺れを感知し、地震と誤認するケースがあります。
実際、2016年には東京湾で大地震が発生したとする緊急地震速報が出されたことがありました。落雷による衝撃を地震計が誤って検知したのが原因で地震は起きておらず、直後に取り消されています。ただし、横浜市営地下鉄で列車が一時停止するなどの影響が出ました。
参考:日本経済新聞|気象庁「東京湾で震度7」、直後に取り消し
●地震システムが誤作動を起こした
地震の誤報では、人為的なミスやシステムエラーも無視できません。地震観測・解析システムは日々改善されていますが、予期せぬバグや機器の不調が原因で、誤った解析結果が出される場合があります。
例えば、過去にはプログラムのバグで、正しい観測値が送信されずに誤報につながった例がありました。
参考:朝日新聞|震度7の誤報は「プログラムのバグ」 気象庁長官が振り返る地震対応
2.地震が発生しても速報が出ない原因

地震が発生しても速報が発信されないのには、いくつかの理由があります。ここではおもな原因と、それぞれの背景について見ていきましょう。
●震度1未満だった
実際に地震が発生しても、震度が1未満だと基本的に速報は出ません。気象庁の緊急地震速報は、下記の場合に配信される仕組みになっています。
・震度5弱以上
・震度3以上の強い揺れが予想される地域
つまり、体に感じにくいごく弱い地震では、速報自体が発信されないわけです。なお、震度が1未満で速報を出さないのは、過剰な警報による混乱を防ぐのが目的である点を理解しておきましょう。
●震源の近くだった
震源に近すぎる場合、揺れが始まってから速報が届くまでの時間が間に合わない場合があります。地震速報は最初の「P波」を検知したら、遅れてくる「S波」が到達する前に発信されます。震源地が近いと両者の時間差が短く、警報よりも先に揺れが届いてしまうのです。
つまり、揺れ始めた時点で間に合っていないわけですが、技術的な限界によるものなので現時点では避けがたい現象といえます。
●速報が間に合わなかった
緊急地震速報は、地震発生直後に基準の予測震度を下回っていると発表されません。ただし、その後に大きな揺れが観測されてから、速報が発表されるケースがあるのです。
地震の規模や震源の深さ、観測網の位置などの条件によっては解析に時間がかかり、速報が最初の地震から数十秒遅れて発表される場合もあります。
●スマホの受信設定がOFFだった
見落としがちですが、スマホや携帯電話の緊急地震速報の設定がオフになっている場合があります。オフになっていると緊急地震速報を受信できないので注意しましょう。
また、電波状態が悪い場所では通知自体が届かない可能性があります。とくに、スマホや携帯電話を買い替えた際には設定を確認してみてください。
3.緊急地震速報が誤報だった事例の一覧
緊急地震速報では、過去には「誤報」と呼ばれる事例も発生しています。ここでは、実際に発生した事例を見ていきましょう。
●静岡県の伊豆で発生した地震の誤報
2025年4月17日に、静岡県東伊豆町で震度7とする緊急速報が誤って送信されました。防災システム研修中の人為的な操作ミスでエリアメールを送信した事例であり、地震は発生していませんでした。
参考:NHK 静岡 NEWS WEB|静岡 東伊豆町 「震度7発生」エリアメール誤って送信
●能登半島で発生した震度7の誤報
2024年1月1日、石川県能登地方で最大震度7とする速報が一時発表されました。あとで誤報と判明し、約9分後に実際の観測震度は最大震度3であったと発表しています。システムのメモリに、過去の震度情報が誤って流出したのが原因でした。
参考:朝日新聞|震度7の誤報は「プログラムのバグ」 気象庁長官が振り返る地震対応
●2016年8月1日に発生した震災レベルの誤報
2016年8月1日、関東地方を震源とする規模の大きな「震災レベル」の緊急速報が誤って発表されました。解析システムが複数回発生する弱い地震を同時解析し、誤って大規模地震と判断されたのが理由です。
参考:ウェザーニュース|緊急地震速報の気象庁誤報 なぜこうなったのか?
●2013年に奈良県で地震が発生するとの誤報
2013年8月8日、奈良県で震度7相当の地震があるとの速報が出ましたが、実際には揺れの観測はありませんでした。三重県沖にある、海底地震計の電気信号トラブルが原因で誤報につながったと発表しています。
参考:日本経済新聞|「最大震度7」と誤報 緊急地震速報で気象庁
4.今日や昨日の緊急地震速報の誤報はどこで確認できる?
緊急地震速報の真偽を知りたい場合は、気象庁の「緊急地震速報のお知らせ」を確認しましょう。速報の誤報や取り消しに関する情報を随時掲載しており、発表日時・対象地域・理由などが明記されています。
「速報が鳴ったのに揺れなかった」「周囲が騒いでいない」と感じたときは、事実を確認してみてください。
5.地震が誤報でも正確な情報収集・行動が大切

地震速報が誤報だったとわかっても、油断するのは禁物です。ここでは、地震速報が出されたときに取るべき行動を解説します。
●身の安全を確保する
地震速報が出されたら、第一に自分や家族の身を守ることを最優先に行動してください。例えば、速報が鳴ったら下記のような行動を意識しましょう。
・すぐに机の下にもぐる
・頭を守る
・家具の近くから離れる
地震が誤報であっても、安全確保の基本動作を迷わず実行することが命を守るために大切です。
●揺れがおさまったら避難する
もし実際に揺れを感じた場合は、揺れがおさまってから落ち着いて避難行動に移る必要があります。安全を確認し、ガスの元栓を閉めたり火の元を確認したりしながら、速やかに建物の外に出る準備を整えましょう。
地震が誤報でも避難経路を意識する、非常口の場所を再確認するといった行動を習慣化することが重要です。
●情報収集や状況確認をおこなう
緊急地震速報の信ぴょう性を確認するためにも、正しい情報収集を心がけましょう。気象庁の公式サイトや自治体の防災アプリなどを活用し、地震の発生状況や震源地、震度などを確認してください。
なお、SNSは誤情報や憶測が拡散されやすいため、必ず一次情報をチェックして裏取りすることが大切です。また、自宅や職場の被害状況もあわせて確認し、必要に応じて通報や連絡もおこないましょう。
●万一に備えて防災グッズを用意しておく
地震に備えて、防災グッズを用意しておきましょう。最低限、非常持ち出し袋に下記のようなものを準備しておくのがおすすめです。
・飲料水
・非常食
・モバイルバッテリー
・ラジオ
・懐中電灯
・予備の乾電池
特に、乾電池は日常的にも使えるアイテムなので必ず用意しておいてください。また、しばらく停電が続く事態を想定し、家電製品への電力供給やスマホの充電に役立つポータブル電源(大容量の持ち運び式蓄電池)も便利です。
関連人気記事:地震が起きたらどこに逃げる?それぞれの場所の安全ゾーンと取るべき行動
6.地震に備えてJackery(ジャクリ)のポータブル電源を用意しておこう

地震などの災害時は、停電によって家電製品の使用やスマホの充電ができなくなるリスクがあります。そんなときに活躍するのが、世界中で信頼されているブランド「Jackery(ジャクリ)」のポータブル電源です。
コンセントやUSBポートを備えているのはもちろん、コンパクトながら大容量なのが特徴。スマホの充電だけでなく、冷暖房から調理器具まで動かして、停電中もいつもと同じ生活ができる安心が手に入ります。ソーラーパネルと組み合わせれば長期停電にも対応可能です。
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源は過充電・過放電・発熱を防止できる「BMS(バッテリーマネジメントシステム)」をしっかりと備えた安全性の高さも魅力。非常時の備えとして、活用してみてはいかがでしょうか。
7.地震の誤報に関するよくある質問
地震の誤報に関するよくある質問と回答をわかりやすくまとめました。同様の疑問があれば、解決しておきましょう。
●緊急地震速報のアラート誤報が自分だけのケースはある?
基本的に「自分だけに緊急地震速報の誤報が届く」というケースはありません。緊急地震速報はエリア単位で配信され、同じ地域にいる人へ一斉に通知が届く仕組みになっています。
ただし、以下のようなケースでは「周囲には通知が届いたのに、自分のスマホだけ鳴らなかった」ということは起こり得るので注意しましょう。
・通知設定がオフになっていた
・携帯電話の電波の圏外にいた
・一時的に電波干渉があった
また、地下鉄やビルの中など、通信環境が不安定な場所にいると通知を受け取れない場合があります。大地震の速報を見逃してしまうリスクを防ぐためにも、端末の設定や電波状況を定期的に確認しておくことが大切です。
●緊急地震速報の正確性はどれくらい?
緊急地震速報の正確性は、緊急地震速報評価・改善検討会 利活用検討作業部会によると80%程度と発表されています。90%を超えるケースもあり、非常に高い精度であるといえるでしょう。
ただし、地震の発生場所や状況によっては、誤差が生じる場合もあります。とくに、震源が海底や観測網から遠い場所で発生したケースでは、データが不十分で速報が不正確になりやすい点に留意しておきましょう。
緊急地震速報は「完璧な予測」ではなく、あくまで「目安」として受け止める意識が大切です。
参考:緊急地震速報評価・改善検討会 利活用検討作業部会(報告書)図表集
●緊急地震速報がはじまった理由は?
緊急地震速報は、地震被害の軽減を目的に導入されました。初期微動の「P波」を感知し、遅れてくる「S波」が到達する前に人々に知らせることで、以下のような行動を促す狙いがあります。
・火を止める
・頭を守る
・安全な場所へ移動する
2007年に全国で運用が開始され、2011年の東日本大震災以降はさらにその重要性が認識されています。
●緊急地震速報の仕組みを教えて
緊急地震速報は、地震計が速いスピードで伝わるP波を感知した瞬間に作動する仕組みです。全国約690カ所の気象庁の地震計・震度計と、国立研究開発法人 防災科学技術研究所の全国約1,000カ所に設けられている地震観測網を利用しています。
震源の位置と地震の規模を即座に推定し、強い揺れが予想される地域に自動的に速報を配信するのが特徴です。コンピュータの性能の向上によって瞬時に計算ができるようになったことに加えて、1観測点のP波の観測データから震源やマグニチュードを推定する手法などを活用してすばやい速報を可能にしています。
●緊急地震速報の入手方法が知りたい
緊急地震速報は、下記の媒体などで受信可能です。
・スマートフォン
・テレビ
・ラジオ
・防災無線
スマホの場合は対応機種であれば、特別なアプリ不要で自動的に「緊急速報メール」として通知されます。ただし、受信設定がオフになっていると通知は届かないので注意しましょう。また、防災アプリや自治体の防災メールを併用すれば、速報以外の情報もタイムリーに入手可能です。
まとめ
緊急地震速報で誤報をゼロにできないのは、速報性と正確性の両立という難しい課題があるのが理由です。スマートフォンや携帯電話の設定を間違っていると通知を受けられないので、しっかり確認しておきましょう。
また、停電でスマートフォンを充電できず、情報収集が難しくなるリスクも避けなければなりません。ソーラー充電に対応しているJackery(ジャクリ)のポータブル電源を用意しておけば、災害時でも確実に電力を確保できます。
目的に合わせて容量や出力が異なる豊富なラインナップから選べるので、地震の備えとしてチェックしてみてください。