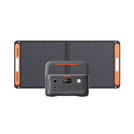1.屋根に設置する雪止めとは
雪止めとは、屋根からの落雪を防ぐため、軒先に近い部分に設置される部材です。屋根からの落雪による事故を防ぐためには、雪止めが欠かせません。雪止めは、豪雪地帯よりも年に数回雪が降る程度の地域で大きな効果を発揮します。
●屋根への雪止め設置に関する法律
屋根への雪止め設置に関して、明確に法律で定められているわけではありません。しかし、民法第218条では「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」とあり、落雪が間接的に法へ抵触する恐れがあるのです。
雪について明記されているわけではありませんが、雪は解けて雨水のように流れるため、隣家に雪が落ちる屋根だと、この法律に抵触するという見方ができます。
落雪が原因で人的・物的被害が発生するだけでなく、近隣トラブルが生じる可能性もあり、状況次第では賠償請求にまで発展する場合もあります。まずは、雪止めの設置に関する法律があると認識しておきましょう。
2.屋根に雪止めを付ける3つのメリット

屋根に雪止めを付けると落雪を防ぐことができ、通行人に被害が出たり、近隣住民とのトラブルが発生したりするのを防げます。また、雪止めを付けると、大雪が降った時でも家屋の出入口を確保できるというメリットもあります。
①人的・物的被害を防げる
屋根に雪止めをつける大きなメリットは、人的被害や物的被害を防げる点です。屋根からの落雪は、自分や家族、隣家の住民に被害をもたらす可能性があります。また、屋根の勾配や立地によっては、通行人に被害が出る場合があるため、雪止めで道路への落雪も防げます。
雨どいが破損したりカーポートが被害を受けたり、車がへこんでしまったりするなど、落雪による物的被害も、雪止めがあれば防げるでしょう。屋根へ雪止めをつけることは、さまざまな被害から守ってくれるメリットがあるといえます。
②近隣トラブルを防げる
落雪による近隣トラブルを防げるのも、屋根に雪止めをつけるメリットの一つです。屋根の勾配次第では、隣家の敷地内に雪が落ちてしまう可能性があるからです。
隣家の敷地内に雪が落ちてしまうと、家屋や庭木の枝、鉢植えに被害をもたらしてしまうかもしれません。弁償費用の請求など、場合によっては近隣トラブルに発展してしまう可能性があるため、雪止めの設置は近隣トラブルを防ぐのに役立つでしょう。
③出入り口を確保できる
雪止めを設置しておくことで、出入り口を確保できるのもメリットといえます。大雪になってしまった場合、屋根からの落雪が出入口をふさいでしまう事例も少なくありません。屋根雪がどこに落ちるかを予想して雪止めを設置すれば、出入口付近への落雪を防げます。
3.屋根に雪止めを付ける3つのデメリット
冬の雪害対策として屋根に雪止めを設置する家庭も増えていますが、便利な反面、デメリットも存在します。雪下ろしや耐震性、屋根材への影響など、事前に把握した上で雪止めの設置を検討しましょう。屋根に雪止めを付けるデメリットは、以下のとおりです。
①錆びが発生する
屋根に雪止めを設置する場合、錆びが発生してしまうデメリットがあります。雪止めは金属製のものが多いため、錆びの被害は避けられません。
錆びが発生すると雪止めがもろくなってしまうほか、家屋の外観を損なう原因にもなります。ステンレスやアルミなど、錆びにくい素材の雪止めを選ぶとよいでしょう。
②雪下ろしの邪魔になる
雪止めをつけると、雪下ろしの邪魔になるというデメリットもあります。雪下ろしは積もった雪を、屋根を滑らせて軒下に落とす作業です。そのため、雪止めがあると雪が落ちず、作業がスムーズに進まない場合があります。
さらに、雪下ろし作業の際にスコップが雪止めに引っかかり、危険な思いをしたという人も少なくありません。屋根に雪が多く積もる地方では、雪止めがかえって作業の邪魔になり、デメリットとなっています。
③耐震性に影響が出る
雪止めをつけるデメリットに、耐震性への影響が挙げられます。雪止めは金属製のものが多く、設置することで屋根が重くなり、住宅への負担も大きくなってしまいます。
築年数や、住宅が木造かどうかなどで耐震性への影響は異なります。専門業者に相談して、耐震性を保ったまま雪止めを設置してもらうとよいでしょう。
4.雪止めの設置が必要になるケース

屋根への雪止めの設置は義務ではありませんが、屋根の状態や家屋の周辺状況、気候次第では、雪止めの設置が必要となるケースもあります。しかし、雪国では雪が滑り落ちやすい屋根になっている場合が多く、雪止めを設置しない家屋の割合が高めです。
そのような状況の雪国でも、雪止めが必要になるケースについてまとめました。
●雪国でも雪止めが必要なケース
雪国では、雪下ろしの邪魔になったり、すが漏れによって漏水を引き起こしたりする可能性があるため、雪止めを設置しない場合が多くあります。
(すが漏れとは:雨漏りに似た現象で、室内の熱で解けた屋根雪が再び凍り、周りの雪解け水が屋根のつなぎ目から浸水する現象です。)
しかし、雪国でも以下のような家屋は雪止めが必要なケースといえます。
・近隣民家と隣接する家屋
・通路・道路に面している家屋
・軒先に雨どいのある家屋
屋根雪が落ち、通行人や隣人への人的・物的被害が想定される場合や、通路をふさいでしまう場合は、雪止めを設置します。また、屋根雪の重みで雨どいが破損するのを防ぐために、雪止めを設置する必要があります。
雪国でも、家屋の立地や周辺の状況によって雪止めが必要になると理解しておきましょう。
5.屋根に付ける雪止め金具の種類4選
屋根に付ける雪止め金具は、形状によって金具タイプ・アングルタイプ・ネットタイプに分けられます。雪止めを選ぶ際は、屋根の勾配や形状、素材に合わせて選ぶことが大切です。屋根に付ける雪止めとして代表的なものを紹介していきます。
①金具タイプ

金具タイプの雪止めは、L字型・おうぎ型・台形型・富士型などさまざまなタイプがあります。洋瓦・和瓦・平板瓦用など、屋根のタイプに合うものを選びましょう。金具タイプのなかには、ステンレス製のものやアルミ製のものなど、錆びにくいタイプもあります。
②アングルタイプ

長い棒で屋根雪をせき止めるように設置するのが、アングルタイプの雪止めです。金具タイプの雪止めよりも、広い範囲の落雪を防ぐことができます。雪が滑りやすい屋根や、降雪量の多い地域の屋根に設置するのがおすすめです。
③ネットタイプ

ネット部分をフェンスのように設置するものや、軒先にネット部分が当たるように設置するものがあります。どちらのタイプも屋根雪を落ちにくくする効果があります。太陽光パネルが設置されている屋根に取り付けられることが多い雪止めです。
④雪止め瓦

瓦自体に輪形や駒形の部分を設け、雪止めの効果をつけたものです。積雪時にかかる重さを考え、軒先ではなく壁がある位置に設置されます。積雪が多い地域では、雪止め瓦を屋根の中間部と軒先に近い部分に入れる場合もあります。
6.屋根の雪止め後付け工事にかかる費用
屋根の雪止めを後付けする際の費用としては、設置する雪止め金具などの料金と、足場代がかかります。以下に、雪止め金具を後付け工事で設置する際の費用相場をまとめました。
|
屋根の素材 |
価格相場(建坪30坪の一戸建ての場合) |
|
スレート |
6万~10万円 |
|
金属系(ガルバリウムなど) |
9万円~16万円 |
|
瓦 |
8万円~40万円 |
設置する金具の種類で設置方法も異なるので、費用にも違いが生じてきます。また、足場も家屋が何階建てかによって変わります。一般的な2階建ての一戸建てであれば、15万円前後の足場代がかかると想定しておきましょう。
7.雪害の備えにおすすめのJackery(ジャクリ)ポータブル電源

大雪によって起こりえる二次災害として、3日以上にのぼる大規模な停電が挙げられます。停電が起きている間も電気の供給を継続するためには、ポータブル電源が欠かせません。
ポータブル電源とは、内部のバッテリーに大量の電気を蓄え、コンセントが使えない状況でも電化製品に給電できる機器を指します。大雪による停電時に、ポータブル電源が活躍する場面は、以下のとおりです。
・電気毛布や電気ストーブを稼働し、常に快適な気温で生活できる
・電子レンジや電気ケトルを使い、暖かい料理を作れる
・冷蔵庫に給電し、食品の腐敗を防ぐ
・停電情報を調べるためのスマホを常にフル充電にしておける
・LEDライトを点灯させて、夜間に暗闇を照らせる
・電動除雪機を使い、簡単に除雪作業が行える
雪害対策として常備するポータブル電源は、創業から14年間で世界販売台数600万台を突破した実績を誇るJackery(ジャクリ)製品がおすすめです。業界トップクラスのコンパクト・軽量設計なので、持ち運びの負担になりません。
BMSとNCM制御機能が発火や火災を防ぎ、屋外で使用しても安全です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しているので、10年以上も停電対策として活躍します。
8.屋根に付ける雪止めに関するよくある質問
屋根に付ける雪止めについて、DIYで取り付け可能な雪止めはどのタイプなのか、屋根の材質にあう雪止めはどれかなど、疑問に思う人も多いでしょう。屋根に付ける雪止めに関するよくある質問と回答について、詳しく解説します。
●DIYで取り付け可能な雪止めと業者施工の違いは?
DIYで取り付け可能な雪止めは、金具タイプのものが当てはまります。金具タイプの雪止めにもさまざまな種類があるので、取り付け可能なものや配置について、まずは屋根の専門業者に相談してみるとよいでしょう。
しかし、DIYで取り付けをすると適切な箇所に設置できなかったり、うまく設置できず雨漏りが発生したりするリスクがあります。雪と一緒に雪止めが落ちてくる危険性もあります。
一方、業者による施工なら、屋根の形状に合わせ、適切な数の雪止めを適切な位置に設置してもらえます。積雪量や耐震性なども考慮してもらえるため、DIYで雪止めを取り付けるよりも満足度の高い仕事をしてもらえるでしょう。
屋根の勾配や雪止めの設置場所によっては、高所作業となる場合もあります。危険も伴うので、雪止め設置の経験豊富な業者に依頼することをおすすめします。
●金属屋根・瓦屋根・スレート屋根それぞれに合う雪止めは?
金属屋根・瓦屋根・スレート屋根に合う雪止めをまとめました。
・金属屋根・・・金具タイプかアングルタイプの雪止め
・瓦屋根(和瓦)・・・金具タイプ(富士型)の雪止め、雪止め瓦
・瓦屋根(洋瓦)・・・金具タイプ(おうぎ型)、アングルタイプの雪止め
・スレート屋根・・・金具タイプ(おうぎ型)、アングルタイプの雪止め
瓦屋根は、和瓦・洋瓦で雪止めのタイプが変わってきます。また、どの屋根のタイプでも、屋根の勾配や形状で落雪のしやすさは変わります。業者と相談しながら屋根につける雪止めを決めるのがおすすめです。
●北海道で屋根への雪止め設置は推奨されない?
北海道では、屋根への雪止め設置は推奨されていません。雪下ろしの際に雪止めに雪が引っかかったり、作業道具が引っかかったりして、作業の妨げになる可能性があるからです。
しかし、隣家に雪が落ちる可能性がある屋根や、車庫の上や通路にかかる屋根には、近隣トラブルや人的・物的被害を防ぐために雪止めの設置が推奨されています。
●雪止めをつけていても落雪するのはなぜ?
雪止めをつけていても落雪する理由は、以下の通りです。
・雪止めが適切な位置に取り付けられていない
・雪止め金具が屋根の形状に合っていない
・雪止めの耐荷重を超えて屋根に積雪している
・積雪量に対して雪止めの設置数が少ない
雪止めや屋根に関する知識のない人が雪止めをつけると、誤った位置に雪止めを設置してしまい、効果が発揮されない可能性が高くなります。また、落雪する可能性のある場所に適切に設置できなかった場合も、雪止めをしていても落雪してしまいます。
土地の気候に合わせた数の雪止めを設置することも大切です。費用を抑えるため、見込まれる積雪量に対して少ない雪止めしか設置していないと、落雪の可能性が高まります。
ただし、雪止めはあくまでも落雪を「防ぐ」ためにつけるものと理解しておきましょう。積雪状況は毎年変わるので、雪止めを設置したからといって、落雪が「ゼロ」になるわけではないと理解しておいてください。
まとめ
屋根からの落雪を防ぐ雪止めは、人的・物的被害や事故、近隣トラブルを防ぐメリットがあります。一方で、錆びや耐震性に影響を及ぼす可能性などのデメリットも否めません。
しかし、屋根に雪止めが設置されていれば大雪時に出入口を確保できるため、安心につながるというメリットもあります。
屋根の雪止めを設置し、落雪によるリスクを最小限にしてください。