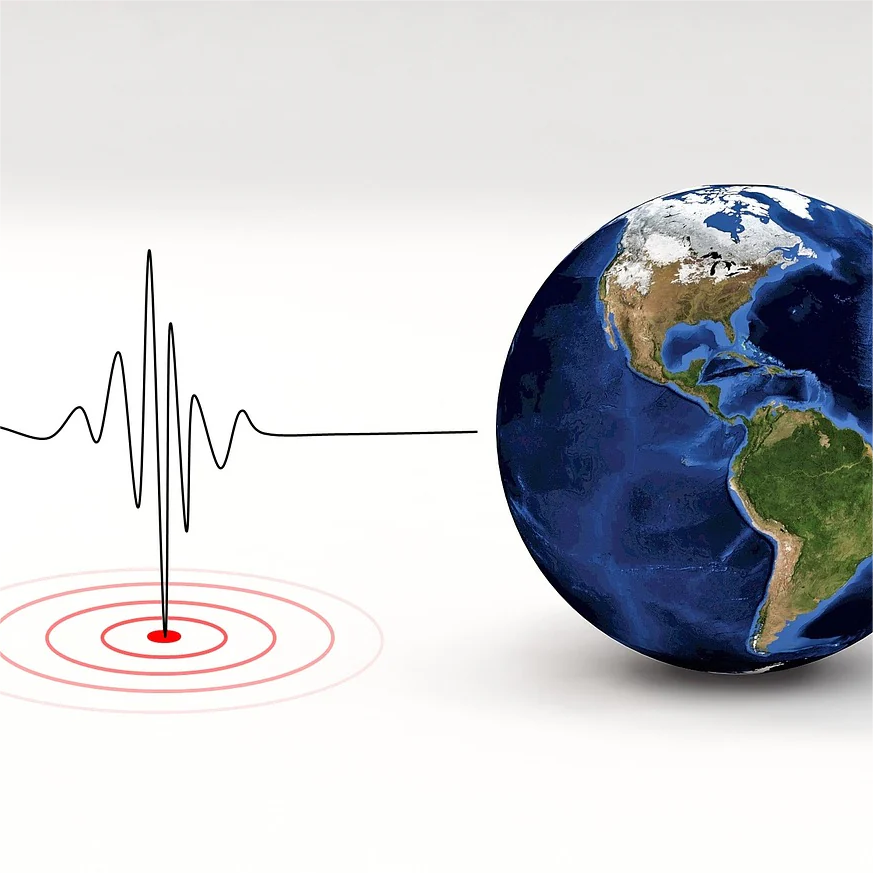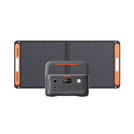1.南海トラフと鹿児島県トカラ列島近海の群発地震の関係性は?
鹿児島県トカラ列島近海では、2025年6月以降に大規模な群発地震が発生しています。群発地震と南海トラフ地震との関連性について、現在の状況と専門家の見解を確認しましょう。
●トカラ列島近海の群発地震|震度1以上の揺れが1年間で2,000回以上観測
2025年6月21日から2025年7月14日午前8時までに、トカラ列島近海で震度1以上の地震が2,006回という異例の頻度で発生しました。震度の内訳は以下のとおりです。
・震度6弱:1回
・震度5強:3回
・震度5弱:4回
・震度4:46回
・震度3:139回
・震度2:496回
・震度1:1,317回
群発地震の原因には、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む複雑な地殻構造が関係しています。さらに、能登半島地震のような流体プロセス(熱水・地下水・ガス・マグマ)の影響も考えられています。
海洋研究開発機構(JAMSTEC)は、マグマやガスの蓄積が地震活動に関与している可能性を示しました。群発地震は、住民の生活に大きな影響を及ぼし続けています。
参考
WEB防災情報新聞|日本列島の縮図?トカラ(悪石島、小宝島)の群発地震
JAMSTEC国立研究開発法人海洋研究開発機構|トカラ列島の火山について
●南海トラフ地震との関係性は明らかではない
トカラ列島の群発地震と南海トラフ地震の因果関係は科学的に証明されていません。気象庁南海トラフ地震評価検討会の平田直会長は「四国や本州まで影響を及ぼすとは考えられない」と述べています。
ただし、専門家の間では以下のような議論もされています。
|
項目 |
内容 |
|
専門家の見解 |
両方ともフィリピン海プレートの動きに関連している共通点がある |
|
過去の事例 |
熊本地震(2016年)や能登半島地震(2024年)の前にも、トカラ列島で群発地震が観測された |
|
一部の指摘 |
群発地震は大地震の前兆となる可能性があるという見方もある |
現時点では、トカラ列島の群発地震と南海トラフ地震との明確な関連性は確認されていません。しかし、過去の事例や専門家の指摘を踏まえると、今後の地震活動の推移を慎重に見守る必要があるといえるでしょう。
参考:NHK|南海トラフ巨大地震検討会“トカラ列島近海の地震の影響なし”
2.鹿児島で大地震(南海トラフ)が起きる可能性はあるのか?
鹿児島県は南海トラフ地震の影響を受ける可能性がある地域であり、活断層や火山活動に伴う地震など、複数のリスクが存在しています。それぞれの地震リスクを確認しましょう。
●鹿児島の主な活断層と震源域の特徴

鹿児島県には複数の活断層が存在し、マグニチュード6~7クラスの地震発生リスクを抱えています。県北西部を中心に、以下のような主要な活断層が分布しているためです。
・日奈久断層帯
・出水断層帯
・甑断層帯
・市来断層帯
とくに1997年の鹿児島県北西部地震(M6.6)は、薩摩川内市などで震度5強を観測し、負傷者や住宅の損壊が発生しました。東西方向の左横ずれ断層運動が特徴的で、震源が浅いため局所的に強い揺れが生じる可能性があります。
軟弱地盤の地域は揺れが増幅されやすく、液状化現象への対策も重要な課題です。
●南海トラフ以外の地震リスクと活断層の存在
鹿児島県は南海トラフ地震以外にも、内陸型地震と火山活動に伴う地震という2つの大きなリスクが存在します。2つの地震の内容を確認しましょう。
|
地震の種類 |
リスク要因 |
該当箇所 |
過去の主な事例 |
|
内陸型地震 |
活断層による地震 |
日奈久断層帯、出水断層帯など |
マグニチュード6〜7クラスの地震が発生 |
|
火山活動に伴う地震 |
火山の活動に伴って発生する地震 |
桜島、霧島山などの活火山 |
1914年 桜島地震(M7.1) 鹿児島市で死者13人 |
鹿児島県内には活断層が点在し、過去にM6〜7の地震が発生しています。1914年の桜島地震では死者13人が出るなど、火山性地震のリスクもあります。
火山活動と地震の同時発生といった複合災害の危険性もあり、南海トラフへの備えと並行して地域の特性に応じた対策が欠かせません。
●南海トラフ地震が鹿児島に及ぼす影響

南海トラフ地震が発生した場合、鹿児島県にも強い揺れと津波による深刻な被害が予想されます。県内42市町村が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定され、太平洋沿岸の8市町は「津波避難対策特別強化地域」にも指定されています。
過去の地震と津波被害の事例は、以下のとおりです。
|
項目 |
内容 |
|
津波被害事例 |
宝永地震や安政南海地震で、志布志湾に津波被害が起きたと推定される |
|
現在のリスク |
志布志湾沿岸を含む太平洋側は、南海トラフ地震による津波が直接到達する可能性が高い |
|
対策 |
津波からの被害を軽減するため、早期避難体制の整備が必要 |
また、軟弱地盤の地域では地震動が増幅されやすいため、建物の耐震化とあわせた防災対策が求められています。
参考
関連人気記事:南海トラフが起きても安全な県ランキング|前兆・備え・危険な県も徹底解説
3.南海トラフ地震で鹿児島に予想される震度と津波の被害
南海トラフ地震が発生した場合の鹿児島県への影響について、震度分布と津波の到達予測を詳しく解説します。
●南海トラフ地震発生時の鹿児島の予想震度|震度5弱〜5強が多い予想
鹿児島県の多くの地域で震度5弱から5強の揺れが予想されています。とくに震度が大きいとされる地域は以下のとおりです。
|
地域名 |
想定される震度 |
|
曽於市・志布志市 |
最大震度6強 |
|
大隅地域 (鹿屋市・錦江町・垂水市・曽於市・志布志市・肝付町・大崎町・東串良町・南大隅町) |
震度5弱〜6強 |
|
姶良・伊佐地域 (霧島市・伊佐市・湧水町・姶良市) |
震度6弱 |
軟弱地盤は揺れが強まり、肝属川周辺や沿岸部で液状化の恐れがあります。耐震性の低い木造住宅は倒壊の恐れがあり、築年数などによって被害に差が出ると予測されています。
●津波の高さと到達時間の予測|30〜60分で最大10〜11mの津波到達想定
鹿児島県では、大隅半島などの沿岸部に津波が押し寄せると想定されています。とくに屋久島町の沿岸は、地震発生から約49分後に高さ約11.89mの津波が到達する見込みです。
志布志市は津波が発生後35分で到達し、46分で最大となると想定されており、避難にかけられる時間はごくわずかです。
津波警報の発令を待つのではなく、強い揺れを感じたら直ちに高台へ避難しましょう。
参考:鹿児島県|被害シナリオ No.1 鹿児島県全体:⑦南海トラフ
4.南海トラフ地震で鹿児島はどこが危ない?
南海トラフ地震による鹿児島県への影響は、沿岸部の津波リスクと内陸部の震度被害に大きくわかれます。地域特性を理解して適切な備えを進めましょう。
●津波被害リスクの高い沿岸部(志布志湾・肝付町など)
太平洋に面した志布志湾沿岸や肝付町などの地域は、海抜が低く津波の影響を受けやすい地形的特徴があります。想定される地震・津波の情報は以下のとおりです。
|
地域名 |
想定震度 |
最大津波高 |
津波到達予測時間 |
|
志布志市 |
震度6強 |
6.40m |
地震発生から約35分後 |
|
肝付町 |
震度5強 |
8.38m |
地震発生から約29分後 |
参考:鹿児島県|被害シナリオ No.1 鹿児島県全体:⑦南海トラフ
とくに河口部や湾の奥では津波が遡上し、内陸部まで浸水する可能性があるため注意が必要です。強い揺れを感じたら、沿岸にいる人は迷わず高台へ避難してください。
●震度被害が想定される内陸部(姶良市・霧島市・鹿児島市など)
県内の以下の地域は、活断層と軟弱地盤のため震度5強〜6弱の強い揺れが予測されています。
・姶良市
・霧島市
・鹿児島市
都市部は建物倒壊に加え、交通網の寸断で救助や物資輸送が困難になるでしょう。霧島市は約70箇所の道路不通が想定されており、孤立地域の発生も予測されています。
病院や避難所として使われる公共施設の耐震性も大きな課題です。被害を抑えるには、平時からの対策と避難計画の確認が不可欠です。
参考:鹿児島県|被害シナリオ No.1 鹿児島県全体:⑦南海トラフ
5.鹿児島の地震や南海トラフに備える防災対策と避難準備
南海トラフ地震などの大規模災害に備えるため、防災対策と避難準備が重要です。具体的な対策を確認しましょう。
●避難ルートと集合場所を家族で決めておく
地震発生時の混乱を避けるため、家族で複数の避難ルートと集合場所を事前に決めておくことが大切です。昼夜問わず安全に移動できる経路を確認し、天候が悪い場合の代替ルートも想定しておきましょう。
以下のような家族がよくいる場所の、最寄りの避難所や高台への経路を共有します。
・自宅
・学校
・職場
鹿児島市では227か所の避難所が指定されており、津波避難ビルも68か所設置されています。実際に歩いて避難経路を確認し、所要時間や危険箇所をチェックしておくと安心です。
また、避難所の場所や設備を事前に確認しておけば、災害時の避難がスムーズになります。家族会議で定期的に避難計画を見直し、子どもにもわかりやすく伝えておきましょう。
参考:鹿児島市|かごしま市防災リーフレット~“知識”と“備え”で高まる防災力~
●災害情報の受信手段と持ち出し品の準備をする
災害時の正確な情報収集のため、複数の情報受信手段を確保しておきましょう。防災アプリや緊急速報メールなどで、避難指示や避難所開設情報をリアルタイムで受信できます。
非常持ち出し袋には、以下の持ち物を準備してください。
・飲料水(1人1日3リットル)
・非常食
・懐中電灯
・携帯ラジオ
・救急用品
・服用薬
・モバイルバッテリー
家族構成に応じて、乳幼児がいる場合はミルクや離乳食、高齢者がいる場合は常備薬やお薬手帳などを追加します。防災行政無線の内容は、自動電話案内サービスでも確認できます。複数の手段で情報を得られるようにしておくと安心です。
参考:鹿児島市|防災行政無線の放送内容の確認方法を教えて下さい
●停電への備えとして電源を確保する
長期間の停電に備えて、照明や通信の電源確保が欠かせません。停電に対する備えは、以下のアイテムを準備しましょう。
・懐中電灯
・ランタン
・予備電池
・モバイルバッテリー
非常時への備えとして、ポータブル電源の導入をおすすめします。容量500Wh以上のものであれば、スマホの充電やLEDランタンなどの使用が数日間可能です。ソーラーパネルと組み合わせることで、日中の充電により電力を補充できます。
停電時は冷蔵庫や照明の使用を最小限に抑え、スマホの画面輝度を下げるなど、電力消費を節約する工夫も大切です。
関連人気記事:南海トラフ地震に備える|地震に必要な防災装備と知っておきたい対策や行動
6.南海トラフに備えた電源確保なら「Jackery(ジャクリ)ポータブル電源」がおすすめ!

南海トラフ地震などの災害時の非常電源として「Jackery(ジャクリ)のポータブル電源」が最適です。ポータブル電源とは、コンセントが使える持ち運び式蓄電池のことで、停電時にスマホや照明などの電源を確保できる心強い備えになります。
Jackery(ジャクリ)は13年間の販売実績と全世界500万台以上の販売実績を誇り、防災製品等推奨品マークも取得済みの信頼できるブランドです。軽量・コンパクト設計で女性でも扱いやすく、ソーラーパネルとセットで太陽光充電も可能なため、長期間の停電にも対応できます。
避難所や車中泊での実用性も高く、静音レベル約30dB以下で周囲に迷惑をかけません。いざという時の備えとして、Jackery(ジャクリ)ポータブル電源で確実な電源確保を始めましょう。
7.鹿児島の地震や南海トラフに関するよくある質問
鹿児島の地震や南海トラフ地震について多く寄せられる疑問にお答えします。
●南海トラフ地震で1番危ない県はどこですか?
南海トラフ地震は、静岡県から宮崎県にかけての太平洋沿岸地域が最も危険とされています。とくに以下の県は、震度6弱以上の揺れと津波の高さも20mを超えると想定される地域です。
・静岡県
・愛知県
・三重県
・和歌山県
・愛媛県
・徳島県
・高知県
これらの地域は震源に近く、強い揺れと大津波の影響を受けやすい位置にあります。一方、鹿児島県は最大震度6強が想定されており、志布志湾沿岸では津波高6.4m程度が予測されています。ただし、被害の大きさは地形や耐震性などで異なるため、すべての地域で備えが欠かせません。
「1番危ない」という表現よりも、それぞれの地域特性に応じた対策を講じることが大切といえるでしょう。
参考
●南海トラフ大地震はあと何年後に来ますか?
どのタイミングで南海トラフ地震が起きるかは、現時点の科学では判断できません。ただし、過去の発生間隔から今後30年以内に発生する確率は80%程度とされており、いつ発生してもおかしくない状況です。
前回の南海トラフ地震である昭和東南海地震と昭和南海地震から約80年が経過しており、過去の発生間隔に近づいています。気象庁も「もしかしたら明日にも起こるかもしれません」と注意を呼びかけています。
災害はいつ起きてもおかしくありません。日ごろからの準備を安心につなげましょう。
参考
まとめ
南海トラフ地震で鹿児島県民が身を守るには、地域の特性を理解した備えと迅速な避難行動が重要です。
志布志湾や肝付町などの沿岸部は津波リスクが高く、霧島市や鹿児島市などの内陸部も活断層による強い揺れが懸念されます。複数の避難ルートを家族で共有し、防災アプリや緊急速報メールなどの情報収集手段を確保してください。
長期停電に備えてJackery(ジャクリ)のポータブル電源を準備し、いつ来るかわからない災害に対する安心できる環境を整えましょう。