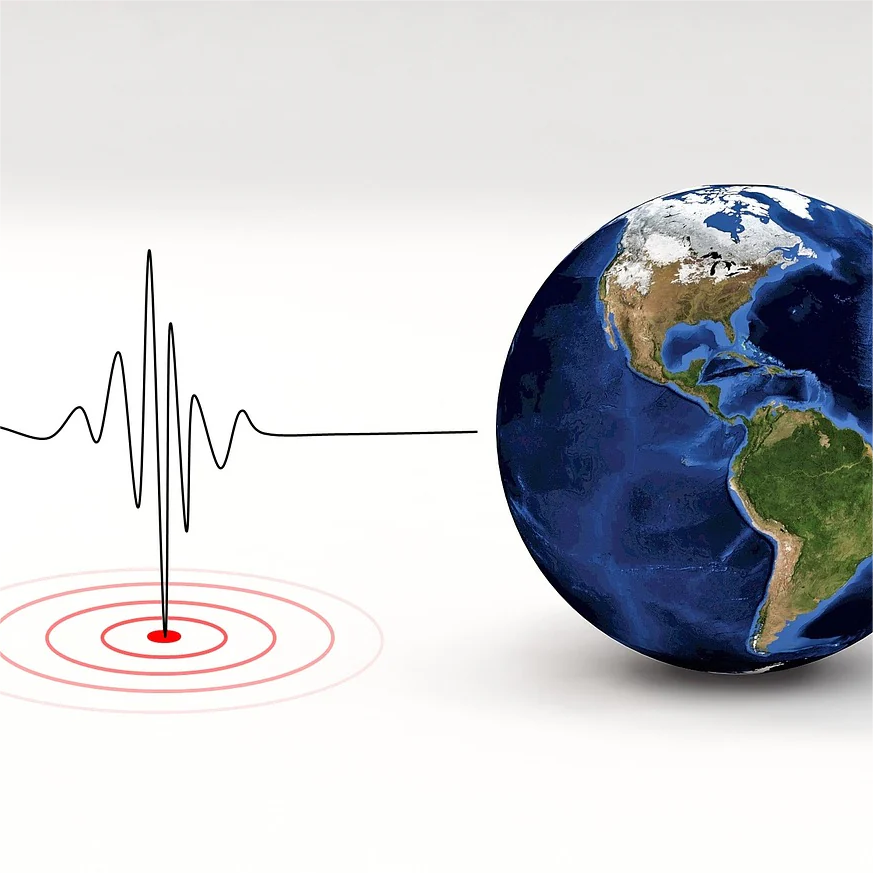1.南海トラフ地震とは?沖縄への影響を理解する
南海トラフ地震は、静岡県から宮崎県の沖合にかけて広がる海底の溝「南海トラフ」で発生する巨大地震です。沖縄は震源域から離れていますが、津波の影響を受ける可能性が高いため、正しい知識を身につけましょう。
●南海トラフ地震の概要と発生確率
南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界で、約100〜150年ごとに発生してきた大規模な地震。前回から約80年が経ち次の地震への警戒が必要な状況です。今後30年以内にマグニチュード8〜9クラスの地震が起きる確率は約80%とされています。
規模は東日本大震災に匹敵し、太平洋沿岸における震度7の揺れや10メートルを超える津波が発生する想定です。人口の多い広範囲に影響することから、大きな被害が懸念されています。
●沖縄は震源域から遠い?誤解と知っておくべき沖縄特有のリスク
南海トラフ地震の震源域は、四国沖から九州南部まで広がっていますが、沖縄県はこの震源域から約1000キロ以上も離れています。沖縄では震度3〜4の揺れが予測されており、建物の倒壊での人的被害が発生する可能性は低いでしょう。
しかし、距離が離れていても、必ずしも安全とは限りません。沖縄気象台によると、南海トラフ地震でマグニチュード9の地震が発生し震源地が沖縄に近い場合、約1時間弱で沖縄本島北部に3メートル超えの津波が到達すると予想されています。
沖縄ではとくに津波のリスクが高いため、危険性を理解しておくことが大切です。
●過去に沖縄を襲った津波の歴史から学ぶ
沖縄では1771年4月24日に発生した八重山地震による「明和の大津波」が、史上最大の津波災害として記録されています。津波被害の概要は以下のとおりです。
|
震源地 |
石垣島南東沖(石垣島南方約40km付近) |
|
地震の規模 |
マグニチュード7.4 |
|
津波の到達した最大の高さ |
最大約30m |
|
死者・行方不明者数 |
合計11,861人 (八重山地方:9,313人・宮古島地方:2,548人) |
|
死亡率 |
石垣島:48.6%・八重山地方全体:32.2% |
津波堆積物や津波石の調査から、1771年の「明和の大津波」と同規模の津波が、過去約2000年間で600年おきに4回ほど発生したと考えられています。
沖縄は歴史的に津波の被害があった地域であり、今後も同様のリスクがあるという認識を持つことが大切です。
関連人気記事:南海トラフが起きても安全な県ランキング|前兆・備え・危険な県も徹底解説
2.【2025年最新予測】南海トラフ地震で沖縄に具体的に何が起こるのか?
 南海トラフ地震による沖縄への影響について、最新の被害想定データに基づいて具体的に解説します。津波の到達時間から建物への影響、沖縄特有の課題まで詳しく見ていきましょう。
南海トラフ地震による沖縄への影響について、最新の被害想定データに基づいて具体的に解説します。津波の到達時間から建物への影響、沖縄特有の課題まで詳しく見ていきましょう。
●沖縄に到達する津波の高さと時間
沖縄県では地震発生後、最短で約1時間後に津波の襲来が予想されており、最大の津波高さは5メートルに達すると想定されています。地域別に見ると以下のとおりです。
・最大5メートルの津波想定(名護市・国頭村)
・最大4メートルの津波想定(糸満市・宮古島市など)
・最大3メートルの津波想定(那覇市)
・集落全体が浸水する可能性のある地域(沖縄本島北部の西海岸)
この津波によって最大で約10人の死者、避難者が約7,300人発生すると予想されています。観光客などは避難場所や経路を把握しておらず、避難が遅れることも想定されるでしょう。
参考:内閣府沖縄総合事務局|沖縄版南海トラフ巨大地震地域対策計画(第1版)
●想定震度と建物倒壊・インフラ寸断の危険性
南海トラフの震源から遠く離れた沖縄では、揺れは震度3〜4程度と予想され、深刻な建物被害は起きにくいと考えられています。
ただし、沖縄県内では周期の長い揺れ(長周期地震動)が発生する可能性もあり、高層ビルや石油タンクがゆっくりと長時間揺れる恐れがあります。建物の部材の破損や、タンクから液体が漏れて火災が起きるリスクもあるため、このような揺れには十分注意しましょう。
台風対策が中心の沖縄の建物は比較的強固ですが、耐震基準前の建物などは地震で損壊するリスクがあります。海岸沿いの道路や港湾施設に浸水や被災の可能性があり、地震規模に関係なく耐震対策が求められます。
●観光への打撃と復興への課題
南海トラフ地震の影響で、沖縄の観光業は大打撃を受ける可能性が高いです。観光客減少に加え、空の便が制限されることで、物資輸送にも影響します。
復興面では、沖縄県が本土から遠く離れている地理的特性により、救助の遅れや県内対応の限界が懸念されています。また、発災後も避難が長期化する見通しで、継続的な支援体制の整備が必要です。
このような離島特有の制約により、自助努力だけでは限界があるため、事前の備えと地域コミュニティの連携がより大切といえるでしょう。
3.沖縄で南海トラフの被害が大きくなると予想されるエリア
沖縄県内でも地域によって津波の影響度は異なります。とくに人口密度が高く、海に近い市街地や観光地では深刻な被害が想定されているため、具体的なリスクを把握しておきましょう。
●那覇市:港湾施設・商業施設・住宅地に津波リスク
那覇市は沖縄県の政治・経済の中心地として人口密度が高く、津波による被害が最も深刻になると予想される地域です。予想される被害を確認しましょう。
・観光客が多く避難が遅れる(観光エリア)
・倉庫・商業施設などが浸水する(港湾施設・海沿い)
・物流機能が停止(県全体への物資供給の遅れ)
・津波の想定高さは最大3メートル
津波発生時、那覇港周辺は地形の特性から浸水リスクが高い地域です。地理に不慣れな観光客の避難が遅れる可能性や、港湾の浸水で物流機能が止まるリスクもあります。
津波は最大3メートルと想定されているため、高台への避難ルートを事前に確認し、速やかに行動できる準備をしておきましょう。
●石垣市・宮古島市:漁港や観光エリアでの浸水被害に注意
石垣市と宮古島市は、離島という立地特性により本島以上に津波の脅威にさらされています。予想される被害は以下のとおりです。
・広範囲での浸水被害
・漁港や観光施設
・救援の遅延(離島であるため)
・津波の想定高さは最大4メートル
島全体が標高の低い地形のため広範囲での浸水被害が予想されます。両市では漁業と観光業が主な産業のため、港やリゾート施設の被災は経済への大きな影響が懸念されます。
さらに、離島であるがゆえに本島からの救援が遅れるため、島内での自助・共助体制の充実が不可欠です。
●名護市:市街地近くの海岸沿いに津波の可能性
名護市は沖縄本島北部に位置し、津波の想定高さが最大5メートルと県内で最も高い数値が予想されている地域です。予想される被害を見てみましょう。
・広範囲での浸水被害
・住民・観光客双方の避難が集中
・観光施設の被害
・津波の想定高さは最大5メートル
海岸沿いの地域では、住宅地と観光施設が混在しているため、地元住民と観光客の両方に対する避難対策が必要です。海岸線近くに宿泊施設や商業施設が増加していることから、施設利用者の安全確保が重要な課題となっています。
市内には比較的高台も存在するため、事前の避難ルート確認と地域全体での防災意識の向上により、被害の軽減が可能です。
関連人気記事:地震から津波までの時間は?過去の事例とシミュレーションで学ぶ防災対策
4.南海トラフ地震に備えた沖縄での防災対策3つ

沖縄特有の地理的条件を踏まえ、効果的な防災対策を講じることが重要です。津波対策や家の安全対策、離島での備えについて、すぐに役立つ方法を解説します。
①沖縄での効果的な避難方法と避難場所の確認
沖縄では限られた1時間のなかで避難する必要があるため、事前の避難準備が重要です。避難対策として以下のポイントを確認しましょう。
・指定緊急避難場所を確認する
・複数の避難ルートを事前に設定する
・ハザードマップで津波浸水想定区域を確認する
・海抜表示や津波避難ビルの位置を把握する
・定期的な避難訓練に参加する
地震はいつ起こるかわからないので、自宅だけでなく職場・子どもの学校・保育園などからの避難ルートも確認しましょう。車での避難は渋滞を招く恐れがあるため、徒歩避難を基本としてください。そのうえで、高齢者や障がい者への支援体制を地域で検討しておきましょう。
定期的な避難訓練が、津波時に迷わず行動するための大切な備えになります。
②沖縄の住宅における地震・津波対策
沖縄の住宅は台風対策を重視した設計が多いものの、地震に対する備えも欠かせません。築年数の古い家は耐震診断を受け、必要に応じて補強すれば、震度4程度の揺れにも備えられます。
また、以下の家具の転倒防止対策も実施します。
・L字金具で固定
・突っ張り棒(ポール)
・耐震マット・ジェルパッド
・家具の配置見直し
食器棚や冷蔵庫には突っ張り棒やL字金具を設置し、テレビなどの家電には耐震ジェルマットを活用しましょう。非常時に備えて、通路や玄関周辺には大きな家具を配置しないことが大切です。
津波対策では、2階以上の高い場所に非常用品を保管し、停電時でも避難できるよう懐中電灯やラジオを各階に配置します。津波浸水区域にある住宅では、屋上への避難経路や避難階段の設置を検討し、安全対策を強化しましょう。
③沖縄の地理的特性を考慮した防災グッズの準備
南海トラフ地震や台風などの災害に備え、支援が遅れやすい離島では、最低1週間分の備蓄が欠かせません。備蓄品は以下のようなものを準備しましょう。
・飲料水(1人1日3リットル)
・非常食(米・缶詰・レトルト食品)
・常備薬や救急用品
・携帯トイレ
・非常電源
沖縄は台風や停電が頻繁に発生するため、電気をためておけるポータブル電源はとくに重要な防災アイテムです。スマートフォンの充電だけでなく、扇風機や照明器具も使用でき、長期停電時の生活の質を大幅に向上させます。
Jackery(ジャクリ)のポータブル電源ならソーラーパネル付きで、電力復旧が遅れても継続的に電力を確保できるため安心です。
乳幼児がいる家庭では、ミルクやおむつなどの備蓄も忘れずに準備しましょう。とくに夏場は沖縄の気候に配慮して備蓄品を管理し、定期的な確認で品質を維持することが大切です。
関連人気記事:南海トラフ地震の対策を”今”はじめよう!今日来るかもしれない大地震の対策は?
5.南海トラフに備えた「ポータブル電源」を選ぶならJackeryがおすすめ!
沖縄では台風による停電が頻発し、数日から1週間以上の長期停電を経験することも珍しくありません。南海トラフ地震が発生すれば、本土からの電力供給や復旧支援が遅れ、深刻な停電の長期化が予想されます。
災害発生時には情報収集や照明、暑さ・寒さ対策において、電力は非常時の生命線といえます。全世界で500万台以上の販売実績があり、最大5年の無料保証もあるJackery(ジャクリ)のポータブル電源は安心して使える製品です。
ソーラーパネルとセットで使えば、長期の停電時でも電力を持続的に確保できます。停電時には冷蔵庫の維持や調理家電の使用にも対応でき、家庭での備えとして沖縄の災害に非常に役立つ防災アイテムです。
もっと多くの商品を見る
6.南海トラフ地震に関する沖縄県・自治体の公式情報と避難行動
正確な被害想定と適切な避難先を知るためには、公式情報の確認が不可欠です。沖縄県や各市町村が提供する最新の防災情報と、避難場所の正しい選び方を解説します。
●沖縄県・市町村の防災ポータルサイトとハザードマップの確認方法
沖縄県内の各市町村では、津波浸水想定や避難場所を示すハザードマップをウェブサイトで公開しています。
国土交通省の「重ねるハザードマップ」で、津波や土砂災害の想定区域を確認できるため、概要を把握しましょう。那覇市の「なはMAP!」や石垣市の「WEB版ハザードマップ」など、各自治体の専用サイトでは、詳細な地域情報や多言語対応版も提供されています。
情報は随時更新されるため、家族全員で避難先やルートを年に数回チェックして共有しましょう。
●指定緊急避難場所と避難所の違いとは?正しい避難先選び
南海トラフ地震などの大規模災害が発生した際、避難する場所には「指定緊急避難場所」と「避難所」の2種類があります。状況に応じて正しく使い分けるため、両者の違いを確認しましょう。
|
項目 |
指定緊急避難場所 |
避難所 |
|
目的 |
命を守るために一時的に避難する場所 |
災害後、一定期間生活を送るための場所 |
|
使用するタイミング |
津波・洪水・土砂災害などからすぐに避難する際 |
自宅が使えなくなった後に滞在する場合 |
|
滞在時間 |
一時的(短時間) |
中長期的(数日〜数週間) |
|
避難先の種類 |
安全な空き地・公園・学校の校庭など |
体育館・公民館など |
避難所には支援物資や情報が集まり、給水拠点や救護所としても機能します。まず命を守る避難場所へ避難し、その後必要に応じて避難所に移る流れが基本です。
7.南海トラフ地震で沖縄への影響についてのよくある質問

ここでは、南海トラフ地震が沖縄に与える影響について、よく寄せられる疑問について解説します。
●南海トラフ地震はいつ発生するのか?
南海トラフ地震の発生時期は予測できませんが、今後30年以内に約80%の確率で起きるとされています。南海トラフ地震は、約100〜150年ごとに発生する周期性のある地震です。すでに前回の発生から80年近く経っており、次の地震への警戒が強まっています。
2024年8月には日向灘の地震をきっかけに初めて臨時情報が発表され、地下のひずみが進んでいることが確認されました。発生時期は予測できないため、常に備えておく意識が求められます。
●南海トラフ地震が起きたら沖縄は安全でしょうか?
震源から約1000km離れる沖縄では、震度3〜4の揺れが想定され、大きな建物被害は少ないと考えられています。しかし、津波による影響は深刻で地震発生から約1時間後に最大5メートルの津波が到達すると予想されており、完全に安全とはいえません。
沖縄県は本土からの物資供給に依存しているため、本土の被災により食料や燃料などの物資不足が長期化します。
離島では救援が遅れるため、備蓄と避難計画の準備が欠かせません。日ごろから防災対策を意識して行動しましょう。
まとめ
南海トラフ地震は沖縄から離れた震源域で発生しますが、津波による深刻な影響が想定されています。震度3~4程度の揺れでも、最大5メートルの津波が約1時間で到達し、沿岸部では浸水被害が懸念されます。
離島の特性上、支援の遅れに備えて1週間分の備蓄と避難準備を整えましょう。沖縄では停電対策として、Jackeryのポータブル電源のような非常電源が充電・照明・調理に活躍します。災害時に備えて、家族で避難場所を確認し、防災意識を持つことが大切です。