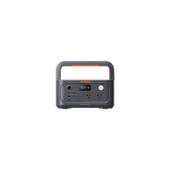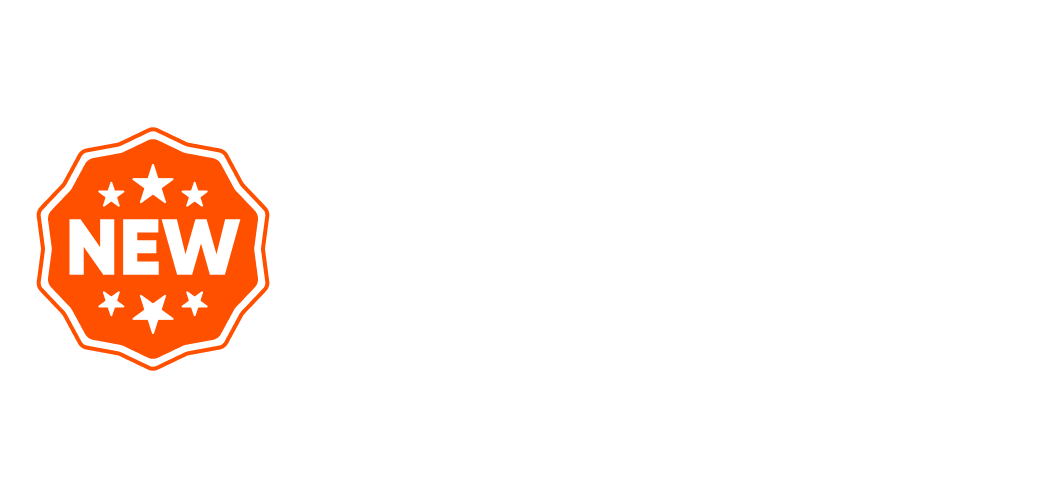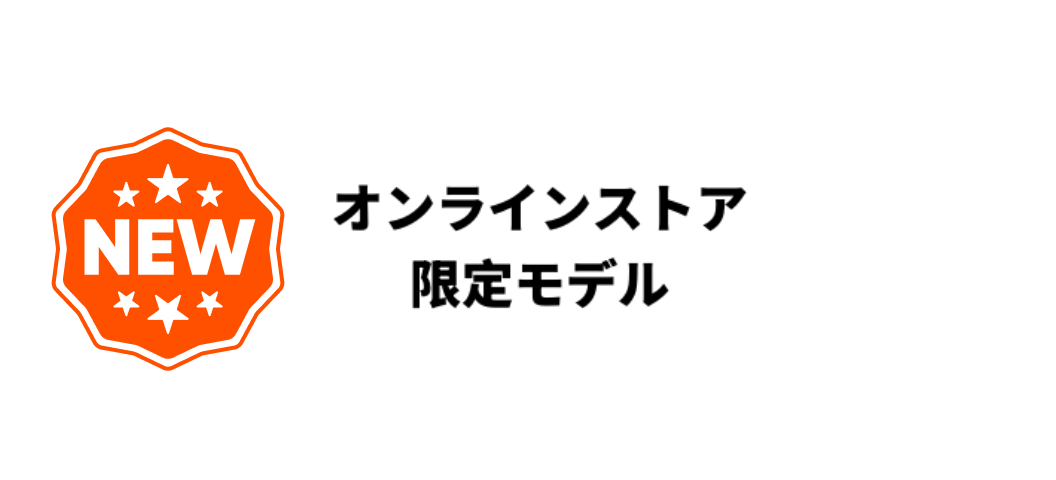1.南海トラフ地震が怖い!いつ来る?巨大地震が起こる仕組みを解説

南海トラフ地震は日本史上最大級の被害をもたらす可能性がある巨大地震です。現在、過去の発生パターンからいつ起きてもおかしくない状況で、南海トラフ地震の規模と被害想定から多くの人が怖いと感じています。
地震の仕組みと発生メカニズムを理解し、地震への不安を減らしましょう。
●南海トラフ地震は繰り返し発生する巨大地震
南海トラフ地震は偶然起こるものではなく、地球の活動によって繰り返し発生する巨大地震です。駿河湾から日向灘沖にかけてプレートの境界を震源域として、100〜150年間隔で繰り返し発生してきました。
参考:国土交通省 気象庁「南海トラフ地震について」
南海トラフ地震が起こる仕組みは、以下のとおりです。
1. 海側のプレート(フィリピン海プレート)が陸側のプレート(ユーラシアプレート)の下に1年あたり数cmの速度で沈み込む
2. 2つのプレートの境界が強く固着して、陸側のプレートが地下に引きずり込まれ、ひずみが蓄積される
3. 陸側のプレートが引きずり込みに耐えられなくなり、限界に達して跳ね上がることで地震が発生する
1→2→3の状態が繰り返され、南海トラフ地震はおおむね定期的に発生しています。
●一度で終わらない?南海トラフ地震は時間差で起こる可能性が高い
南海トラフ地震は、一度の地震で全てのエネルギーが解放されず、時間差で複数回発生する可能性が高いです。過去の事例を見てみましょう。
・1854年:安政東海地震(M8.6)→32時間後、安政南海地震(M8.7)が発生
・1944年:昭和東南海地震(M8.2)→2年後、昭和東南海地震(M8.4)が発生
最初の地震で建物が損傷した状態で次の地震が来ると、さらに危険性が高まります。時間差のある地震が起こる可能性を理解し、最初の地震後も警戒を緩めないことが大切です。
参考:国土交通省 気象庁「南海トラフ地震ーその時の備えー」
2.生き残る地域は?被害予想と南海トラフ地震後の日本
南海トラフ地震が発生した場合、日本の多くの地域で被害が予想されます。具体的な被害予想と地域ごとの影響について解説します。 お住まいの地域の危険度を知り、適切な対策を立てる参考にしてください。
①日本の半分が被災!震度7の強い揺れが日本各地で発生
南海トラフ地震の発生時は、日本の約半分の地域が被災すると予想されています。震度6弱以上または津波高3m以上となる地域は31都府県の764市町村に及び、面積は全国の約3割、人口は全国の約5割を占めると想定されています。
参考:内閣府「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書 概要」
南海トラフ地震で大きな被害が見込まれる地域は、以下の画像のとおりです。

特に震度7の強い揺れは、静岡県から宮崎県にかけての10県149市町村に及ぶと予想され、広範囲で建物倒壊のリスクがあります。また、震度6弱以上の揺れは神奈川県から鹿児島県にかけての24府県600市町村に及び、地震の影響は超広域にわたることが予測されます。
参考:内閣府「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書 概要」
以下の画像で赤く示された地域は震度7、オレンジは震度6強が予測されている地域です。

引用:国土交通省 気象庁「南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ」
とくに太平洋側の広い範囲で強い揺れが想定されています。日本全体の社会機能に大きな影響を与える可能性があり、各家庭の対策も不可欠です。
②広い地域で10mを超える津波が発生
南海トラフ地震では強い揺れだけでなく、関東地方から九州地方にかけて太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大きな津波の襲来が想定されています。
参考:国土交通省 気象庁「南海トラフ地震について」
南海トラフ地震の津波高の予想は、以下の画像のとおり広範囲に渡り10m以上です。

引用:国土交通省 気象庁「南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ」
南海トラフ地震で特に注意すべきは、津波の到達時間の速さです。下記の画像のとおり、多くの地域で地震発生から10分以内に第一波が到達すると予測され、早急な避難が求められます。
海岸への津波の到達時間(津波高 1m)
【ケース①「駿河湾~紀伊半島沖」に 「大すべり域+超大すべり」域を設定】

津波が到達するまでの時間は東日本大震災の際よりも早いと予想され、避難のための時間が限られています。
地震を感じたら、すぐに高台へ避難することが命を守るために大切です。「少し様子を見よう」という判断が命取りになる可能性があります。沿岸部にお住まいの方は、津波が起きたときの避難経路や避難場所を家族で事前に確認するのも必要な地震対策です。
③南海トラフ地震の死者数予想を県別ランキングで公開
南海トラフ地震による死者数は、最悪のケースで約17.7万人〜約29.8万人に達する可能性があります。
各都府県で死者数が最大となるケースの死者数の内訳は、以下の表のとおりです。
|
都府県 |
死者数の予測(約) |
|
静岡県 |
88,000人 |
|
和歌山県 |
53,000人 |
|
三重県 |
31,000人 |
|
高知県 |
30,000人 |
|
宮崎県 |
25,000人 |
|
徳島県 |
18,000人 |
|
愛知県 |
14,000人 |
|
愛媛県 |
9,200人 |
|
大分県 |
6,700人 |
|
大阪府 |
3,600人 |
参考:総務省「南海トラフ巨大地震の被害想定について(建物被害・人的被害)」
死因別では以下の想定が発表されています。
● 建物倒壊による死者が約7.3万人
● 津波による死者が約9.4万人~約21.5万人
● 地震火災による死者が約0.9万人
特に津波による犠牲者が多く、沿岸部での迅速な避難が死者数の減少に大きな影響を与えると考えられます。建物の耐震化や早期避難の徹底など、一人ひとりの備えが必要です。
参考:内閣府「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書 概要」
④ライフラインの9割以上が停止する地域多数
南海トラフ地震後は、以下の表のとおり広範囲でライフラインの機能停止が予想されています。
|
インフラ |
最大の影響範囲 |
特に影響が大きい地域 |
復旧の目安 |
|
上水道 |
約3,570万人が断水 |
東海三県、四国・九州の一部(8~9割が断水) |
発災から約1ヶ月で9割以上が復旧 |
|
下水道 |
約3,460万人が利用困難 |
東海三県、四国、近畿・九州の一部県(約9割が利用困難) |
発災から約1ヶ月で9割以上が復旧 |
|
電力 |
約2,930万軒が停電 |
東海三県・近畿三府県(約9割)、山陽三県(約3~7割)、四国・九州二県(約9割) |
需給バランス起因の停電は数日間で解消、電柱被害による停電は約1~2週間で復旧 |
|
通信(固定・携帯) |
固定電話:約580万回線通話不能 携帯:被災1日後に最大停波 |
全国的に通話困難(特に被災直後は輻輳) |
数日間で停電起因の障害は解消、通信設備の被害も約4週間で大部分が解消 |
|
都市ガス |
約180万戸で供給停止 |
東海三県(約2~6割)、四国(約2~9割)、九州二県(約3~4 割) |
約6週間で大部分が復旧 |
参考:内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について(施設等の被害)」
ライフラインの停止に備え、水や食料、簡易トイレの備蓄、ポータブル電源の確保など、1週間以上生活を維持できる準備が必要です。
結論:南海トラフで生き残れる可能性が高い安全な地域はここ
南海トラフ地震で生き残れる可能性が高い地域は、太平洋から離れた日本海側の地域や内陸部です。津波の心配が少なく、揺れも比較的軽度と想定されています。具体的には以下の地域です。
● 北海道
● 東北地方の日本海側
● 北陸地方
● 山陰地方
● 関東地方の埼玉県や東京都西部など内陸地域
しかし、南海トラフ地震以外の地震リスクもあり、どの地域に住んでいても防災対策は必要です。現在住んでいる場所のリスクを正しく理解し、地域に合った対策をしましょう。
関連記事:家庭用非常用電源おすすめ5選!停電中も冷蔵庫やエアコンを動かしたい人必見
3.南海トラフ地震が怖い人必見!生き残る確率を上げる防災対策5選

南海トラフ地震が怖い方にとって、具体的な対策を知ることが安心につながります。ここでは、生存率を高める南海トラフ地震の防災対策を5つ紹介します。
対策を今日から少しずつ始めることで、いざというときの備えを強化しましょう。
①家の耐震性を強化する
住宅の耐震性強化は、南海トラフ地震による死亡リスクを減らす効果的な対策です。建物の倒壊は地震による直接的な死因として多く、約7.3万人が建物倒壊で亡くなると想定されています。
参考:内閣府「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 報告書 概要」
特に1981年以前に建てられた住宅は、現在の耐震基準を満たしていない可能性が高く、耐震診断を受けるのがおすすめです。多くの自治体では耐震診断の費用補助を行っているため、お住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。
関連記事:【家族で生き抜く】災害に強い家の特徴とは?間取り・設備・メーカーを解説
耐震診断の結果、補強が必要と判断された場合は、耐震補強工事が必要です。耐震補強工事の費用は数十万円から数百万円かかることもありますが、自治体による補助制度を利用できる場合が多いです。
参考:東京都耐震ポータルサイト「耐震化助成制度」
②家庭内の安全対策を行う
地震の揺れによる家具の転倒や落下は、怪我の原因や避難経路の妨げとなります。室内の安全対策は比較的低コストで実施できる防災対策です。
家具や家電の転倒・落下防止の対策は、以下のとおりです。
● 棚やタンス、本棚などはL字金具や突っ張り棒、粘着マットなどで固定する
● 家具は出入り口を塞がない位置に配置し、寝具から離して設置する
● ガラス窓には飛散防止フィルムを貼る
あわせて、室内の整理整頓をするのもポイント。高い場所には重い物を置かず、重い物は下・軽い物は上に収納しましょう。また、棚や引き出しには飛び出し防止器具をつければ、中身の散乱を防げます。
関連記事:冷蔵庫の地震対策は転倒防止対策を!おすすめの転倒防止グッズや注意点を紹介
③避難経路や連絡方法を確認し、家族で共有する
家族がバラバラのときに地震が発生する可能性があります。スムーズに家族の安否を確認できるよう、事前に避難場所や連絡方法を確認し、全員で共有するのが大切です。
まず、自宅や職場、学校周辺の避難場所や避難経路を家族で確認しましょう。自治体が公開しているハザードマップを活用すると、津波や土砂災害の危険区域も確認できます。
津波の危険がある地域では、最寄りの津波避難ビルや高台を事前に把握し、実際に歩いて避難経路を確かめるのがおすすめです。
〇ハザードマップの一例

家族との安否確認方法も決めておきましょう。災害時は電話が繋がりにくくなるため、以下のような複数の連絡手段を確認しておいてください。
● 災害用伝言ダイヤル(171)
● 災害用伝言板サービス
● XやfacebookなどのSNS
小さなお子さんには、自分の名前や住所、連絡先を書いたカードを持たせておくと、はぐれた際の手がかりになります。
関連記事:災害時の連絡手段5選を徹底解説!携帯以外の安否確認方法も紹介
④防災用品や備蓄品の準備をする
南海トラフ地震発生後は、ライフラインの停止や物流の混乱により、必要な物資が手に入りにくくなります。日頃から防災用品や備蓄品を準備することが、生存率を高めるために必要な対策です。
避難する際にすぐに持ち出せる非常用バッグを用意しておきましょう。中に入れるべき主な物は、以下のとおりです。
・飲料水、食料(カップ麺、缶詰、ビスケット、チョコレートなど)
・貴重品(通帳、印鑑、現金、保険証など)
・救急セット(絆創膏、常備薬など)
・懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池
・携帯電話の充電器
・簡易トイレや衛生用品(トイレットペーパー、ウェットティッシュなど)
・季節に応じた衣類や防寒具
リュックサックなど両手が使える形のバッグに入れ、玄関など持ち出しやすい場所に保管しましょう。家族構成に応じて、オムツや生理用品、アレルギー対応食品なども準備する必要があります。
関連記事:外出時のもしもに備える「防災ポーチ」中身おすすめ10選
避難所の収容人数には限りがあり、自宅が無事であれば在宅避難が推奨されています。そのため、1週間程度は自宅で過ごせるだけの備蓄を用意しておくと安心です。
飲料水は1人1日3リットルを目安に備蓄が必要です。食料も同様に1週間分を目安に、缶詰やレトルト食品、乾物など、調理がいらないか簡単にできるものを選ぶと良いでしょう。
備蓄は普段から使っている食品や日用品をやや多めに買い置きし、使ったら補充する「ローリングストック法」がおすすめです。無駄がなく、常に新しい状態を保てます。

水や食料以外にも、簡易トイレや生活用水(風呂の水をためておくなど)の確保も忘れずに行いましょう。
関連記事:在宅避難の備蓄品ガイド!快適に自宅避難するグッズは?必要なものを徹底解説

災害時の電源確保は情報収集や連絡手段の維持に不可欠です。特に南海トラフ地震では広範囲で長期間の停電が予想されるため、ポータブル電源の準備がおすすめです。
ポータブル電源は大容量でACコンセントが使えるのがポイント。下記のように活用すれば、避難所生活や在宅避難時でも安心して過ごせます。
・寒い冬でも電気毛布や電気ヒーターで温まれる
・スマホを繰り返し充電できるので家族との連絡や情報収集ができる
・電気ケトルでお湯を沸かして食事を作れる
ソーラーパネルと組み合わせて使用すると、長期の停電時でも電力を確保できます。
関連人気記事:非常用ポータブル電源おすすめ9選!選び方や災害での使い道も解説
⑤防災知識の確認と定期的な見直しをする
防災対策は一度行えば終わりではなく、定期的に見直しと更新が必要です。
家族や身近な人と防災について話し合う機会を定期的に持ちましょう。地震発生時の役割を下記のように振り分け、実際に行動してみると、地震のときにスムーズに避難できます。
・ガスの元栓を締めるのはお父さん
・非常用持ち出し袋を持ち出すのは自分
・ペットの対応をするのはお母さん
※あくまで例ですので、家族の状況にあわせて役割を分担してみてください。
備蓄品や非常用持ち出し袋の中身も定期的にチェックし、賞味期限が切れたものは新しいものに交換しましょう。また、多くの自治体や町内会で定期的に訓練が行われているため、積極的に参加しましょう。
関連記事:【防災クイズ】小学生から大人・高齢者向けまで!防災対策に役立つ豆知識
4.【命を守る】南海トラフ地震が来たら取るべき行動は?
南海トラフ地震が実際に発生した場合、どのように行動すれば命を守れるのか、地震発生時から時系列に沿って具体的な行動を解説します。
1. 強い揺れを感じたら、まずは身の安全を確保する
2. 揺れが収まったら、火の元を確認し、ガスの元栓や電気のブレーカーを切る
3. ドアや窓を開けて避難経路を確保する
4. 沿岸部にいる場合は、揺れがおさまったらすぐに津波から避難する
5. 避難所へ向かう際は、道路の損傷や落下物に注意し、できるだけ広い道を通る
6. 避難所に到着したら、受付で名前を登録し、避難所のルールに従う
7. 家族との連絡は災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板サービスを活用する
8. 余震に備え、危険な場所には近づかないようにする
地震が起きたときのシチュエーション別の具体的な行動は、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:地震が起きた時に取るべき行動を徹底解説!やってはいけないことや持ち物なども紹介
大規模災害時は行政の支援も限界があるため、各家庭での防災対策が大切です。日頃から地震に備えておけば、南海トラフ地震から自分や家族の命を守れます。
5.南海トラフが怖いなら「Jackeryポータブル電源」でライフラインを守ろう

南海トラフ地震ではライフラインの停止が広範囲で起こると想定されています。大規模災害が起きたときは、被災範囲も広く復旧に時間がかかるため、電力を自宅でまかなえると安心です。
Jackeryのポータブル電源は世界販売台数が500万台を超え、多くの家庭で防災グッズとして活用されています。Jackery Solar Generatorシリーズはソーラーパネルとセットした製品で、停電が長期化しても持続的に電力の確保が可能です。
Jackeryのポータブル電源はコンパクト・軽量モデルが多く、持ち運びもしやすいうえに狭い避難所でも場所を取らず使えます。災害時は避難所生活を快適に送ることもできます。ポータブル電源を準備して、南海トラフ地震が起きたときも安心して過ごしましょう。
6.「南海トラフ地震が怖い」に関するよくある質問
多くの方が抱える南海トラフ地震に関する疑問に答えます。正確な情報を知ることで不安を軽減し、安全に過ごす対策を立てましょう。
①南海トラフ地震が怖いから移住はあり?
南海トラフ地震への不安から、リスクの低い地域への移住は一つの対策です。北海道、東北地方の日本海側、北陸地方などは、南海トラフ地震の影響が比較的少ないと考えられます。
ただし、移住を検討する際は、地震以外の災害リスク(豪雪、洪水、火山など)も検討が必要です。また、移住すると仕事や家族、コミュニティとのつながりなどにも影響します。
現実的な対応としては、今の住まいの耐震化や防災対策を徹底すると、現在の場所でも安全性を高めることが可能です。
②地震が怖くて眠れない時は、何をすれば気を紛らわせる?
地震が怖いせいで眠れないときは、不安の正体を明確にしましょう。漠然とした不安よりも「何が怖いのか」を具体的に考え、下記のように対策を実行すれば、不安が軽減されやすいです。
● 家具が倒れて怪我をするのが怖いなら、家具を金具で固定する
● 被災時の生活が心配なら、非常用持ち出し袋や備蓄品の準備をする
● 津波による被害が怖いなら、避難経路や避難場所を確認する
信頼できる情報を得ることも大切です。不確かな情報や噂に惑わされず、気象庁や自治体が提供する正確な情報を参考にしましょう。ただし、就寝前に不安を煽るような情報に触れることは避けるべきです。
③南海トラフ地震で一番危ない県はどこ?
南海トラフ地震で一番危ない県は、死者数が全体の約3割、最大88,000人と予想されている静岡県です。
参考:総務省「南海トラフ巨大地震の被害想定について(建物被害・人的被害)」
静岡県は震源域に近く強い揺れが予想され、また沿岸部では高い津波が予想されています。特に駿河湾沿岸や遠州灘沿岸の低地部は、津波による甚大な被害が懸念されている地域です。
④南海トラフ地震はあと何年でくる?予想日は?
政府の地震調査委員会は、今後30年以内に南海トラフ地震(マグニチュード8〜9クラス)が発生する確率を80%と評価しています。南海トラフ地震は約100〜150年間隔で繰り返し発生しており、前回の昭和東南海地震(1944年)・昭和南海地震(1946年)から70年以上が経過しました。
参考:政府広報オンライン「南海トラフ地震に備えよう!南海トラフ地震臨時情報が発表されたら?」
南海トラフ地震の発生時期を正確に予測するのは現在の科学技術では難しいです。しかし、過去の発生パターンからある程度の予測はされています。「明日起きてもおかしくない」という意識で防災対策を進めましょう。
⑤東日本大震災と南海トラフ地震どっちが強い?
規模と被害想定の面では南海トラフ地震が東日本大震災を上回ると予測されています。
東日本大震災はマグニチュード9.0で、死者・行方不明者は約2万人でした。一方、南海トラフ地震は最大マグニチュード9.1と予測され、死者数は最悪の場合約30万人に上ると想定されています。
被災範囲も南海トラフ地震の方が広く、影響を受ける都府県は31に及び、日本の人口の約半分が暮らす地域が被災すると予想されています。経済的損失も東日本大震災の16~25兆円程度を大きく上回り、最大220兆円に達する可能性があるとの想定です。
参考:内閣府「(2)東日本大震災の経済的影響の特徴」
7.まとめ
南海トラフ地震は最大で約30万人の死者が出る被害想定が出ており、日本の多くの地域に甚大な被害が起こりかねません。地震に対して正しい情報を得て、防災対策を行えば「怖い」という感情を減らせます。
大規模災害時は電力や水道などのライフラインが止まる可能性が高いです。広範囲で被害が発生すると救助や支援も遅れるため、各家庭での対策が必須。まずは水や食料などの備蓄品とポータブル電源の準備から始めましょう。